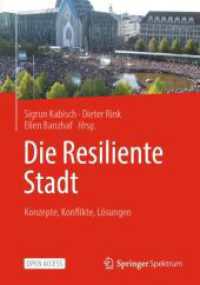内容説明
芭蕉に執念した山本健吉ならではの「奥の細道」現代語訳と鑑賞を堪能して下さい。さらに究極の芭蕉評論「軽み」の論も収載しました。
目次
「奥の細道」現代語訳・鑑賞(日光路(江戸深川‐殺生石 芦野)
奥州路(白河‐平泉)
出羽路(尿前‐象潟)
北陸路(越後‐大垣))
「軽み」の論(即興と眼前体;「言ひ了せて何かある」;方法論を超えて;さび・しをり・細み;単行本「後記」;『奥の細道』(一)
『奥の細道』(二)
『奥の細道』(三))
著者等紹介
山本健吉[ヤマモトケンキチ]
1907年~1988年。明治40年、長崎県生まれ。父は明治期の評論家・小説家である石橋忍月。折口信夫に師事し、民俗学の方法を学ぶ。昭和9年創刊の「俳句研究」編集長として中村草田男ら人間探求派を世に送り出す。昭和24年より評論家として、文芸評論のほか、俳句の評論や鑑賞を執筆。昭和58年、文化勲章受章。昭和63年、5月7日没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
26
最近『奥の細道』に興味を覚えています。まだ鑑賞できるほど読み込んでいませんし、理解しきれていないと感じていますが、好きな部分ができはじめましたのて、いろいろな関係図書を読んでいこうと思いました。2023/06/21
クックーナ
1
その道のプロも参考にし、定評のある文芸評論家、山本健吉氏。やはり、超一流のプロの視点から少しでも学びたいと思って購入したが、私自身がつい数日前におくのほそ道を読み直し始めた程度の人間。古典にも疎く、俳句の世界の評価基準なども全く知らないわけで、鑑賞の部分については、ズバリ難しく頭がこんがらがった。これがわかる人間になりたいと思うばかりである。とはいえ、専門書の中ではかなり平易な言葉で書かれている類かとは思う。私同様、ド素人の方には、長谷川櫂氏などから芭蕉をはじめ俳句の世界観を辿るほうがいいかもしれません。2018/07/20