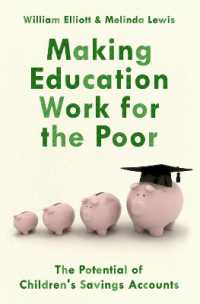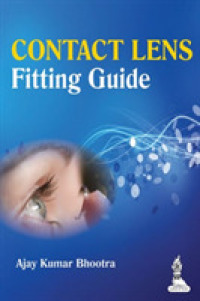内容説明
日本語は、擬音語・擬態語がとても多い。感覚的な表現であるこのことばは、絵本のなかで重要なはたらきをしている。特に、微妙なニュアンスを、いかようにも表現できるのが擬態語の魅力だ。絵本のなかで、そのおもしろさをさぐってみた。
目次
第1章 擬音語・擬態語を調べる(はじまりは、松岡享子さんとの出会いから;『はなをくんくん』のタイトルに「あれ?」;擬音と擬音語は、どう違う?;『もこ もこもこ』は、ことば絵本の歴史を変えた;日常生活には擬音語・擬態語がいっぱい ほか)
第2章 擬音語・擬態語を楽しむ(擬音語・擬態語のおもしろさを軸に展開している絵本;擬音語・擬態語をところどころ効果的に使っている絵本)
著者等紹介
後路好章[ウシロヨシアキ]
1940年、北海道美瑛町に生まれる。北海道大学で教育学を修める。学研、あかね書房、アリス館の編集長を経て、アリス館相談役。先生方に「絵本を使ったおもしろい授業を」の講演を展開中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒラP@ehon.gohon
8
擬態語、擬音語って、どことなく懐かしくて、少しばかり恥ずかしくて、然り気無く心温まる、魔法のような言葉だと再確認させてくれるような本です。 絵本の世界では、饒舌な文章は要らなくて、凝縮した言葉数で、見る者を包み込む事が望まれるのです この本は、ある意味解説書ですが、絵本の紹介や、擬態語、擬音語の効果を読んでいるうちに、心がほんわりほこほこしてきました。2016/05/06
ペミカン
1
擬音語擬態語は品がなくて嫌いだと言っていた三島由紀夫も、けっこう使っている・・・笑 「うっとり」「くっきり」まで無くすのは無理でしょう。 主に年少向け絵本の紹介。長新太では豊かな表現文化、と納得するけれど、漫画ではどんどん造語されて・・視覚感覚的言語との印象もある。2013/09/02
さちこ
1
やばい!卒論の先行研究か!?って焦ったけど、これは読み物に近いかな。。。参考文献。2010/01/28
ムク
0
日本語の豊かさ・奥深さを再認識。2009/01/24
クジラ
0
最近オノマトペを使ったカードゲームがあることを知って、本書を読んでみた。軽い感じで読めて、面白かった。2024/12/06