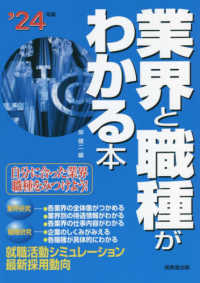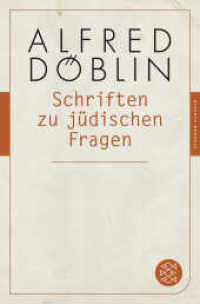内容説明
ぼろきれと骨から紙を。ススと亜麻仁油からインクを。そして、鉛と錫から活字を…。グーテンベルクは、どのようにして、それまでだれも見たことのなかったこの、ふしぎな機械を作りあげたのか?活版印刷誕生の秘話。中世ヨーロッパの人びとの暮らしぶりを、あざやかに伝える美しき歴史絵本。
著者等紹介
ランフォード,ジェイムズ[ランフォード,ジェイムズ] [Rumford,James]
大学での教師生活を経て、絵本作りを手がけはじめ、1996年に最初の絵本「The Cloudmakers」を刊行。ジェーン・アダムズ児童図書賞オナー賞の「Silent Music」をはじめ、絵本作品多数
千葉茂樹[チバシゲキ]
国際基督教大学を卒業後、児童書編集者を経て翻訳家に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
127
グーテンベルクが発明した機械とそこからできた書物の原材料などについて美しい色合いの絵で説明してくれます。インク、点字、紙がどのようにつくられたかもよくわかります。それをさらに金などを使ってか飾り文字を書き羊皮紙で本のカバーをつくるところまでを絵で示してくれます。すばらしい本です。2019/10/11
Hideto-S@仮想書店 月舟書房
99
1450年頃、ドイツのマインツ市に不思議なものが現れた。ぼろ切れと骨から作った紙。亜麻仁油とススを混ぜて作ったインク。溶けた鉛を鋳型に流し込んで作った活字。それらをオーク材を切って削ってネジを付けた機械にセットする。それから職人の手を経て完成したもの=本は世界を変えた。「過去1000年で最も影響力のある人」と称されるグーテンベルクの生涯は謎に包まれている。彼が作った聖書は50部弱が現存し、そのうちの一冊は慶應義塾大学図書館に所蔵されているそう。その制作過程を想像を交えて紹介した絵本。2013年度4月初版。2016/05/04
tokotoko
71
最新の技術を駆使して作られたこの本は、絵本の力を最大限に使って、気持ちよく、知識を広げてくれます。1450年頃のお話です。なぞなぞみたいにね、「いったい、なんだとおもう?」って聞きながら進めてくれるので、どんどん知りたくなります。絵も本格的です。子供の頃から絵本が大好きだった作者が、2年の歳月をつかって制作したそうです。知識と共に、この絵本に宿る作者と訳者の思いや願いも、たーくさんの人が受け取り続けてくれたらいいなぁー!って思います。2015/01/04
けんとまん1007
56
グーテンベルクと言えば、活版印刷。その印刷を構成するものが、一つずつ、わかりやく絵で書かれているので、なるほどという納得感が、とても大きい。印刷というしかけができたおかげで、今の時代があるのだと思うし、それがなかったら、いったいどうなっていただろうと、想像すらできないくらいだ。最初は文字を、一つずつ組んで・・・から、今は、どんな技術なんだろうか。デジタル処理から、印刷できるまで、凄いスピードなんだろうっと思う。2016/08/12
ちはや@灯れ松明の火
56
グーテンターク!ドイツのマインツ市にあらわれて、みんなを夢中にさせたもの。いったい、なんだとおもう?ぼろきれと骨から、ススと亜麻仁油から、なにができる?岩山のヤギの毛皮は、アフリカの川の砂金は、なにに変わる?鉛と錫を溶かして固めて、オークの木材を組み立てて、なにをはじめる?さあ、準備はできたぞ。彼が作ったふしぎな機械が美しい本を生み出した。魔法みたいで魔法じゃない。たくさんの本が生まれて、世界の歴史をすっかり変えてしまった。魔法じゃないのに魔法みたいに。いったい、だれだとおもう?彼の名はグーテンベルク!2016/03/15