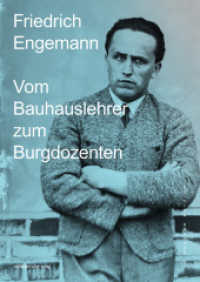出版社内容情報
パトリックは9歳。炭坑で働き事故で死んだ。過酷な労働をする子どもたちがいた。写真家ルイス・ハインが写した彼らの日常。子どもの人権を写真で訴えた一カメラマンの貧しくひたむきな生涯を56点の写真と共に語る
1997年度 産経児童出版文化賞 フジテレビ賞 受賞
中学生~大人まで
内容説明
マニュエルは5歳。カンヅメ工場で働く。アンジェリカは3歳。1日に540個の造花をつくる。パトリックは9歳。炭坑で働き、事故で死んだ。過酷な労働をする子どもたちがいた。写真家ルイス・ハインが撮影した彼らの日常。この写真がアメリカの良心をゆさぶり「子どもの人権」について考えるきっかけを与えた。
目次
第1章 カメラと勇気と
第2章 写真家への道
第3章 百聞は一見にしかず
第4章 工場で働く子どもたち
第5章 少年炭坑夫
第6章 街角と農場の子どもたち
第7章 アメリカを変えた男
第8章 炭坑、工場などで働く子どもたちによる『“非”独立宣言』
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
59
ご感想に惹かれて。インドの不可触民の児童労働や東南アジア児童の住み込み家事使用人のかかわる本を読んだ所だったので、アメリカの児童労働を写真で訴えた本書はとても興味深かった。20世紀初頭の工業製造業・炭坑・農場での児童労働の実体。工場・炭坑の写真に黒人が見えない。南部では特に工場の仕事は農場を棄てて都市部に流入した貧困層の白人もしくはヨーロッパ系移民に限られたという。では、黒人及び少数民族は?家族ぐるみでさらに労働規則が及ばない農場の臨時雇い・季節労働者となったという。労働者内格差の端緒をみた思いである。2022/11/16
コットン
58
1900年初頭に活躍した写真家ルイス・ハインによるアメリカ近代化の影の一つといっていい劣悪環境で働いていた子供たちのポートレートをラッセル・フリードマンがルポルタージュ風にまとめたもので、ひしひしと子供たちの悲惨な状況が写真を通して伝わってくる。2020/02/19
マリリン
48
「わたしはただ美しい子供たちを写しただけ」...心を揺さぶられた。3才や5才でも過酷な状況下で労働しなければならない当時(1900年の初頭)の時代背景を想うと胸が熱くなる。特に少年炭鉱夫の項。その動労の実態を旧式の箱型カメラで写し、アメリカを変えた写真家ルイス・ハインの視線はどこまでもあたたかく優しい。子どもたちがハインを信頼しきってレンズに向ける視線。 貧困の中で生き、その生涯を子供たちの生活・労働を守る為に捧げた清らかな魂を感じたノンフィクションであり写真集。そして当時のアメリカを知る貴重な作品。 2022/11/24
アナクマ
44
1900年代アメリカ。義務教育の法制化など遥か高望みの頃、労働搾取の対象だった子どもたちの写真。1枚目、綿花を摘むマートは5歳。◉とにかく力のある写真に鷲掴みされる。見ながら=被写体から見られながら、これは日本でも諸国の奴隷制下でもあったこと、否、現在進行形で「安く・速い」商品を購入している我々に向けられた眼差し…と、オタオタすること必至。◉貧しかったハイン(撮影者)を救ったのは教育と技芸。「私が問題にしているのは、技術を身につけさせるためではなく、より多くの利益を得ようとして子どもを雇うことなのです」→2021/03/22
たまきら
33
先日読んだ小説に登場したハイン。彼の写真をまとめてみたいと思い、写真だけでなくかれの業績もまとめてあるこの本を手に取りました。娘よりも幼い子供が毎日毎日単純作業に従事し、手にしていた金額の少なさに仰天。こどもたちのおかげで手にする富、あるいは安価な品物。今だって続いているシステムです。ぜひ娘と共有しようと思っています。2020/04/01