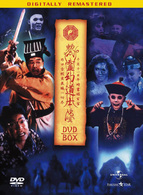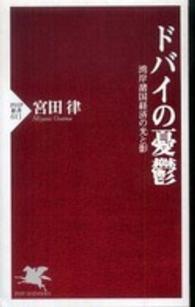出版社内容情報
◆名古屋の人はなぜ小倉トーストが好きなのか?
◆カレーの元祖が大阪に多いのはなぜ?……
〈”県民食”に風土と歴史あり〉
日本全国の土地土地で人々のおなかを満たしてきた22の食べものを深掘り。
”あの美味しいもの”への理解と愛が深まる、食文化・教養エッセイ。
内容説明
土地土地で食いしん坊たちのおなかを満たしてきた22の食を深掘り。日本全国の“旨いもん”への知識と愛が深まる、食文化・教養エッセイ集。
目次
道東ではなぜ牛乳豆腐が生まれたのか?
岩手ソウルフードにはなぜ、三つも麺類があるのか?
忘れられない、十和田湖のきりたんぽ
山形の食文化は、なぜ特別なのか?
信州蕎麦は冷たいのが正解?
金沢の醤油はなぜ甘い?
東京人はなぜ讃岐うどんを愛するのか?
東京と紅茶は相性が悪いのか?
浦和はなぜウナギが名物なのか?
名古屋人はなぜ小倉トーストが好きなのか?〔ほか〕
著者等紹介
阿古真理[アコマリ]
作家・生活史研究家。1968年兵庫県生まれ。食のトレンドと生活史、ジェンダー、写真などのジャンルで執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
136
テレビのケンミンショーに出てくる食のエピソードを解説するような、肩の凝らなさを楽しんだ。なぜ冷麺や豚骨ラーメン、小倉トーストにハード系パンなどが各地に根付きソウルフード化したのか、題名通り大胆に推理していく。自分の経験や調査から論じるので全てが正しいとは思えないが、食に関する大著のある筆者が語るだけに「なるほど」と同意してしまうのだ。特に関西でのミックスジュース人気や、小さな店に意外と旨いカレーがある理由などは、大阪在住時を思い出して納得させられる。こうしたトリビアの積み重ねが、本書のうま味を増していく。2023/06/25
岡部敬史/おかべたかし
93
「大胆推理!」というのが、生きてたなー。いろいろ気づきがあったのですが「東の朝炊き、西の昼炊き」ということばを初めて知った。これはかつて1日に一度しか米を炊かないときに、関東は朝、関西は昼に炊いていたという。それが遠因となって関西では朝ごはんにパンを食べる人が多いのではないかという推理。よく言われる「関西人は新しいもの好きだから」よりよっぽど説得力がある気がしましたよ。2023/11/06
kinkin
83
全国の食文化を探求している著者による地域の食レポート。私はあんまり食と言うものにこだわらないほうだ。どこそこのなに何がうまいと言われてもそこまで行って食べることはないし、まして行列のできるところなど真っ平ごめんだ。この本で必ずしも関東人がうどんが好きとは限らないし、関西の出汁と関東の出汁の考察や、名古屋の喫茶店文化も面白かった。私も岐阜で初めてモーニングが出てきた時は本当に驚いた。小さな国の中でこんなに多彩な食文化があるのは日本ぐらいかも。あと牛乳豆腐というのを食べてみたい、図書館本2025/03/28
きみたけ
71
ちょっと息抜き😙亜紀書房ウェブマガジン「あき地」に連載されたものに三編の書き下ろしを加えてまとめた一冊。著者は食のトレンドと生活史、ジェンダー、写真などのジャンルで執筆活動している、作家で生活史研究家の阿古真理さん。九州四県以外の都道府県を訪れたという著者が、記憶に残る食のエピソードを厳選し、食べものから地域の文化や歴史を考えるキッカケを与えてくれます。大阪人としては「大阪人はなぜミックスジュース好きなのか」が興味津々で、サンガリアの「みっくすじゅ〜ちゅ」が出てくるかと思いきや、出てきませんでした😑2024/07/24
たまきら
38
読み友さんの感想を読んで。秘密のケンミンSHOWという番組を時々見て大笑いしている自分。人間の地域性・ローカルネタは大好物です。そこに食べ物が入ってくるのですから見逃せません。知っているものも知らなかったものも楽しみました。読んでいたらすっかり長野にそばを食べに行きたくなりました。あと、大阪の松葉家さん。美味しかったなあ…。読みながらずっと過去に食べた美味しいものがフラッシュバック。2023/12/27