- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
《そうだ、大槌だけの新聞をつくろう!》
町民の、町民による、町民のための小さな「大槌新聞」10年の奮闘記
----------------------
自分が生まれ育った町に何の関心も持たず、文章もろくに書いたことがない引っ込み思案な「わたし」。
震災を機に踏み出した、町と自身の再生への道のり……。
被災地復興の光と影、真のメディアとジャーナリズムのあり方を忖度なくあぶり出した、自伝的ノンフィクション。
内容説明
自分が生まれ育った町に何の関心も持たず、文章もろくに書いたことがない引っ込み思案な「わたし」。震災を機に踏み出した、町と自身の再生への道のり…。被災地復興の光と影、真のメディアとジャーナリズムのあり方を忖度なくあぶり出した、自伝的ノンフィクション。
目次
第1章 生きる意義を見失っていた震災前
第2章 大槌町の新聞を作りたい
第3章 地域メディアミックスに挑む
第4章 中断された震災検証
第5章 解体された大槌町旧役場庁舎
第6章 本当の復興はこれから
第7章 創造的メディアをめざして
著者等紹介
菊池由貴子[キクチユキコ]
1974年岩手県大槌町生まれ。岩手大学農学部獣医学科(現・共同獣医学科)在学中に潰瘍性大腸炎になり劇症型心筋炎を併発。二度心停止するも奇跡的に生還するが、入退院の繰り返しで大学を中退。東日本大震災前に結婚するも数年で離婚。震災後、情報不足に陥った経験から2012年6月に大槌新聞創刊。再婚と離婚を経て2016年4月に一般社団法人大槌新聞社設立。取材や執筆、編集に加え広告営業や事務までをひとりでこなす。第3回東日本大震災復興支援坂田記念ジャーナリズム賞、第2回エルトゥールル号からの恩返し日本復興の光大賞、令和元年度「新しい東北」復興・創生顕彰など受賞。大槌新聞の定期発行は2021年3月に終了。現在はオンラインによる講演や勉強会、語り部活動、執筆などを続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
けんとまん1007
泰然
いちろく
kan




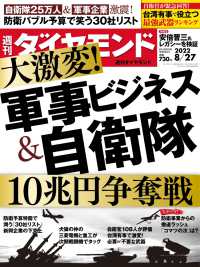

![モーニング 2019年25号 [2019年5月23日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0702195.jpg)


