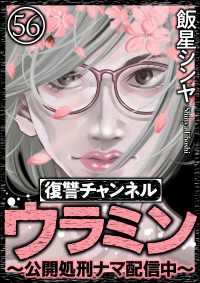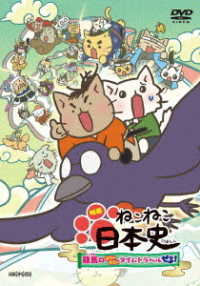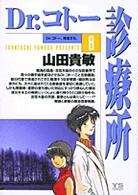内容説明
「不安障害」「依存症」「うつ病」「末期ガン」等への医学的利用の可能性と、“変性する意識”の内的過程を探る画期的ノンフィクション。『雑食動物のジレンマ』『人間は料理をする』の著者が丁寧な取材で幻覚剤の歴史を紐解き、自らも体験することで得た最新の知見と示唆の書。ニューヨークタイムズ紙「今年の10冊」選出(2018年)。
目次
プロローグ 新たな扉
第1章 ルネッサンス
第2章 博物学―キノコに酔う
第3章 歴史―幻覚剤研究の第一波
第4章 旅行記―地下に潜ってみる
第5章 神経科学―幻覚剤の影響下にある脳
第6章 トリップ治療―幻覚剤を使ったセラピー
エピローグ 神経の多様性を讃えて
著者等紹介
ポーラン,マイケル[ポーラン,マイケル] [Pollan,Michael]
作家、ジャーナリスト、活動家。ハーヴァード大学英語学部でライティング、カリフォルニア大学バークレー校大学院でジャーナリズムを教える。卓抜したジャーナリズムの手法に、人類学、哲学、文化論、医学、自然史など多角的な視点を取り入れ、みずからの体験も盛り込みながら、植物、食、自然について重層的に論じることで知られる。2010年、「Time」誌の「世界で最も影響力を持つ100人」に選出。受賞歴多数
宮〓真紀[ミヤザキマキ]
英米文学・スペイン語文学翻訳家。東京外国語大学外国語学部スペイン語学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヘラジカ
61
なんと面白く、なんと刺激的な本だろう。幻覚剤について医学の効能を説明するだけに留まらず、知覚への影響や潜在性、宗教/スピリチュアルと科学の橋渡し的役割まで、タブー視されてきた世界に深く鋭く切り込んでいる。依存性が高い危険薬物と一緒くたにされてきた幻覚剤が、精神世界のフロンティアを拡張・探訪するための可能性を秘めていると説いた名著。ドラッグについて書かれた本を気軽に手にした結果、人間の遠大なる内面世界を知ることになるとは思いもしなかった。こちらもノンフィクションながら今年度のベスト候補。2020/05/25
よしたけ
57
幻覚剤によるさまざまなトリップ現象が語られ、試してみたいとまでは惹かれなかったが、こんな世界があるんだと勉強に。過去にはLSDを含むドラッグは認知能力等を大幅に高める薬、精神疾患に効く薬として、米国で大量消費されたと聞くと隔世の感を感じるとともに、麻薬の合法効果が進むなど、揺り戻しも感じる。いわゆる麻薬だけではなく、痺れキノコなど、種類も多種多様だ。麻薬なんて自分の生活とは関係ないとたかを括っていたが、奥が深く人類の歴史で果たしてきた役割も確かにあったことを理解できた。2022/04/12
carl
24
幻覚剤は、よく聞くドラッグとは違うようだ なんだかんだ言って幻覚剤を使用したいんじゃない?って感じだった 情報大でした 2022/05/09
くさてる
22
誠実な語り口やバランスの取れた観点などが好きで、これまでに翻訳された著者の本はぜんぶ読んできた。これまでは食物や自然をテーマにしてきた著者がなぜ「幻覚剤」をテーマにしたのか疑問だったけど、読み進めていくうちに納得。幻覚剤が人間に与える影響とその歴史を丁寧に紐解き、自身の体験も紹介する姿勢は、これまでの本と変わりがない面白さと誠実さだと感じました。それでも時々は「大丈夫かなポーラン」と思ってしまったのだけど、それだけ内的世界で感じることの言語化と共感には難しいものがあるのかもしれない。面白かったです。2020/08/22
zoe
21
How to Change Your Mind (2018). オリバー・サックス先生のミュージコフィリアから再び始まった本読みの旅も終盤を迎えました。何故、我々がものを考え、体を動かすことができるのか、それは化学物質が体の中を駆け巡っているから。幻覚を生み出す化学物質は、安全性に配慮し、厳密に評価することで、医薬品とすることができるかもしれないと多くの人が考えていることが分かる。2020/11/22