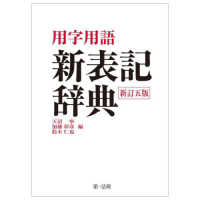内容説明
だれもが悩む問題「死後はどうなる?」を宗教・哲学、AIについての議論を横断しながら対話形式で探究する。
目次
第1部 日本人の死生観のさまざまな源泉(生まれ変わりと不死の生―輪廻と往生;山の上から子孫を見守る―盆という習慣;子孫の命の中に生き続ける―儒教における「生命の連続体」としての家;一度きりの人生―キリスト教における天国と地獄;日本の文化は雑食性か)
第2部 心身問題を考える(魂の存在を証明できるか―デカルトの試み;世界が物質だけなら心はどこにあるのか―自然科学と心のゆくえ;死ぬのは私だ―私とは誰か;関係としての心―死んで自然に還る)
著者等紹介
伊佐敷隆弘[イサシキタカヒロ]
1956年、鹿児島市生まれ。1994年、東京大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士課程修了。ヴィトゲンシュタイン研究(「言語と価値―ヴィトゲンシュタイン哲学の前期後期の連続性と不連続性」)で博士号取得。宮崎大学教育学部教授を経て、2014年から日本大学経済学部教授。専攻は哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
112
人は死んだらどうなるのか?誰もが抱くこの疑問には当然誰も正解を得ることは出来ない。現在まで宗教や哲学、神話において考えられてきた死生観を6つのパターンとして紹介する。1他の人間や動物に生まれ変わる2別の世界で永遠に生き続ける3すぐそばで子孫を見守る4子孫の命の中に生き続ける5自然の中に還る6完全に消滅する。これが1人の人間の中で層状に混ざっているという。先生と生徒の対話を通して専門用語を使わず丁寧に議論を積み上げ、生徒の言う心は関係から生まれるという考えは新しい。結局どの理論も確信は出来ないのだけれど。2023/01/19
trazom
34
死後の姿として、①他の人間や動物に生まれ変わる、②別の世界で永遠に生き続ける、③すぐそばで子孫を見守る、④子孫の命の中に生き続ける、⑤自然の中に還る、⑥完全に消滅する、の6つの仮説を提示しているところまでは面白いが、その後、「宗教的なアプローチ」と「哲学的なアプローチ」が噛み合うことなく併存し、死生観に関する議論が深まってゆかない。更に、死の主体である「私」の定義が重要なことは理解するが、心身問題に余りにも多くの紙幅を割きすぎ、「死んだらどうなるのか?」というテーマからどんどん離れていったことが残念だ。2019/11/26
テツ
20
コロナ禍で自身や身の周りの人間に突然死が近づいてきたような気がして慌てふためき精神にダメージを負っている方々をちょくちょく目にするけれど、そもそも人間はみないつ死ぬのか誰にも解らない残酷極まりない状況に放り込まれた存在だということ。そこを直視することなく生きてきた今までの人生とサヨナラして、出来たら常日頃から死について考えた方が良いのではないかなと思います。死とは何なのか古来から様々な賢人たちが知恵を絞り考え抜いてきた。死について思考を重ねることは死について覚悟することに通じる。2020/10/20
GELC
14
死についての代表的な議論を、専門用語を使わずに、分かりやすい形で示してくれた一冊。哲学を専門的に学んだ人以外は、大いに学ぶところがあると感じる。結論として、死後の世界はあるのか…とか、我々の心はどこにあるのか…などのよくある疑問については答えは明らかにならない。しかし、人格のコピーによる主観の枝分かれや、各人の心の上に上位システムを想定する話は、非常に興味深く読むことができた。デカルトさん間違ってるわー、というのも地味に驚いた(笑)2024/12/08
Te Quitor
7
とても静かなカフェにて読了。普段なら絶対読まない本ですが、この本と「目があった」から読んでみました。ほぼ無音の空間で本を読むことは、普段なかなか味わえないので、かなり新鮮ですね。心穏やかに読み進めておりました。対談形式なので堅苦しい内容ではなかったかな。ちなみに自分の死生観は「死後なんて考えたところで分かりゃしないのだから、勝手に楽しみにしとけば良いじゃん」です。色々な価値観があり、それを知ることが出来るのは楽しいですね2020/12/06
-

- 電子書籍
- 社内に価値あるタレントマーケットプレイ…
-
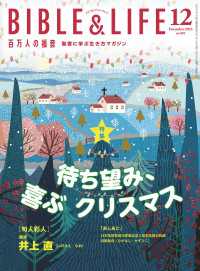
- 電子書籍
- 百万人の福音 2023年 12月号