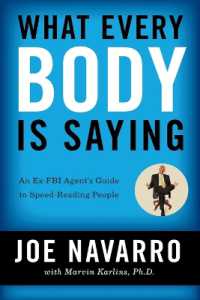内容説明
手紙、夢、仕事、幸福、魂、旅―。見えないものの中から大切な光を汲み取る、静かな励ましに満ちたエッセイ集。
目次
人生の報酬
文字の深秘
手紙の効用
光の場所
内なる医者
たましいの水
塵埃の彼方
見えない導師
島への便り
肌にふれる〔ほか〕
著者等紹介
若松英輔[ワカマツエイスケ]
批評家・随筆家。1968年生まれ、慶應義塾大学文学部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて三田文学新人賞、2016年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』にて西脇順三郎学術賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
113
さまざまな著書から引用された言葉について感じたことなどをわかりやすく書かれています。この著者の若松さんの考えがかなり織り込まれているという気がしました。このような本を読むと、自分も今までに読んで感銘を受けた本などから言葉などを書き出して感想をちょっと書いてきたい気がします。2018/07/15
モリー
50
私は、ふだん、言葉を雑に扱ってはいないだろうか。あるいは、言葉に対する感覚が鈍ってはいないだろうか。例えば、“かなし”という一語に当てられる漢字には、悲、哀、愛、美があると本書にある。しかし、私は、“かなし”“を、悲”か“哀”としてしか受け止めていなかったように思う。これを知ったとき、目に見えない光が七色の虹となって眼前に現れたような感覚にとらえられた。また、深く息を吐かなければ深く息が吸えない、の例え話が心に深く刻まれた。読書のことだ。書くことは息を吐くことで読むことは息を吸うこと。深さが大事なのだ。2025/09/28
井月 奎(いづき けい)
43
言葉の可能性や、その力と作用をよくよく教えてくれる本です。漢字の語源から、一連の詩から、一つの物語から人の本質や心を見だすことを教えてくれて、それらの言葉、文章が自らの中に吸収されて後、現れる自らの言葉こそが読むことの意義、意味であるといいます。自分の基盤は自分である、ということです。その基盤を強固に知るために言葉、文、文章、本が極めて有用であることを静かではあるのですけれども、高い熱量で書き出しています。エッセイなのですが、長めの詩と読むこともできます。旅の本質、やさしさの意味も垣間見せてくれます。2019/12/20
あっこっこ
33
あぁ、わかるなぁ。読み終えたとき、そう呟いていた。一日に独りの時間が恐らく人より必要で、だけれど人嫌いだというわけでなくむしろ好きで。独りが好きと公言すると、大抵は揶揄されて終わってしまうことが多いけれど、私はできるだけ独りの時間は大事にしていたい。「読書」をすると、自然と筆を握ってなにかを書きなぐっている経験もしばしば。でないと、今考えていたコトバを落としそうで。「めぐり逢いのとき」の、ある人とは石牟礼道子さんのことでしょうか。私の人生にもこのような出逢いがあると思うと楽しみで仕方ありません。2019/09/20
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
30
【1回目】Eテレ「100分de名著」(『苦海浄土』の回)を見、たちまち虜となってしまった著者の近作。どのような生き方をしていたら、こんなにも「生」の深淵を覗き込み、「コトバ」や「文字」が「いのち」に根ざしているのかについての思索を深めることができるのだろうか。おこがましいことだが、ぼくの考えが若松さんのそれと共振している部分がいくつかあった。他の読者も、きっとそうした感慨を覚えているに違いないと思う。現在、河合隼雄氏についての連載をされているが、単行本化が待ち遠しい。2017/12/26
-

- 電子書籍
- ほねほねザウルス27-かみの山のソード…