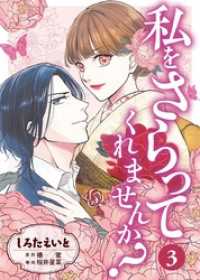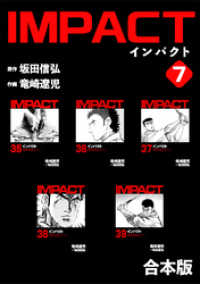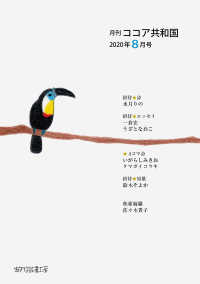内容説明
死者13人、重軽傷者24人、犯人2人は自殺。事件の一報を知ったとき、母が心の中で神に願ったのは、息子の死だった。
目次
第1部 不似合いな事件(「コロンバイン高校で銃乱射事件が発生しています」;砕け散ったガラス;別人の人生;安らかに眠る場所;暗い予感;頼れる子ども時代;加害者の母から被害者の母へ;深い悲しみの現場;残された狭い居場所で;現実逃避の予期せぬ終焉)
第2部 息子への理解(深い絶望;破滅にいたる共依存;自殺への憧憬―高校三年生;暴力への衝動―高校四年生;私の贖罪;批判の渦中で;「どのように?」という問い;隠れた折り目の意味)
著者等紹介
クレボルド,スー[クレボルド,スー] [Klebold,Sue]
コロンバイン高校銃乱射事件を起こしたディラン・クレボルドの母。事件直後から、家族の生活を細部まで振り返り、原因を追究してきた。その過程で、精神衛生と暴力の関連性についての理解を深めながら、現在は自殺を防止する活動に奔走している
仁木めぐみ[ニキメグミ]
翻訳家。東京都出身。跡見学園女子大学英文学科卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くぅ
38
川崎の事件を受けて"殺人を犯しその後に自殺する"という行為をもう少し考える上で知った一冊。米国で1999年に起きた銃乱射事件で犯人となりその後自殺した子供の母親が原因追求の末に記したもの。本編後の解説でG.K.チェスタートンの"他人を殺す男は一人を殺す。自分を殺す男はすべての人間を殺す。本人にとっては、世界を消しているのだ"という言葉が紹介されておりなんとなくすんなりと理解出来た。自殺欲求を未然に解決出来れば起きない事件だが、それを抱えた本人は家族に対しても隠すことがある。→2019/06/04
たまきら
33
コロンバインは上九一色村と同じぐらい起きた事件と同一化されている固有名詞だと思う。銃乱射を起こした2人の高校生のうち一人の親によるこの手記からは親たちが決して味わいたくない苦しみが伝わってくる。特に後半からはこの事件から学び取ろうと努力する活動に胸を打たれた。ただ気になることがある。銃規制への提言がないのだ。どんなにNRAが声高に弁護しても、アメリカの銃社会が産む大量殺人への誘惑は見過ごせない。この単純なことを書けない、あるいは書こうとしない姿勢もまたアメリカの闇だと思う。2019/02/26
ばんだねいっぺい
31
親だから子どものことを全部ってのは、無理だと思う。心意気としては、そうだとしても。それにしても、犯人を異常者扱いするだけじゃなくて、スクールカースト文化を変えよう運動も強くあっていいのではないか。やっぱり、脱マチズモだなと思いを強くした。2019/06/09
香菜子(かなこ・Kanako)
30
息子が殺人犯になった――コロンバイン高校銃乱射事件・加害生徒の母の告白。スー・クレボルド先生の著書。犯罪被害者や被害者家族からすれば、犯罪加害者や加害者家族に対して怨恨や怒りを覚えるのは自然なことなのかもしれないけれど、周囲からの冷たい視線や差別や偏見に苦しんでいるのは加害者家族も同じ。私は加害者家族に対する非難や嫌がらせは絶対にあってはならないと思います。2019/01/13
テツ
25
コロンバイン高校銃乱射事件の加害者生徒の母親による手記。自分の息子がある日突然大量の人間を殺害してそのまま自殺してしまったら一体何を思いどれだけの後悔を重ねて世間からの視線に対してどう向き合っていけばよいのだろうかと考えて気が滅入る。家庭環境をはじめとした周囲のコトやモノが全く影響しないとは言わないが、個人がやらかした事柄について家族に責任の一端を担わせるべきじゃないよな。自発的な苦悩は避けられないのかもしれないが、社会という隠れ蓑の中から無記名のままで責任を追求してはいけない。加害者の家族は被害者だ。2021/06/17


![サキヨミ![1話売り] story06-2 花とゆめコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1908839.jpg)