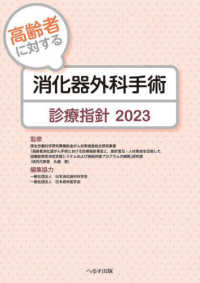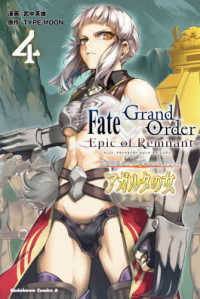出版社内容情報
現象学の新たな地平を開拓し、人間存在のふしぎに迫る、哲学者・木田元の高弟による渾身の哲学書。著者の身の回りの体験を通し、フッサールやメルロ=ポンティの現象学をわかりやすく解説しながら、人間の想像力の謎に迫る哲学入門。
内容説明
「人間とはなにか。そして、私はいったいなにものか」解けない謎にいどむのは、自分と他者と世界を肯定するため。幽体離脱や二日酔いなどの実体験を手がかりに、現象学の未知の可能性を切りひらく。心身問題と格闘し、独我論を超えて、人間のあり方の秘密に迫る思考の冒険。
目次
1 人間ってなんなのか
2 二日酔いから心身問題へ
3 現象が現象でなくなるとき
4 夢か現か幻か
5 身体の心と人格
6 不滅の問い
7 人間が人間でなくなるとき
著者等紹介
岡山敬二[オカヤマケイジ]
1970年北海道岩見沢市生まれ。北海道大学文学部卒。中央大学大学院文学研究科博士課程修了。哲学博士(中央大学)。中央大学文学部、中央大学理工学部、大妻女子大学等の非常勤講師を経て、日本大学法学部助教。専攻は現象学を中心とする現代哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yozora
3
デカルトの心身問題を紐解こうとしたフッサールの思索を追う。「現象学」での物事の知覚の方法など(感性的総合、キネステーゼ)が詳しく紹介されていてよかった。最後は、フッサールの現象学が他者論を乗り越えられないのでは、という話になり有耶無耶で終わるが、現象学の手触りは感じられた。2024/05/09
原玉幸子
1
現象学の哲学的考察は、自身の体験から言うと「本人の自我が目覚める時からの思考実験」であり、誰もが通る(と思われる)儀礼として必要でしょうが、超弦理論で温度、時間、空間すらも幻想ではとの領域に突入している現代では、2014年の著作ではやや時代錯誤かと。と言いつつも、超弦理論が証明されるのであれば哲学的考察に必ず帰ってくるはずにて、現象学の考察手法として知っておいても良いかも。ミーハーな私は、専門家として学術追求するわけではないので、変に原書を読むより斯かる解説書が望ましいと考えています。(●2014年・秋)2019/12/07
田中峰和
1
現象学や哲学に関心があり、とくに現象学に予備知識のある人にとってはお勧めの本。サルトルの「実存が本質に先立つ」と言う主張とか、ハイデッガーの「事実存在と本質存在」とか、フッサール以降の知識がないと、理解困難な内容だ。フッサールからサルトル、メルロ・ポンティ、エマニュエル・レヴィナス、ジャック・デリダらに継承された現象学について、基礎から学ぶ必要があると感じた。着想から5年以上の年月がかかった著者の執筆の経緯や、専任職に着くまでの苦労など、あとがきの読みやすさと、本文の難解さとのギャップが楽しめた。2014/10/03
ぴの
0
メルロ=ポンティを追っていたら辿り着きました。本書は「人間とは何か」という果てなき問いに対して、主にフッサールの現象学に依拠しながら、著者なりにその答えを模索するものです。結果的に明確な答えは得られないのですが、問うこと自体に意味があるという具合に締めくくられます。正直なところ、私はフッサールに関して何の知識もなかったので理解が追いつきませんでした。とはいえ、本書の出発点は人間の恐ろしさや底知れなさにあり、私の関心に近いこともあって何とか読了しました。何だか哲学たいう営みの原点に戻ったような気分です。2017/12/29
よっぴー
0
唯野教授読んで、わかりやすそうな現象学の本を読もうと思って買ったけど僕の頭ではよくわからない本だった…。2019/08/11
-

- 洋書
- The Goatman