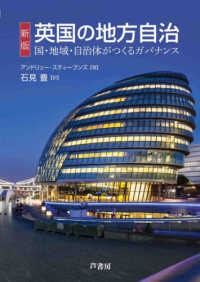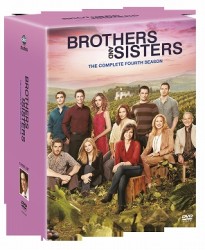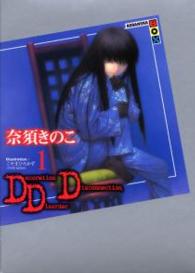出版社内容情報
産む・産まない・産めないを、国家や医療、他者が管理しようとするこの世界で、「わたしたち」は自身の経験を語る。日本における中絶の歴史を振り返り、当事者の声と、支援者や研究者、取材者などの立場で様々な中絶を見聞きした人たちの声を収録。
内容説明
産む・産まない・産めないを、国家や医療、他者が管理しようとするこの世界で「わたしたち」は自身の経験を語る。日本における中絶の歴史を振り返り、当事者の声と、支援者や研究者、取材者などの立場で様々な中絶を見聞きした人たちの声を収録。
目次
第1部 中絶をめぐる長いお話(妊娠したら産むしかない?―堕胎罪と優生保護法;中絶を禁止する動きと女たちの抵抗―表現と記録;わたしの身体、わたしが決める―リプロとSRHR)
第2部 わたしの経験(自由に産めないのなら、とコンドームを買った;目が覚めて、「この世に戻れた」と思った;手話通訳はなく、説明がわからない ほか)
第3部 様々な経験に接して(孤立出産;若年女性と沖縄での中絶;一〇代の妊娠葛藤 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
83
表題の「わたしたち」には、当事者だけでなく、男性、医療従事者、社会などすべての人々が含まれていることを読後感じた。中絶を経験した38人の体験談はもちろん異なるが、日本の中絶は費用が高く懲罰的な面があり、世界中で認められている中絶薬が認可されてもハードルが高く、必要のない同意書を求められることなど問題だらけであることを初めて知った。映画「あのこと」や「17歳の瞳に映る世界」でも、いつの時代も若い女性に負担がかかる。SRHRという概念「自分の身体は自分で決める」という考えが葛藤を少しでも和らげればいいと思う。2025/05/25
きみどり
16
戦中の産めよ増せよから一転、戦後は産児制限のため優生保護法(現・母体保護法)が作られ、70年代末に少子化の気配が漂い始めるや今度は中絶の制限へ(先人たちの反対運動に感謝)。その頃に「水子供養」なる宗教ビジネスが興ったというのは知らなかった。中絶への罪悪感を掻き立て、お金をむしる。ゲスの極みやな。それにしたってこの国には女性の身体の自己決定権という考えがいまだ根付いていないのかと暗澹たる気持ちになる。望まない妊娠には、無理解で時に暴力的な男性が必ず存在するのに、罰せられるのは女性。2025/07/14
すーぱーじゅげむ
14
編集意図としては、産む・産まないを決めるのは女性の権利である、というもの。そして、38の中絶経験談。夫がDVとか、経済的に豊かでないのにすでに5人子供がいるというのは中絶の権利は当然あるだろうと思いました。けど、キャリア的に今じゃないとかは、子育てが妻ばかりに負担がかかる現状、金銭的問題、孤立、とか子育てのインフラが整ってたらまた違うのかなと思いました。どちらにしろ掻派法は痛そう。そして男たちよ、あなたのせいでその子は手術しなきゃいけなくなったんですよ。2025/07/09
shikada
12
中絶の当事者による、一人ひとりのインタビュー集。中絶の相談に行ったらかかりつけ医に「少子化だし3人くらい生んだら?」って言われた、イギリスの中絶・避妊の体制が日本より進みすぎてた、手術直後の朦朧状態で水子供養の営業をされて「なんでいま??」って感じた、中絶後に罪悪感を感じていたときに、中絶したことがある女性が寄り添ってくれたなど…、1つ1つのエピソードに重みがある。堕胎罪の詳細(妊娠させた男性は罪に問われない)や、中絶の法的な取り扱いがどう改善されてきたか(どういう問題が残ってるか)もわかる。2025/08/27
CBF
3
(★★★☆☆) 産む・産まない・産めないを、国家や医療、他者が管理しようとするこの世界で、自身の経験を語る。日本における中絶の歴史を振り返り、当事者の声と、様々な中絶を見聞きした人たちの声を収録ー。 読んでいるだけでお腹が痛くなるような壮絶な体験も綴られていた。本来は男性含め、妊娠や中絶に一生無関係な人ってほぼ居ないはずだけど、知られていないことが沢山。 『...堕胎罪には登場しない(罰せられない)妊娠の相手男性が、中絶するときには最終決定権を握るという摩訶不思議な仕組みが、八〇年以上、今も続いている。』2025/07/10
-

- 洋書電子書籍
- Advances in Cyber S…