内容説明
スウェーデン流コーヒーブレイクFIKAとともに、日本の学校の未来を語り合おう。あらゆる子どもを包摂する、みんなのための学校へ。
目次
第1章 児童中心主義―義務教育を概観する
第2章 自由・柔軟
第3章 ゆとり・文化
第4章 休み時間/放課後、学習環境
第5章 マジョリティ、マイノリティ―「同質性」と「異質性」
第6章 権利と参加、そして尊重
第7章 民主主義・平等
第8章 葛藤、そして未来
第9章 点描 コロナ禍とポストコロナの学校
著者等紹介
戸野塚厚子[トノズカアツコ]
宮城学院女子大学教育学部教授、同大学院健康栄養学研究科教授。博士(教育学、筑波大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
練りようかん
14
早くから移民を受け入れてきた国家的背景や共働きが前提の社会事情から、どのような場であるべきかが考え抜かれている印象を受けた。まず非常にリラックスした職員室の写真に固定観念が崩れ、教科書が貸与制とあり一瞬意味がわからず、そこから日本の課題解決の取っ掛かりが見えてくるのが興味深い。休み時間に「みんなで」とか「輪に入ろう」と大人が働きかけない在り方の容認が素晴らしい。二項対立にしない、進学受験がない等具体的な事柄から“駆り立てない”がキーワードに思えて、日本は教師・子ども・保護者に対し真逆をいってると感じた。2025/06/30
yurari
2
スウェーデンの社会思想家、教育学者、女性運動家であったエレン・ケイは、子供に積極的教育をするのではなく、大人は模範として存在することを提唱/ラーロプラン(スウェーデン版学習指導要領)における身体活動「特に低学年では、遊びが知識の習得をするうえで極めて重要であること、学校は全ての子供に身体活動を提供するよう努めなければならない」/螺旋階段輪を上るように、同じことをレベルアップさせながら繰り返し取り上げる→スパイラル教育2024/09/06
-

- 和書
- アメリカ都市教育史


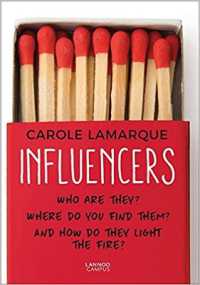
![ディープ・パープル・第3期ベスト[ワイド版] バンド・スコア](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44013/4401366131.jpg)




