目次
序章 ソーシャルワークの新しい可能性
第1章 批判はどこまで到達しているのか―本書において明らかにしたいこと
第2章 「実践の科学化」の方法論―「当事者」として何を引き受けることができるのかという問いを中心に
第3章 「間柄的関係」の実践―「地域包括支援センター」の実践を例に
第4章 「共感」から生まれる関係性のあり方―「あおやま広場」のコミュニティ・エンパワメント・スキームを例に
第5章 「対話」による公共空間の構築―中津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定プロセスを例に
第6章 見出された「意味」の構造とは―「間柄的関係、共感、対話」という3つのキーワードから同定されるもの
終章 ソーシャルワークが目指す社会のあり方とは
著者等紹介
衣笠一茂[キヌガサカズシゲ]
臨床ソーシャルワーク研究所(CSWRI)・Kinugasa&Associates代表。同志社大学大学院文学研究科社会福祉学専攻博士課程後期中退。博士(論文博士・社会福祉学・同志社大学)。社会福祉法人あしや聖徳園ソーシャルワーカー、九州看護福祉大学助教授、大分大学教育福祉科学部教授、同福祉健康科学部長等を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
1
ソーシャルワークの新しい可能性 批判はどこまで到達しているのか 「実践の科学化」の方法論 「間柄的関係」の実践―「地域包括支援センター」の実践を例に 「共感」から生まれる関係性のあり方―「あおやま広場」のコミュニティ・エンパワメント・スキームを例に 「対話」による公共空間の構築―中津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定プロセスを例に 見出された「意味」の構造とは―「間柄的関係,共感,対話」という3つのキーワードから同定されるもの ソーシャルワークが目指す社会のあり方とは2021/09/06
-
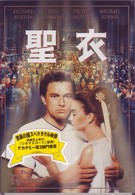
- DVD
- 聖衣





