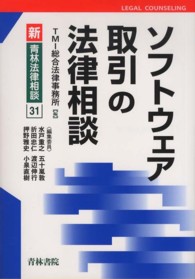内容説明
レジリエンスに関心のある研究者、臨床家、教育者、学生など、幅広い読者のための必読書。理論、実践、研究結果の確かなる基礎を提供する。
目次
第1部 導入と概説(序論;レジリエンスのモデル)
第2部 個人を対象としたレジリエンス研究(コミュニティサンプルにおけるレジリエンス―プロジェクト・コンピテンスの縦断研究;不利益と経済危機を乗り越えるホームレスの子どもたち;集団的トラウマと極度の逆境―戦争、テロ、災害におけるレジリエンス)
第3部 レジリエンスにおける適応システム(ショートリストおよびレジリエンスと関連する保護システム;レジリエンスの神経生物学;家族という文脈におけるレジリエンス;学校という文脈におけるレジリエンス;文化という文脈におけるレジリエンス)
第4部 前進を目指して―実践と将来の研究のために意味を読み解く(実践のためのレジリエンスの枠組み;結論とこれからの研究)
著者等紹介
マステン,アン[マステン,アン] [Masten,Ann]
ミネソタ大学理事会メンバー教授。同大学、児童発達研究所のアーヴィング・ハリス記念教授。非営利団体The Society for the Research in Child Developmentの元会長、アメリカ心理学会(APA)のフェローであり元部会長(第7部会:発達心理学)、Psychological Science協会のフェローを歴任。現在、Medicine and the National Academies研究所の、子ども、若者、家族に関する評議会の委員。人間の発達におけるレジリエンス研究のエキスパートとして国際的な知名度を持つ。学会誌投稿論文数、著作数は150を超える。2014年には、科学研究と社会に貢献した発達心理学研究の長年の功績に対して、アメリカ心理学会から、ブロンフェンブレンナー賞が贈られた
上山眞知子[カミヤママチコ]
東北大学大学院教育学研究科博士課程後期3年の課程単位取得。公認心理師・臨床心理士・宮城厚生協会坂総合病院常勤臨床心理士、山形大学地域教育文化学部教授を経て、東北大学災害科学国際研究所客員教授(社会対応研究部門歴史資料保存研究分野)。専門は、臨床心理学、発達心理学、神経心理学
モリス,J.F.[モリス,J.F.] [Morris,J.F.]
東北大学文学研究科文学博士(日本史)。2020年3月末まで宮城学院女子大学学芸学部日本文学科教授。2020年4月から、東北大学災害科学国際研究所客員特任教授、宮城学院女子大学名誉教授。宮城歴史資料保存ネットワーク理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。