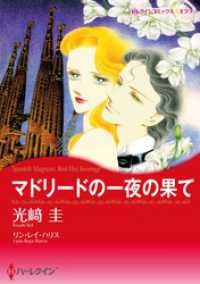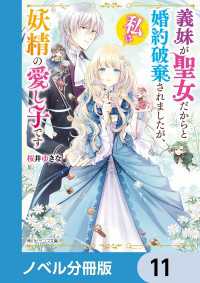内容説明
「データが示す子どもたちの実態は切実であった」本著の目的は、単なる貧困の実態を表すのではなく、調査の意義や方法といった設計部分から地方自治体と研究者の協働、さらには施策の策定・実施・改善まで、データに基づく議論の展開を提示することにある。つまり、調査が実態と施策の架け橋となることを期待している。
目次
第1部 貧困概念と貧困調査(子どもの生活実態調査の意義;貧困概念とはく奪指標;3つのキャピタルの関連)
第2部 貧困の諸相―生活上のニーズに着目して(所得格差と貧困;生活と貧困;健康・つながりと貧困;就学前の子どもと貧困)
政策提言
著者等紹介
山野則子[ヤマノノリコ]
大阪府立大学人間社会システム科学研究科/地域保健学域教育福祉学類教授、スクールソーシャルワーク評価支援研究所所長。博士(人間福祉)。日本子ども家庭福祉学会副会長、日本社会福祉学会理事、厚生労働省社会保障審議会児童部会委員、内閣府子どもの貧困対策検討会議構成員(2014年)、子供の貧困対策に関する有識者会議構成員(2015年~)、文部科学省第9期中央教育審議会本委員などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
23
子どもの貧困と「子ども」を強調して貧困がとらえられたことはとても大切なことである。子ども期をどのように保障していくのか社会には鋭く問われている。本著は、著者たちがかかわった大阪での調査をもとに、経済的な実態や剥奪指数などを使いながら、実態をみたものである。また、最後には簡単な政策提言もされていた。2020/03/19
katoyann
16
大阪の子どもの生活実態に関する調査研究報告書。大阪の子どもの就学支援金受給率や住宅事情等の実態が分かる。 貧困層の家庭に育つ子どもは自己肯定感と自己効力感が低いという。例えば、親に余裕がなく、話を聞いてもらえないという状況下で育つと自己肯定感が下がるという。また、絵本を読み聞かせてもらう経験の有無が子どもの将来の学力や経済力を左右するという。 なお、「子ども食堂」や「学習支援」等の施策に対しては、経済支援を抜きにしたネットワーク支援であるとしてその有効性に懐疑的な見解を述べている。勉強になった。2023/05/16
takao
2
ふむ2022/11/01
バリバリブーン
0
子供の貧困と生活環境の関連について、データ分析して分類したものを詳細に紹介している。結果をざっくりとまとめると親の経済状況と子供の貧困は緩やかに関連しているというもので、特に意外な結果は示されていない。巻末の政策提言もまた然りで保障に関するものが主。もう少し違った視点からのアプローチを期待しただけにちょっと残念。いっそAI分析したらどうかと思った。時間をかけて読んだ割に得られるものは少ない印象でした。2020/02/22