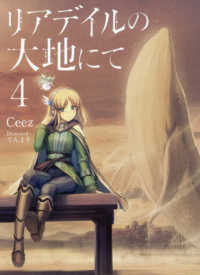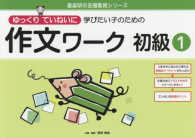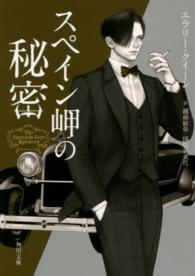内容説明
子どもの貧困の再発見から10年。この10年間の政策・実践・研究を批判的に検討し、“子どもの貧困を議論する枠組み”を提供する。新・スタンダードの誕生!
目次
子どもの世界の中心としての「遊び」
第1部 遊びと経験の意味(貧困と子どもの経験―子どもの視点から考える;生きるためにあそぶ―あそびが見えてくる社会にむけて;遊びと遊び心の剥奪―障害と貧困の重なるところで)
第2部 子どもの世界を守る実践(遊びと育ちを支える保育実践;みんなが気持ちいい学童保育;やはり、授業がプレイフルであること;地域子育て支援拠点事業の多様なあり方―夜の多世代型子育てサロンはじめました;放課後の地域の居場所から考える)
第3部 育ちの基盤を支える(子どもの健康と貧困;子育ての分断と連続;貧困対策における保育の再定位に向けて―家族のライフコース、労働とレジリエンス)
「子どもの世界」を社会全体で守るために―家族主義をどう乗り越えるか
著者等紹介
松本伊智朗[マツモトイチロウ]
北海道大学大学院教育学研究院教授。専門は教育福祉論、社会福祉論。雑誌『貧困研究』(貧困研究会、明石書店)編集長
小西祐馬[コニシユウマ]
長崎大学教育学部准教授。専門は児童福祉、貧困研究
川田学[カワタマナブ]
北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター准教授。専門は発達心理学、保育・幼児教育(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりん
26
子どもの貧困をテーマにしたシリーズもの。テキストのような感じ。子どもの貧困は親の障害や貧困が引き起こしているものもあり、周りが気づいて助けてあげればよいが、見過ごされているものも多く問題解決は簡単ではない。2019/09/19
ゆう。
26
子どもの貧困は、遊びの不平等をもたらす。それは、子どもの今を奪い、発達を奪うことだと思った。遊びから貧困をとらえようとする試みはとても野心的だ。だからこそ重要だと思った。そして豊かな遊び環境を整えるためには、豊かな大人の世界が必要だと思った。2019/09/11
りょうみや
21
子どもの貧困シリーズ全5巻の中で本書がタイトルで惹かれてまず読んでみた。子どもの貧困を経済面・教育面から一歩超えて遊びと経験の面から多角的に眺める他にはなかなか見ない珍しい切り口。貧困の面だけでなく、そもそも遊びとは何か、遊びは人生・人の発達においてどのような役目を果たすのかについて色々と考えさせられる。2019/06/29
lovehunteru
2
タイトルに惹かれて。 「特別旅行に行かずとも、一緒に買い物に行ったり、散歩をしたりするだけで子どもの世界は広がる」というのを読んで、確かに働き詰めだったり、心に余裕がなかったら散歩さえも出来ないだろうなぁと思った。 引用や出典が多く読みにくかったけれど、興味深かった。2019/08/03
いなちゅか
0
貧困を考えると家庭環境や労働、経済などに目が向きごちになるが、本書は遊びの観点から考察している。遊べる場所は増えている一方で多くの成長要素が市場化している傾向は看過できない。子どもの自主性を育みつつ、大人の介入を最低限にする上手な付き合い方を模索する必要がある。 2021/12/09