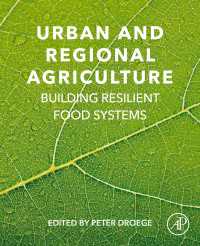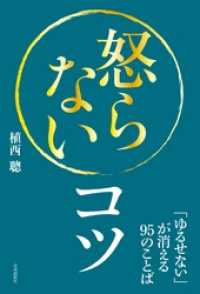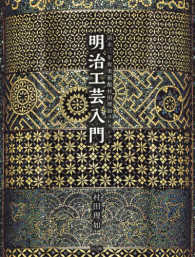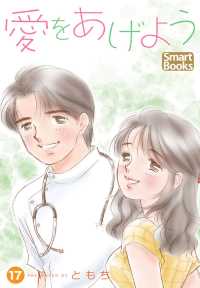出版社内容情報
本書は、ベトナムにおける社会復帰が困難となったハンセン病患者を対象に、彼らの社会復帰を困難とさせている要因および具体的な支援のあり方について明らかにしながら、社会復帰支援理論の再構築を目的とする。10年にわたる現地での実態調査に基づく労作。
はじめに
本研究および各章の目的
ハンセン病に関する呼称について――患者、元患者、回復者など
ベトナム社会主義共和国の概要
地名・人名等の表記について
第1章 問題の背景
第1節 ハンセン病とはどのような病気か
病理学的側面
第2節 ハンセン病の治療方法
第3節 世界のハンセン病の状況
1970年代におけるハンセン病の流行状況
1980年代におけるハンセン病の流行状況と対策――リハビリテーション概念の登場
1990年代におけるハンセン病の流行状況――「ハンセン病患者」への関心
ハンセン病制圧に向けての取り組み
第4節 ハンセン病によるスティグマの問題
第2章 ベトナムのハンセン病患者をめぐる状況
第1節 はじめに
第2節 第二次世界大戦前後の治療手段と患者数の実勢
第3節 民間慈善団体の活動
第4節 宗教関係者による患者の収容保護
ハンセン病村の開設
ベンサン病院の開設
受け入れ患者数の増加
第5節 ベトナム戦争の終結と新体制への移行
第6節 ベトナム戦争終結後のハンセン病患者――1970年代のタンビン村にみる患者の窮状
第7節 ベトナムにおけるハンセン病対策
ベトナムにおけるMDTの導入と登録有病率の推移
ハンセン病対策を担う機関とその役割
新規患者の発見と治療
第8節 問題の所在
今日のベトナムにおけるハンセン病のイメージ
ベトナム社会におけるハンセン病患者の存在
ハンセン病問題に対する視点
ダナンのハンセン病村移転問題
移転先住民の反対
ハンセン病(元)患者が抱える問題
第3章 ハンセン病(元)患者の実態調査
第1節 問題の背景と調査の目的
第2節 ベトナムのハンセン病についての先行研究
WHOの報告資料およびBangらによる論文
患者の身体障害発生状況についての研究
身体障害発生状況についての調査
先行研究の限界
先行研究の総括
第3節 調査の方法
パイロットスタディの実施
調査対象者への倫理的配慮
調査項目の設定について
調査エリアについて
調査対象となった機関とハンセン病村について
第4節 結果
調査結果の概要
平均年齢
出身地域
民族
宗教
きょうだい数と婚姻状況
学歴
生活の場所
発症した年齢
ハンセン病専門治療機関で治療を受けるきっかけ
身体障害程度と治療履歴
社会経済状況
第4章 ハンセン病(元)患者のライフヒストリー
第1節 本章の目的
第2節 研究の方法と調査における制約
調査の方法
データ化における制約
ライフヒストリーデータの表記について
第3節 結果
主なライフヒストリーのパターン
長期間にわたる入退院
誤診・発見が遅れたケース
家族関係の疎遠化
ハンセン病による離婚・婚約破棄
患者同士の結婚
自分から家族と距離を置くケース
家族から支援を受けていたケース
物乞いとなったケース
ハンセン病による差別
孤児だったケース
社会復帰ができなかったケース
従軍・戦争経験者
戦争の影響を受けた人々
患者を支援する側に回った人々
その他のライフヒストリー
第4節 (元)患者のライフヒストリーにみられる特徴
戦争に関わるライフヒストリー
第5章 ハンセン病(元)患者を親に持つ子どもたちの被差別経験と葛藤
第1節 本章における関心と目的
第2節 問題の背景
第3節 ハンセン病(元)患者の親を持つ子どもたちに焦点を当てた先行研究
第4節 研究方法
調査対象者と場所
調査方法および質問項目
倫理的配慮
第5節 結果
調査対象者の性別および年齢層別割合
同居家族における(元)患者
婚姻の状況
子どもたちの教育と学歴
子どもたちの現況と職業
自己の情報開示について
被差別経験の有無とその内容
周囲の人間の理解
子どもたちの恋愛と結婚
被差別経験の有無と自己の情報開示
将来の生活の場所について
被差別経験の有無と将来の生活の場所について
被差別経験と自己の情報開示
10歳代グループにおける定住/転出希望の割合
他者との関係における困難性
子どもたちに対する周囲の理解
ハンセン病村に住むということ
10歳代グループの特徴
第6章 ハンセン病(元)患者のQOL
第1節 本章の目的
第2節 ハンセン病患者のQOLについての先行研究
第3節 方法
第4節 倫理的配慮
第5節 結果
対象者の基本的属性
患者群の身体障害程度
患者群と一般群の下位尺度スコア比較
身体機能
日常役割機能(身体)
身体の痛み
全体的健康感
活力
社会生活機能
日常役割機能(精神)
心の健康
全体平均の比較
病院間の比較結果
自立支援プログラムへの参加状況
自由回答として挙げられたもの
一般群のQOL結果について
第7章 ハンセン病(元)患者に対する自立支援
第1節 本章の目的
第2節 (元)患者の社会経済的状況と自立支援の必要性
第3節 自立支援の諸概念――IBRおよびCBRの概念
障害者支援のアプローチ――IBR、アウトリーチ活動、CBR
CBR登場の背景
CBRの定義と目的
CBRの実践方法
現状におけるCBRの問題点
CBRの現状を踏まえた課題
第4節 ハンセン病(元)患者に対する自立支援をめぐる議論
Nichollsによる社会経済的リハビリテーション(SER)のガイドライン
SERの目的と原則
全体的原則
参加型原則
継続性
社会的統合
性別に対する配慮
固有のニーズへの配慮
第5節 SERの具体的な実践
具体的な実践段階
固有のニーズへの対応
職業訓練の提供
ローンの提供
SERにおけるニーズ評価
SERにおけるマンパワーと資金
ニーズの多様性と支援のあり方
NichollsのSER概念の総括
「社会復帰を望まない」というニーズに対して
第6節 その他のSERの議論
Withingtonらのバングラデシュにおける研究
DevadasによるSERの議論
先行研究におけるSER概念の志向性
第7節 ハンセン病(元)患者への自立支援に関する先行研究
ミャンマーのハンセン病対策におけるリハビリテーション
ミャンマーにおける職業訓練のニーズアセスメント
職業訓練に対するニーズ
スティグマの感覚
職業訓練のニーズアセスメント
第8節 ベトナムにおける自立支援の事例
病院Bにおける自立支援プログラムの概要
第9節 自立支援プログラム参加者によるニーズアセスメント調査
目的
方法
第10節 結果
第8章 ハンセン病(元)患者にとって社会復帰とは何か
第1節 本章の目的
第2節 身体障害および後遺症の問題
MDT導入以前のグループの問題
G2グループにおける少数民族出身者
身体障害・後遺症とスティグマの問題
第3節 (元)患者のライフヒストリーにみられる特徴
患者を支援する側に回った人々
ライフヒストリーにみられる(元)患者同士の結婚
子どもたちにとっての被差別経験と必要な支援
第4節 偏見解消に向けた取り組みの必要性
第5節 ハンセン病(元)患者の処遇は改善されたのか
(元)患者のQOLの状況
若年患者群のQOL
高齢患者群のQOL
ハンセン病(元)患者の心の健康
高齢患者群のニーズとQOL
自立支援プログラムの有無と(元)患者のQOL
中間集団の存在とQOL
現在のハンセン病(元)患者の処遇に対する考察
第6節 (元)患者のニーズに即した支援のあり方
IBRに基づいたSERの可能性
第7節 (元)患者が「社会復帰」すべき場所とは――日本とベトナムの比較
日本における社会復帰の事例
ベトナムと日本の比較
第8節 次世代のハンセン病対策における課題
現行のハンセン病対策の継続
社会経済的リハビリテーション(SER)の実施
逆統合による一般社会との融合
ハンセン病(元)患者を親に持つ子どもたちへの支援
ハンセン病に対する偏見解消の取り組み
第9節 本研究の限界と課題
おわりに
参考資料
英語文献
日本語文献
ベトナム語文献
その他文献(フランス語)
附録
附録1 インタビューガイド――ハンセン病(元)患者実態調査
附録2 インタビューガイド――ハンセン病村の子どもたちへのインタビュー(被差別経験)
附録3 インタビューガイド――ハンセン病(元)患者のQOL調査
附録4 インタビューガイド――自立支援プログラム参加者へのフォーカスグループインタビュー
渡辺 弘之[ワタナベ ヒロユキ]
著・文・その他
目次
第1章 問題の背景
第2章 ベトナムのハンセン病患者をめぐる状況
第3章 ハンセン病(元)患者の実態調査
第4章 ハンセン病(元)患者のライフヒストリー
第5章 ハンセン病(元)患者を親に持つ子どもたちの被差別経験と葛藤
第6章 ハンセン病(元)患者のQOL
第7章 ハンセン病(元)患者に対する自立支援
第8章 ハンセン病(元)患者にとって社会復帰とは何か
著者等紹介
渡辺弘之[ワタナベヒロユキ]
新潟県立看護大学看護学部准教授。1967年福島県郡山市生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科グローバル人間学専攻博士課程修了(人間科学博士)。1995‐97年、ホーチミン国家人文社会科学大学東洋学部(現・日本学部)等に勤務の傍ら、ベトナムのポリオ施設や孤児施設、ハンセン病施設のボランティアに参加。1997年にベトナムから帰国後、新潟県立看護短期大学教員(現・新潟県立看護大学)となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。