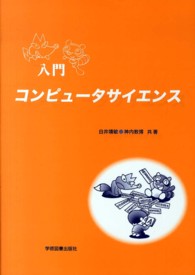出版社内容情報
超高齢社会・日本では、高齢者の孤独死などの社会的孤立が深刻化している。本書は、最新かつ多様な調査データに基づいた計量的アプローチにより、高齢者の社会的孤立に関する詳細な測定・評価を行い、今後の孤立予防・軽減策を展望するものである。
序章――本書のねらい
第?部 社会的孤立の定義・問題の所在
第1章 社会的孤立とは何か
社会的孤立が議論される背景
社会的孤立の定義と測定方法
高齢者の多くは孤立しているのか
高齢者の社会的孤立研究の課題
第2章 社会的孤立は「問題」といえるのか
離脱理論、社会情緒的選択理論と自発的な孤立
社会的孤立と関連する諸問題
社会的孤立問題の課題共有の必要性
第3章 どの程度の乏しさから社会的孤立と捉えるべきか
健康指標との関連に着目する意義
使用するデータ
交流頻度の多少による要介護認定等の発生率の相違
健康リスクが高まる人との交流頻度の乏しさ:多変量解析
交流頻度が週1回未満・月1回未満という基準
他者との交流が不明な人々
第?部 社会的孤立・孤立死の要因
第4章 独居高齢者は社会的に孤立しているのか
高齢期の独居と社会的孤立
使用するデータ
独居状態に至る主要な経緯:独居世帯の多様性
どのような独居が孤立と関連しやすいのか
長期孤立と短期孤立の相違
多様な「独居」に着目する意義
第5章 誰が孤立しやすいのか――社会的孤立の個人要因
システマティック・レビューの動向と課題
人口学的要因との関連
家族形成との関連
社会経済的地位との関連
身体的・精神的健康との関連
無回答・調査拒否と社会的孤立との関係
第6章 孤立死に至る人々はどういう人なのか――セルフ・ネグレクトとの関連
社会的孤立の帰結としての孤立死・孤独死
孤立死とセルフ・ネグレクト(自己放任)
使用するデータ
セルフ・ネグレクト事例の多様性
深刻度との関連:孤立死に至りやすい人々とは
孤立死事案をめぐる今後の課題
第?部 孤立予防・軽減にむけた実践と評価
第7章 見守られている人はどういう人か――独居高齢者への見守り活動のプロセス評価
住民主体の見守り活動のプログラム評価の課題
使用するデータ
見守り活動利用・非利用独居者の特性
住民による見守り活動の未充足ニーズ数
見守り活動のプロセス評価の意義
評価に耐えうるデータ整備の必要性
第8章 地域活動の推進は社会的孤立を軽減させるのか
高齢者の社会的孤立・孤独軽減にむけたプログラム
地域活動への参加による孤立軽減効果の可能性
見守り活動や生活支援による孤立軽減効果の可能性
高齢者の社会的孤立軽減にむけた介入研究の課題
第9章 高齢者が孤立しやすい地域はあるのか――社会的孤立の地域環境要因
ポピュレーション・アプローチの可能性
地域環境が個人の社会関係に及ぼす影響
高齢者が孤立しやすい地域はあるのか
地域単位のソーシャル・キャピタルと孤立化/非孤立化との関連
社会的孤立の軽減にむけた地域診断の可能性と課題
結論と展望
本研究で得られた主要な知見
学術的・政策的インプリケーション
本研究の限界と今後の課題
引用文献
あとがき
初出一覧
索引
斉藤 雅茂[サイトウ マサシゲ]
著・文・その他
目次
第1部 社会的孤立の定義・問題の所在(社会的孤立とは何か;社会的孤立は「問題」といえるのか;どの程度の乏しさから社会的孤立と捉えるべきか)
第2部 社会的孤立・孤立死の要因(独居高齢者は社会的に孤立しているのか;誰が孤立しやすいのか―社会的孤立の個人要因;孤立死に至る人々はどういう人なのか―セルフ・ネグレクトとの関連)
第3部 孤立予防・軽減にむけた実践と評価(見守られている人はどういう人か―独居高齢者への見守り活動のプロセス評価;地域活動の推進は社会的孤立を軽減させるのか;高齢者が孤立しやすい地域はあるのか―社会的孤立の地域環境要因)
著者等紹介
斉藤雅茂[サイトウマサシゲ]
日本福祉大学社会福祉学部准教授。1980年埼玉県生まれ。上智大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程修了。博士(社会福祉学)。日本学術振興会特別研究員、日本福祉大学地域ケア研究推進センター主任研究員を経て2012年より現職。平成26年度日本老年社会科学会論文賞、平成24年度日本老年社会科学会奨励賞、第22回日本疫学会学術総会ポスター賞など受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。