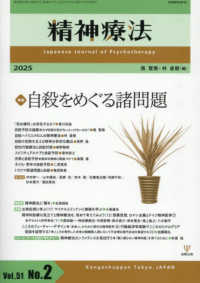目次
第1部 貧困とは何か(身近にある貧困をとらえる―貧困・低所得・生活困窮の理解;何が貧困で、何がふつうの暮らしなのか―貧困の概念と定義;社会は貧困をどう見ているか―保守化する貧困観;なぜ貧困が生じるのか、そして何をもたらすのか―スティグマ・不自由・不平等)
第2部 貧困対策としての社会保障(政府が貧者をたすける理由―公的扶助の思想・理念;公的扶助という名の貧者の管理―貧困対策と福祉国家の統治;公的扶助は「恥」なのか―社会保障のなかの公的扶助;生活をまるごと保護するとはどんなことか―生活保護の目的と原理;保護は「依存」を生み出すのか―生活保護の内容・方法・水準 ほか)
著者等紹介
金子充[カネコジュウ]
1971年東京都生まれ。2000年明治学院大学大学院社会学研究科社会学・社会福祉学専攻博士後期課程単位取得退学。東京都社会福祉協議会非常勤職員、日本社会事業大学・立教大学非常勤講師等を経て、2003年から立正大学社会福祉学部専任講師、2007年から同准教授。専門は、社会福祉学(社会政策論、公的扶助論)。2006年から、住居喪失者や生活保護受給者の支援をおこなうNPO法人(独立型社会福祉士事務所)ほっとポット監事として運営にかかわる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
40
分断社会とは、個人と個人が切り離され、人々の連帯感や相互扶助が失われた社会のこと(19頁)。貧困をなくしていくうえで必要なのは、多くの人々が貧困の現実に気づくこと、社会的に放置してはならないと考えること(57頁)。 オスカー・ルイスの貧困「貧困の文化論」:こんにち、社会の幅広い層から支持されている。貧困の文化は下位文化であるとされ、劣った文化に支配されることは下層の人々の病理であり、個人的な問題であると理解されている(100-1頁)。2018/01/13
ゆう。
36
貧困とは何か、その概念と制度、将来的にあるべき姿を考察した内容で、とても重みのあるものでした。貧困対策のなかで生じてくるスティグマや自己責任の問題点を示しながら、社会的に解決するべきものとして貧困があり、日本の貧困対策は十分に機能しきれていないことも指摘されています。将来的展望としてベーシックインカムなどが提示されています。貧困は資本主義社会のなかで必然的に生じる社会問題としてとらえた場合、ベーシックインカムが社会福祉制度として機能するのかどうかは、慎重になるべきだと僕は思いました。2017/11/18
羊山羊
9
今収入が減っている人は本著を念力でも眼力でもいいから読むべき。自分が一体、どこの貧困ラインに位置しているか見極め、そこから脱却するために何が必要かが収まった1冊。本著のパターナリズム=上から目線への忌避はちょっとやりすぎと思うものの、逆説的に貧困と向き合う事の難しさを物語る。今の日本の公的扶助の捕捉率は20%なのだという。残りの80%は何らかの扶助が受けられるのに受けられていない、ということだ。そしてそれは自分もそうかもしれない。2021/04/08
スミレ雲
6
ざくっと読み。扶助と保険というしくみ。国家の責任としての生活保障制度。日本では、恥の意識が強くなる生活保護。スティグマ、レッテル貼りになる。世代で意識はかなり違うような気もするけど。2018/04/15
aoi
3
公的扶助論のテキストとして指定された。 貧困、生活保護制度、スティグマ、パターナリズム、保護依存、ケアとコントロール(管理)…色々な問題を知り、考えるきっかけを作ってくれた。 金子充(2017)「入門 貧困論」明石書店2022/05/31