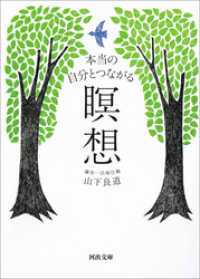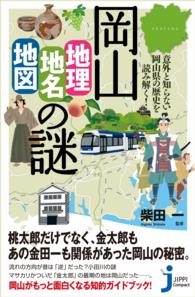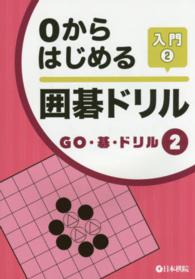目次
1 暮らしを映す人間模様
2 未来を照らす歴史
3 変容する社会と文化
4 多元化する政治
5 躍動する経済
6 絡み合う日比関係
著者等紹介
大野拓司[オオノタクシ]
ジャーナリスト、中央大学非常勤講師、沖縄大学地域研究所特別研究員。アジア・アフリカ・オセアニア地域研究
鈴木伸隆[スズキノブタカ]
筑波大学人文社会系准教授。文化人類学、フィリピン地域研究
日下渉[クサカワタル]
名古屋大学大学院国際開発研究科准教授。政治学、フィリピン研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。