目次
第1章 進化・発展・近代化をめぐる社会学
第2章 途上国の開発と援助論
第3章 援助行為の本質の捉え直し
第4章 押し寄せる力と押しとどめる力
第5章 都市・農村の貧困の把握
第6章 差別や社会的排除を生み出すマクロ‐ミクロな社会構造
第7章 人々の福祉向上のための開発実践
第8章 目にみえない資源の活用
著者等紹介
佐藤寛[サトウカン]
日本貿易振興機構アジア経済研究所上席主任調査研究員。専門:開発社会学、イエメン地域研究
浜本篤史[ハマモトアツシ]
名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授。専門:開発社会学、環境社会学、中国地域研究
佐野麻由子[サノマユコ]
福岡県立大学人間社会学部准教授。専門:開発社会学、ジェンダー論、ネパール地域研究
滝村卓司[タキムラタクジ]
名古屋市立大学大学院人間文化研究科研究員。専門:開発社会学、国際協力論、内発的発展論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
開発は、生活水準の向上等をめざして社会を意図的に近代化しようとする行為、ならびにそれを支援する行為(5頁)。コラム2 中国における発展社会学と転型社会学(40頁)。この転型社会学という呼称は初めて知った。計画経済→市場経済への転型ということらしい。社会主義市場経済というのはどうなるのかと今でも思う。李培林先生が権威のようである。今後、人口大国の開発社会学は大きな影響力を及ぼすのではなかろうか? 60冊の大半は馴染み深い内容であるが、2016/11/09
とある本棚
5
タイトルの通り開発社会学のブックガイド。本書を読むと、途上国の開発も日本の開発経験と地続きで考えるべきであることがよく分かる。開発学というと、イギリスやアメリカに留学して学位を取る人が多いが、日本の開発経験についてまとまった知識を持っておくことは必要であろう。その際本書は役に立つ。佐藤寛氏の「内発的発展の称揚には、一種の日本人のコンプレックスがある」という指摘には、苦笑しつつも頷ける。2022/08/15
menocchio
2
学校のカラーなのか、国際協力や開発支援に関心のある生徒によく会う。しかし、近代化や開発の正当性を自明視していることが多く、そこに違和感を感じていた。本書のいうように、開発とは「意図的に近代化を促進する行為」、すなわち一種の介入である。その際に重要なのは「善意は善行を保証しない」ということであり、我々は「介入」のあり方にもっと真剣に向き合うべきなのではないか。国際協力に関心のあるひとはぜひパラパラめくってみてほしい。2016/08/11
Megumi Uchino
1
広い意味での開発社会学での良書を60冊紹介してくれる本。先日おすすめした、エドガーシャインのHelpingもランクイン。特に最近私は開発・援助論、社会構造論が気になるようです!2015/12/23
-

- 電子書籍
- 月の子~私は嫦娥~【タテヨミ】第26話…
-
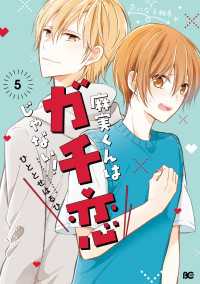
- 電子書籍
- 麻実くんはガチ恋じゃない! 5 Bs-…




