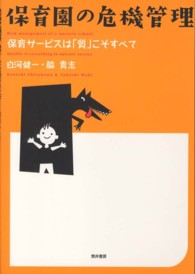目次
第1部 時間について―家族の時間がもっとあれば(「バイバイ」用の窓;管理される価値観と長い日々;頭の中の亡霊;家族の価値と逆転した世界)
第2部 役員室から工場まで―犠牲にされる子どもとの時間(職場で与えられるもの;母親という管理職;「私の友達はみんな仕事中毒」―短時間勤務のプロであること;「まだ結婚しています」―安全弁としての仕事;「見逃したドラマを全部見ていた」―時間文化の男性パイオニアたち;もし、ボスがノーと言ったら?;「大きくなったら良きシングルマザーになってほしい」;超拡大家族;超過勤務を好む人々)
第3部 示唆と代替案―新たな暮らしをイメージすること(第三のシフト;時間の板挟み状態を回避する;時間をつくる)
著者等紹介
ホックシールド,アーリー・ラッセル[ホックシールド,アーリーラッセル][Hochschild,Arlie Russell]
カリフォルニア大学バークレー校社会学部教授。専門は社会学。「感情労働」を概念化した『管理される心』(石川准・室伏亜希訳 世界思想社 1983=2000年)のほか、家族やケア労働者のグローバル化についての研究も知られている
坂口緑[サカグチミドリ]
明治学院大学社会学部准教授。専門は社会学、生涯学習論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。8歳男子の母親。都市におけるコミュニティ形成と生涯学習との関係について研究している
中野聡子[ナカノサトコ]
明治学院大学経済学部教授。専門は経済学史、経済思想史。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、博士(経済学)。12歳男子の母親。現代経済学の観点から経済学の歴史、思想史を研究している
両角道代[モロズミミチヨ]
明治学院大学法学部教授。専門は労働法。東京大学法学部卒業。8歳男子と3歳女子の母親。北欧、特にスウェーデンの労働法や社会政策に関心を持って研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ロピケ
さとう
ふみ
Mana
19May
-
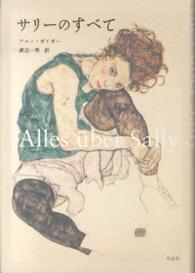
- 和書
- サリーのすべて