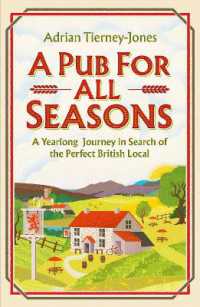目次
1 自然
2 生活と生業
3 環境と開発
4 歴史
5 経済
6 政治と外交
7 宗教と儀礼
8 言語と文学
9 文化
著者等紹介
菊池陽子[キクチヨウコ]
東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。専攻はラオス近現代史
鈴木玲子[スズキレイコ]
東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。専攻はラオス語学
阿部健一[アベケンイチ]
人間文化研究機構総合地球環境学研究所教授。専攻は環境人類学・相関地域研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
68
国連によると最貧国になるが、実際には自然も食生活も豊かで、消費社会になっていないだけなのではないか。このシリーズではガイドブックや観光旅行では表層しか見えない政治・歴史・文化・風習・経済などを掘り下げてくれる。本州と同じ位の面積に人口約700万人。日本と同様に国土の約69%が森林から成る。豊かな自然は生態系の宝庫でもある。今まで日本からの援助が多くされているが、戦略的ではない援助である。今後中国からの援助と中国人の増加も確実に増加する。中国からの援助と要求で貴重な自然が破壊されるのを防げないのがもどかしい2019/12/01
Akihiro Nishio
20
ラオスにて再読。改めて読み直すと、ラオス人、特にラオ族の生活様式、者の考え方、伝統について非常に丁寧に観察して書かれていることがわかる。このシリーズでも屈指のクオリティでしょう。実際に現地に来てみると、首都ビエンチャンでは、本書で書かれているような人びとの営みを垣間見ることができない。田舎にも足を伸ばした方が良さそうだ。2016/08/15
源次/びめいだー
1
2010年12月発行の本。ラオスに対する理解を深めることができました。2024/06/10
cybermiso
1
ラオスについて歴史から政治、暮らしまで広範囲にかかれている。民族の違いがためになった。一軒一台の機織り機や高床式の家、焼畑、首都の発展、山岳地方の精霊信仰など、現地でも再確認。 ・日本の森林率とラオスの森林率はほぼ同じ(69%)、東南アジアでは一番 人々は主に低地ラオ(タイ系、稲作、ランサン王国、上座仏教、9世紀ごろより)、山腹ラオ(先住民、クメール系、ワットプー遺跡、焼畑)、高地ラオ(チベット、ビルマ系、18〜19世紀より中国から移り住んだ、焼畑、精霊信仰、モン族、アカ族とここ)にわけられる 2019/05/08
セイタ
1
初めて、読んだエリアスタディーズ!ラオスには全く縁がなかったが、フィールドワークを行うことが決まったので、ラオスについての知識を深めるために図書館で借りてみた。10人くらいの学者がそれぞれの分野からラオスのことを分析していて、かなりためになった。個人的には虫明悦生先生の章を気に入っている。現地に深く入り込んでいるように感じるからだ。この本を読んで、ラオスが自身のフィールドである雲南とのかなり似ているという印象を受けた。ラオスには森で住んでいる人が多いのと、多様な民族がラオス化するという点である。2018/02/09