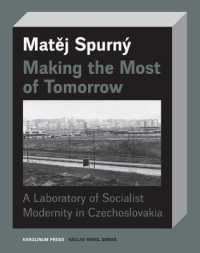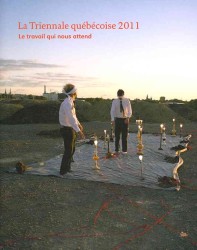出版社内容情報
NPO法制定から10年。多くのNPOは経済的な困難を抱えながらも、自立をもとめて模索を続けている。では、NPOはどうすれば真の社会変革の担い手となりうるのか? この10年を総括し、寄付、ボランティア、アドボカシーの3つの観点から提言する。
はじめに
第1章 NPOはいま、どこにいるのか
1 NPOの二つの役割と目的
2 NPOセクターの現状分析にみる窮状
2-1 収入規模からみたNPOセクター
2-2 多様化する活動分野
3 持続性が問われるNPOの経営
第2章 NPOは何が変質したのか
1 行政の下請け化とは何か
1-1 行政との距離感の問題
1-2 下請け化の特徴
1-3 下請け化はなぜ起こるのか
1-4 委託依存が引き起こす悪循環
2 社会的企業に傾斜する日本のNPO
2-1 二つの社会的企業論
2-2 社会的企業はなぜ注目されるのか
第3章 この一〇年をどう総括するのか
1 数の論理と質の評価
2 二つの側面からみたNPOセクターの評価
2-1 市民の生活を支える側面
2-2 市民性創造の側面
第4章 市民性創造がなぜもとめられるのか
1 日本の市民社会とは
2 時代が要請する新たな市民社会像
2-1 新たな市民社会に期待される三の役割
2-2 時代の変化と市民社会の再編
第5章 寄付とボランティアがなぜ欠かせないのか
1 寄付者を貢献者に変える戦略
2 ボランティアという顧客
第6章 社会変革の道筋を誰が描くのか
1 社会変革の担い手になるための条件
2 アドボカシーとは何か
3 社会変革を射程に入れた目標デザイン
3-1 目標の種類――インプットからアウトカム、インパクトへ
3-2 目標の設定方法――直感から論理へ
第7章 活動の価値をどうとらえるのか
1 社会変革とアウトカム評価
1-1 評価とは何か――成果確認のための方法論
1-2 社会が変化していることをどのように確認するのか
1-3 効果測定のための基本用語
2 市民が判断する公益性の評価
2-1 NPOと支援者が築く支援市場
2-2 関係者別にみたNPO評価――その整理と特徴
2-3 市民の評価を体現するパブリック・サポート・テスト(PST)
2-4 関係者の評の総意としてのPST
第8章 ほんもののNPOをめざして
1 日本の市民社会、再考
2 NPOセクターの課題
3 市民参加をうながすための制度的支援策
3-1 PSTの再評価
3-2 もうひとつの寄付――ボランティアとPST
3-3 税額控除の可能性
3-4 助成財団との連携
4 魅力的で信頼されるNPOとは
おわりに
参考文献
はじめに(一部抜粋)
なぜ、本著を記すのか
二〇〇六年に『NPOが自立する日――行政の下請け化に未来はない』という著書を記しました。多くのNPOでは財政難を背景に、比較的まとまった資金を得やすい行政の委託事業を増やしてゆくうちに公的資金への依存が高まり、その結果、行政の下請け化が起こっていることをそこで指摘しました。行政の下請け化にはいくつかの特徴がありますが、もっとも気になるのは新たなニーズの発見ができなくなり、NPOの真骨頂である社会的な創意工夫力すなわちイノベーション力が失われてゆくことでした。
その著書を出版してまもなく賛否両論の反響がりました。「下請け化がまずいことは百も承知だし、なりたいと思っている人なんていません。でも、どうしたらよいのでしょう?」という切実な問いかけもありました。以来、私は自ら提起した問題に対して答えを出すことは自分の責任であると強く感じてきました。
NPO法制定一〇年の成果と課題
NPO法制定から一〇年。今年(二〇〇八年)は節目の年といってよいでしょう。NPO法制定以来、三万五千近い団体が設立されました。他制度のもとに設立された法人数と比較しても、ひけをとらない数です。短期間のうちに大きく法人数を伸ばしてきたのです。
また、活動面でも実績を積み上げてきています。全国に七〇〇ほどある子育て広場のほとんどはNPO法人です。介護事業者の五%ほどをNPO法人が占めるようになりました。また、従来とはまったく異なる方法でホームレス支援のモデルを提示するなど、新たな問題解決方法やモデルを提示したNPOの活躍もみられます。
他方で、NPOセクター全体をみると、その内実は厳しいものと言わざるをえません。つまり、多くのNPOが経済的に自立できていないのです。年度末に剰余金(収支差額)がまったく残らないか、むしろ負債をかかえている団体は全体の六割以上におよびます。また、企業の「資本」にあたる正味財産がマイナスを示している団体が全体の一五%もあります。
企業とは意味が異なるところがありますが、それは債務超過の状態にあるということです。年度末になると現金が残らず、たいした資産もないわけですから、翌年度からの活動を維持することさえままなりません。信用力もないので金融機関からの借り入れも困難です。そこで事務局長の給与支払を遅らせたり、理事や職員から借り入れをすることで、活動維持のための現金を確保するという、苦肉の策で活動をつないでいる状況も明らかになってきました。このような状況をかんがみると、NPO法人の数を増やすことよりも、経営力を高め、信頼性を高めてゆくことに政策的な課題が移っているのではないかと思います。
(…略…)
(…中略…)
本著の目的
本著ではNPOの本質に立ち戻りながら、NPOセクターの一〇年をふりかえってみたいと思います。まず、NPO全体の財務状況を把握したうえで、行政の下請け化や社会的企業など今の傾向をふりかえり、そしてこの一〇年をどうとらえたらよいのかを考えてゆきます。
NPOセクターをふりかえり総括するためには、基準となる中心軸のようなものが必要になります。それはまさに、NPOとは何か、本来何をするために誕生したのかという本質論を見直すことでもあります。この問題を突きつめてゆくと、戦後日本の市民社会の再編という問題が浮上してきます。そこでは、有権者と政治家の関係の見直しや、知識社会における個人の生き方をも視野にふくめる必要があります。
この市民社会の再編という大きな課題において、NPOどのような役割を果たしうるのか。そのための戦略とはどのようなものであるべきなのか。それを支援する政策とは何であるのか。このような視点から、NPOの過去と未来について考えてゆきます。
内容説明
NPO法制定から一〇年。多くのNPOは経済的な困難を抱えながらも、自立をもとめて模索を続けている。では、NPOはどうすれば真の社会変革の担い手となりうるのか?この一〇年を総括し、寄付、ボランティア、アドボカシーの三つの観点から提言する。
目次
第1章 NPOはいま、どこにいるのか
第2章 NPOは何が変質したのか
第3章 この一〇年をどう総括するのか
第4章 市民性創造がなぜもとめられるのか
第5章 寄付とボランティアがなぜ欠かせないのか
第6章 社会変革の道筋を誰が描くのか
第7章 活動の価値をどうとらえるのか
第8章 ほんもののNPOをめざして
著者等紹介
田中弥生[タナカヤヨイ]
国際公共政策博士。独立行政法人大学評価・学位授与機構准教授。財務省財政制度審議会臨時委員。外務省ODA評価委員。東京大学工学系研究科客員助教授、国際協力銀行評価室参事役等を経て現在に至る。日本、東アジア、東南アジア、南部アフリカ、中枢の非営利組織の支援、研究を行う。その過程で非営利組織の評価に関心を抱き学び始める。現在はODAや政策評価などにも着手している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
a98s219
sidus