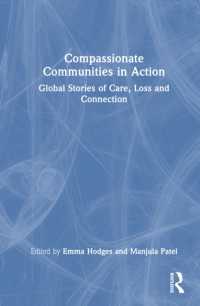出版社内容情報
海洋資源の持続可能な利用ために何が必要か。2003~06年、文化人類学を基盤に地理学、歴史学、水産学、地域研究、生態人類学の専門家が、世界各地における海洋資源の利用と流通、管理に関して実態調査を行った。本書はその学際研究の成果と課題を提示する。
国立民族学博物館「機関研究」の成果刊行について(松園万亀雄)
第1章 海洋資源の流通と管理に関する人類学的研究(岸上伸啓)
1 はじめに
2 「流通」と「海洋資源の管理」
3 広域に流通する海洋資源に関する人類学的研究
4 地域内を流通する海洋資源に関する研究
5 海洋資源の流通と管理をめぐる問題――流通と資源の枯渇化
6 本書の構成
第2章 社会資源としてのサケ――ユーコン川上流域の先住民社会におけるサケの重要性とそれをとりまく諸問題(井上敏昭)
1 はじめに
2 グィッチン
3 リアル・フードとその分配
4 サケ漁とその漁獲の加工
5 グィッチン社会におけるサケの分配
6 サケ漁と分配に関する近年の変化
7 先住民社会からみたサケ資源管理の諸問題
第3章 アラスカ・コディアック島の先住民による商業サケ漁(手塚薫)
1 はじめに
2 アラスカにおける水産業の特徴
3 アラスカの水産資源管理
4 コディアック島水産業発展の歴史と先住民の活動
5 オールドハーバー先住民による現在のサケ漁
6 サケ漁民と水産加工業者の言説
7 サケ漁民の対応
8 サケ漁の人類学的意義
9 サケの安全性と天然サーモンへの関心
10 海産資源の持続可能な利用のために
11 おわりに
第4章 「サケの民」カナダ北西海岸先住民族――サケの保存・調理・分配(岩崎まさみ)
1 はじめに
2 『クワキウトルの民族誌』について
3 サケ文化を伝承するナムギースの人びと
第5章 カムチャツカ先住民社会とサケ資源の分配・流通――その歴史的変遷と現状(渡部裕)
1 はじめに
2 調査の概要
3 カムチャツカのサケ資源をめぐる歴史
4 新たな制度の導入と現代の配分における課題
5 おわりに
第6章 カナダ・ニューファンドランドおよびラブラドル州における商業アザラシ漁――タテゴトアザラシの利用、管理、流通に関する一報告(浜口尚)
1 はじめに
2 アザラシ漁の生物学
3 「大西洋アザラシ漁管理計画」とアザラシ類資源の持続的利用
4 アザラシ漁の現況――二〇〇五、二〇〇六年の事例より
5 おわりに
第7章 漁業とサンゴ礁生態系の共存は可能か?――持続的資源利用・流通によるアジア太平洋の里海をめざして(鹿熊信一郎)
1 はじめに
2 爆弾漁
3 シアン化合物漁
4 サンゴ礁魚類養殖
5 サンゴ礁魚類の活魚流通
6 観賞用サンゴの養殖と流通
7 おわりに
第8章 刺参ブームの多重地域研究――試論(赤嶺淳)
1 はじめに
2 ナマコ食文化――刺参と光参
3 ナマコ戦争とワシントン条約
4 ナマコ資源の管理主体
5 利尻島におけるナマコ漁の栄枯盛衰
6 資源管理の実際――北海道利尻島の事例
7 結び
第9章 回遊魚シイラにみるハワイにおける魚食文化と観光(橋村修)
1 はじめに
2 世界のシイラの漁獲高と文化
3 ハワイにおけるシイラの魚食文化と漁業
4 ハワイを中心としたシイラ流通とその再編
5 考察とまとめ
第10章 禁忌と資源――人はいかに自然を説明するか(竹川大介)
1 はじめに
2 フツナ島の概要
3 資源管理と生業
4 タブーと呪術
5 考察
6 おわりに――転回する資源論
第11章 第四世界における贈与交換の展開――トレス海峡諸島先住民社会の内旋的適応(松本博之)
1 贈与と市場交換
2 第四世界としてのトレス海峡諸島
3 真珠貝漁業とトレス海峡諸島民
4 キリスト教と社会システム
5 パトロン=クライアント関係と再分配
6 戦後のイセエビ漁の展開と先住民社会
7 結びにかえて
第12章 海洋資源の流通と管理をめぐる研究の成果と今後の課題(岸上伸啓)
1 海洋資源の流通をめぐる問題
2 商業水産物と流通、資源管理
3 先住民による生業水産物の流通と資源管理
4 今後の課題――先住民社会の再生産と流通、資源管理
あとがき
索引
あとがき
本書は、国立民族学博物館の機関研究「文化人類学の社会的活用」のプロジェクト「日本における応用人類学展開のための基礎的研究」(二〇〇四年度~二〇〇八年度、代表者・岸上伸啓)の成果のひとつである。編者はこのプロジェクトを遂行するために、科学研究費補助金・基盤研究(A)「先住民による海洋資源の流通と管理」(二〇〇三年度~二〇〇六年度、代表者・岸上伸啓)と国立民族学博物館の共同研究会「開発と先住民族」(二〇〇五年度~二〇〇七年度、代表者・岸上伸啓)を最大限に活用した。したがって本書は、科研調査と民博の共同研究会の成果でもある。
二〇〇三年度から二〇〇六年度にかけて世界各地における海洋資源の利用と流通、管理の実態に関する現地調査を、編者は本書の執筆者たちとともに実施し、海洋資源を持続可能な形で利用するための方策を探った。二〇〇六年一一月一八日・一九日に各自の調査成果をもちより国立民族学博物館において一般公開のシンポジウム「先住民族と海洋資源の開発――利用・流通・管理」を開催した。本書は、同シンポジウムの報告をベースにしたものである。
一連の現地調査とシンポジウムによって世界各地には海洋資源に関してさまざまな利用形態、管理形態、流通形態が存在していることが明確になった。また、海洋資源の利用や管理をめぐる紛争や枯渇化などの問題が存在することも判明した。さらにグローバル化が進む現代社会においては、特定の地域における海洋資源の利用を制限し管理することだけではその枯渇化を防ぐことは困難である、ということもわかった。そして海洋資源を持続可能な形で利用するためには、生産者と消費者を結ぶ地域を越えた流通のネットワークを考慮にいれた管理制度を設計することが必要である、という結論に達した。
本研究は、文化人類学を基盤としながら地理学、歴史学、水産学、地域研究、生態人類学の専門家が参加した学際研究である。さらに、人間を中心にすえた基礎的な研究でありながらも、応用的実践を指向するあらたな試みである。本書の第一二章でまとめたように、本研究は一定の成果をあげたが、今後の研究課題もいくつか残った。また、本書の成果が海洋資源の持続可能な利用の実践にどのように貢献しうるかも今後の問題である。しかしながら執筆者らは、近い将来、地道な研究の積み重ねが社会的実践に結実することを願ってやまない。今後の研究の発展のためにも、本書について読者諸氏にご批判・ご叱正を請う次第である。
(…後略…)
目次
海洋資源の流通と管理に関する人類学的研究
社会資源としてのサケ―ユーコン川上流域の先住民社会におけるサケの重要性とそれをとりまく諸問題
アラスカ・コディアック島の先住民による南業サケ漁
「サケの民」カナダ北西海岸先住民族―サケの保存・調理・分配
カムチャッカ先住民社会とサケ資源の分配・流通―その歴史的変遷と現状
カナダ・ニューファンドランドおよびラブラドル州における商業アザラシ漁―タテゴトアザラシの利用、管理、流通に関する一報告
漁業とサンゴ礁生態系の共存は可能か?―持続的資源利用・流通によるアジア太平洋の里海をめざして
刺参ブームの多重地域研究―試論
回遊魚シイラにみるハワイにおける魚食文化と観光
禁忌と資源―人はいかに自然を説明するか
第四世界における贈与交換の展開―トレス海峡諸島先住民社会の内旋的適応
海洋資源の流通と管理をめぐる研究の成果と今後の課題
著者等紹介
岸上伸啓[キシガミノブヒロ]
国立民族学博物館・総合研究大学院大学教授。専攻は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。