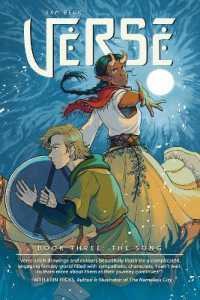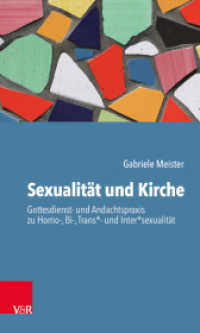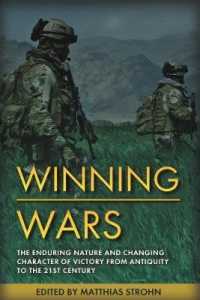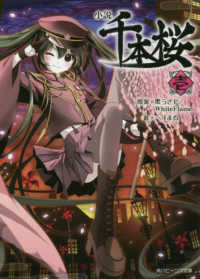出版社内容情報
家庭内で男性から虐待を受けている女性の子どもは、母親と同様にその虐待の被害者です。虐待を目撃した子どもの複雑な感情を、虐待を受けている母親自身や専門家たちに理解できるよう促し、母子が健全な生活を送れるよう援助する方法や指針を示します。
日本の読者の皆さんへ
謝辞
はじめに
第1章 子どもたちはパートナーの暴力を見聞きしている
第1部 虐待する男性とその子ども
第2章 虐待心性(虐待をする心理状態)と子ども
第3章 虐待する男性が父親となったとき
第4章 子どもの内的世界を理解する
第5章 子どもの境界線を守る
第2部 虐待する男性と家庭のダイナミクス
第6章 アボット家の週末
第7章 母親としての役割を守る
第8章 家族の健全なダイナミクスを維持する
第9章 去るべきか、去らざるべきか
第10章 児童保護機関と折りあう
第3部 虐待する父親と子ども―別居後―
第11章 子どもにとっての両親の別居や離婚の意味
第12章 別居後の虐待する父親
第13章 家庭裁判所の制度の中で解決策を見出す
第4部 明日に向かう子どもたち
第14章 子どもの治癒を促す
第15章 子どものエンパワメント
第16章 虐待の悪循環を断つ
参考資料と関連情報
虐待されたお母さんの個人的な話を聞かせてください
日本国内の配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設リスト
監訳者あとがき
日本の読者の皆さんへ
この地球上の国々は、これまでドメスティック・ヴァイオレンス――夫、恋人、親密な関係のパートナーによる女性への虐待が横行しているという事実を認めようとせず、とりくもうとしていませんでした。各国政府はそうした問題は存在しないことにしておく、あるいは暴力や脅迫を受けるのは女性に問題があるからだ、ということにしておくほうが簡単だと考えていたのです。女性たちは小さな問題を大げさに騒ぎ立てすぎだと責められ、男性のしもべという社会的役割を拒むことが男性の虐待を引き起こしているのだと責められてきました。
しかし幸いにも、私たちの暮らしている現代においては、女性に対する家庭内虐待を否定することができなくなりました。秘密が明らかになったのです。勇気ある活動家や研究者たちにより、多くの女性たちがパートナーからの身体的暴力や性暴力にさらされていることが証明され、何千人もの勇敢な女性たちが意を決して虐待の体験を公のもとに開示しました。また、世界中の女性団体がドメスティック・ヴァイオレンスに対する政府の怠慢に抗議したことが功を奏して、大幅な法改正が実施され、法廷や警察の対応が見られるようになり、シェルターやそのほかの社会的支援が利用できるようになり、地域社会が女性に対する虐待を問題視するようになりました。国連やそのほかの国際機関は、女性の人権に、自分自身の家庭で安全かつ平等に暮らす権利が含まれることを宣言しました。
もちろん日本の社会も、こうした過程をたどってきました。女性への家庭内虐待に対して国がもっと対応すべきだと主張する団体の努力が実り、過去10年ほどの間に、国は男性の暴力を食いとめることが最優先事項であると認識するようになり、社会的支援は大きく向上し、国民意識もかなり高まりました。女性の権利が完璧に尊重されるようになるまでには、まだ長い道のりが残されていますが、日本はドメスティック・ヴァイオレンスの問題にしっかりと向きあっており、そのとりくみは、将来への希望とインスピレーションを与えてくれます。
家庭内で男性の被害を受ける女性の問題に社会がとりくみはじめたことで、こうした攻撃的な男性が、同じ屋根の下に暮らす子どもに与えている悪影響にも注意を向ける必要が出てきました。母親をひっぱたいたり殴ったり、脅したり怯えさせたり、セックスを強要したり、暴言によって母親が精神的にボロボロになるまで痛めつけたりする父親または父親代わりとなる人と接しながら暮らしている子どもは、母親と同様に、その虐待や価値の引き下げの被害者なのです。にもかかわらず、子どもの体験や心の傷は、虐待された女性の体験に比べ、あまり認識されていません。
本書『DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す――お母さんと支援者のためのガイド』は、支配的な男性や虐待する男性と暮らす子どもと母親がともに抱えている問題の解決に貢献することをめざしています。私はこの本を、特に虐待を受けている母親自身に向けて書きましたが、専門職も念頭に置きました。ですから、児童福祉の専門職、セラピスト、虐待された女性の擁護者、教職員、そのほか地域社会でさまざまな役割を担う人も、虐待を目撃した子どもの複雑な感情をどのように理解するかについての情報を得ることができるでしょう。また、同様に重要なことなのですが、子どもと母親が安全と自由を手に入れられるよう支援する方法や、彼らの心の傷を癒し、虐待や抑圧のない、健全で幸福な人生を送れるよう援助する方法についての指針を得ることもできるでしょう。
子どもに手を差し伸べ、援助するにあたって、さまざまな分野の職種がその役目を果たすことができますが、最大の援助を与えることのできるのは母親です。前作『DVにさらされる子どもたち――加害者としての親が家族機能に及ぼす影響』(The Batterer as Parent. 2002年。邦訳/幾島幸子訳、金剛出版、2004年)も、ドメスティック・ヴァイオレンスとともに生きる子どもが受ける傷についての多くの洞察を与えていますが、母親が子どもの心の内側に入っていく方法についての指針や支援についてはふれていませんし、子どもが家庭内で受けたトラウマ体験からどのように癒され、回復するのかについても論じていません。
そこで本書は、前作でふれなかった部分からお話しし、続いて母親の自由と子どもの癒しについて書いています。本書を読む母親たちが、エンパワメントされたと感じて、子どもの苦しみを和らげられるように、虐待者の言動は正しくないこと、虐待はほかの誰のせいでもなく虐待者本人の問題であることを子どもが理解するのを促せるように、将来子どもが健全な人間関係を築くのを支援できるようになることを願っています。
また、虐待について子どもと話しあう方法、子どもが自分の感情を人とわかちあえるよう支援する方法、虐待者の言動や態度を身に付けてしまわないようにする方法なども学ぶことができます。さらに、本書に書かれた洞察や提案を通して、母親が子どもと親密な関係を維持し、虐待する男性の多くが仕組む家族間の緊張や対立関係に抵抗するために必要な手段を与えることができれば、というのも私の強い願いです。あなたとお子さんは互いに必要としあっています。たとえ虐待する男性の言動があなたたちを引き裂いてしまうのではないかと恐れる日々が続いたとしても、愛の絆をしっかりと守り抜く方法はいくつもあります。
私たちは皆、女性や子どもが家庭内で安全に安心して暮らせる社会、身内に対する暴力や脅しなど過去の話だと言える社会を築き上げることができます。この本に書かれているような虐待を受けた経験があるかどうかにかかわらず、皆さんにとってこの本が、そのような社会を築くための行動を起こすきっかけとなることを願っています。
平和を祈って
2006年11月
ランディ・バンクロフト
目次
子どもたちはパートナーの暴力を見聞きしている
第1部 虐待する男性とその子ども(虐待心性(虐待をする心理状態)と子ども
虐待する男性が父親となったとき
子どもの内的世界を理解する
子どもの境界線を守る)
第2部 虐待する男性と家庭のダイナミクス(アボット家の週末;母親としての役割を守る;家族の健全なダイナミクスを維持する;去るべきか、去らざるべきか;児童保護機関と折りあう)
第3部 虐待する父親と子ども―別居後(子どもにとっての両親の別居や離婚の意味;別居後の虐待する父親;家庭裁判所の制度の中で解決策を見出す)
第4部 明日に向かう子どもたち(子どもの治癒を促す;子どものエンパワメント;虐待の悪循環を断つ)
著者等紹介
バンクロフト,ランディ[バンクロフト,ランディ][Bancroft,Lundy]
加害者専門カウンセラー、臨床スーパーバイザー、監護権評定者、子ども虐待調査官などを歴任。米国マサチューセッツ州にて1000人を超えるDV加害者のケースに関わる。他にもDVがある家庭に育った10代男子のためのグループ活動を行ったり、女性の人権問題などでも精力的に活動。著書にWhy Does He Do That?:Insides the Minds of Angry and Controlling Men、ハーバード大学公衆衛生学教授Jay Silvermanとの共著The Batter as Parent(『DVにさらされる子どもたち―加害者としての親が家族機能に及ぼす影響』金剛出版、2004年)は、北米児童リソースセンター(North American Resource Center for Child Welfare)2004 Pro Humanitate Literacy Award受賞
白川美也子[シラカワミヤコ]
浜松医科大学を卒業後、同大学精神科教室に入局し、いくつかの病院を経て2000年度より国立病院機構天竜病院精神科医長を務める。2006年度より、浜松市保健福祉部保健福祉施設設置準備室副参事、2007年度より浜松市精神保健福祉センター。精神保健指定医。トラウマティックストレス学会理事、静岡犯罪被害者支援センター理事、NPO法人女性の安全と健康のための支援教育センター理事、全国乳児福祉協議会協議員など。専門は精神療法、女性と子どもの精神医学、特にPTSDや解離性障害など外傷性精神障害
山崎知克[ヤマザキトモカツ]
東京慈恵会医科大学を卒業後、同大学小児科学講座に入局し、小児科一般および小児精神臨床に取り組む。2002年度より国立病院機構天竜病院精神科にて定期研修を開始、2004年度に同病院に赴任、2006年10月より好生会三方原病院精神科医長。東京慈恵会医科大学小児科学講座助手、医学博士、日本小児科学会認定医、日本小児精神神経学会評議員、全国乳児福祉協議会常任協議員、静岡県西部児童相談所精神科嘱託医(非常勤)、浜松乳児院精神科嘱託医(非常勤)。専門は小児精神医学、小児科学、特に子ども虐待など親子の関係性障害
阿部尚美[アベナオミ]
1959年三重県生まれ。南山大学文学部英語学英文学科卒。シラキュース大学コミュニケーション学部修士課程修了。会社員を経て翻訳者に
白倉三紀子[シラクラミキコ]
1997年より編集者・ライターとして出版に従事。2002年に翻訳家としての活動を開始し、アート、文化、旅、ライフスタイルをテーマにした書籍、雑誌などの翻訳、編集を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
okaching