出版社内容情報
長らく異文化間教育が関心を寄せてこなかった乳幼児期に焦点をあて、多文化化が進む社会で生きる子どもたちの連続した発達をどう支援すればよいのかを追究する。「異文化間教育」と「発達」の視点から、豊富な保育実践例をもとに理論の構築をめざす。
はじめに
序章 乳幼児をとりまく多文化的状況(渋谷 恵)
第1部 フィールドワークからみえてきたもの
第1章 中国人5歳児の仲間関係への適応過程――関係発達論の視点から(柴山真琴)
第2章 環境に埋め込まれた保育観と乳幼児の発達(塘 利枝子)
第3章 乳幼児期における多様性尊重の教育――アンチバイアス教育を手がかりとして(山田千明)
第2部 アジアにおける異文化間教育研究
第1章 中国における異文化間教育研究(高 向山)
第2章 台湾における幼児教育研究――台湾の外国人花嫁の子どもの教育問題(翁 麗芳)
第3章 韓国における異文化間教育研究(崔 順子)
第4章 日本における異文化間教育研究(柴山真琴)
第3部 乳幼児期からの異文化間教育への理論的視座
第1章 乳幼児期からの異文化間教育とは(松尾知明)
第2章 異文化間接触の文化化構造(廿日出里美)
コラム 日本で幼少期を過ごした娘たちとともに(玄 正煥)
第3章 子どもの実践知(廿日出里美)
おわりに
【資料】日本、中国、台湾、韓国の保育・幼児教育制度
はじめに
子育てや保育の場における「多国籍化」「多文化化」が進行するなか、子どもたち同士、また、親、保育者など子育てや保育に関わる人々のあいだで、異文化間の交流・接触は日常的なものとなっている。本書は、フィールドワークの経験をもつ保育学、教育人類学、比較・国際教育学、多文化教育学、発達心理学、異文化間心理学など多分野の執筆者たちが、「異文化間教育」と「発達」をクロスして捉えることの重要性に着目し、具体的な保育実践から保育現場の現実を多角的に捉え、乳幼児期からの異文化間教育構築を試みて著した書である。保育実践者の研修、保育者養成校の必修科目「総合演習」などの授業において用いられるテキストとしても異文化理解に関する新たな気づきを促進し役立つよう編まれている。
異文化間教育において幼児の問題が研究対象として認識されるようになったのは、「多文化社会の教育」が日本でも顕在化しはじめた1980年代の終わり頃である。この時期以降、外国人の乳幼児を受け入れることになった幼稚園や保育所などの関係者による実践報告が急増している。しかしこうした研究の多くは、研究対象の実態や現状を明らかにすることに焦点があたり、方法論と理論の吟味が十分なされているとはいいがたい。本書のような、フィールドに密着し複数の専門領域からの多角的アプローチによる理論化構築をめざした研究は今まで行われてこなかったといえよう。
執筆者たちは、2000年5月に異文化間教育学会のラウンド・テーブルで「幼児期からの異文化間理解教育とは?」を企画するなど、6~7年前から乳幼児期からの異文化間教育構築をめざし情報交換を行っていた。異文化間教育は、他者との違いを認識しはじめる乳幼児期から実践することが重要であるにもかかわらず、従来、「幼い子どもは、異なった環境におかれてもすぐに慣れるから……」と、もっぱらその関心は、学齢期以降であった。しかし実際は、乳幼児たちも異文化のなかではとまどい混乱する。編者の長女は3歳~5歳までアメリカで生活した。渡米当初は、異常とも思える高笑いをよくした。また、プリスクールには、登園時間になると大泣きして行くのを嫌がり、最初の1年間は国内でほとんど英語を(もちろん日本語も)話さなかった。相手の言うことがかなり理解できるようになった後も英語での発話がほとんどなかった理由を、「アメリカへ行ったら英語がペラペラになる」と皆に言われてアメリカに来たのに耳に入る英語がまったく理解できない、ペラペラ英語が話せない自分に混乱したのだ、と後になって本人は分析する。
そのようななか、私たちの研究グループが申請していた科学研究費補助金の交付決定通知を受け取った(平成13~15年度「幼児期からの国際理解教育構築への多角的アプローチ」〈研究者代表:山田千明〉)。採択の知らせを受けたとき、「乳幼児期から」の国際理解教育が補助金対象に値する研究だと認められたことに歓喜したことを今でも鮮明に覚えている。
補助金交付でフィールドワークによる共同研究が可能となった。執筆者たちは都合がつけば共同で、そうでなければ個人でフィールドワークを実施した。共同で実施したものに、2001年度の台湾、韓国および日本での調査、2002年度の中国、日本での調査、2003年度の日本での調査がある。かなりハードなスケジュールでフィールドワークを行い、その後のディスカッションで、各自大いなる刺激を受けた。同時に同じフィールドに入っても、教育学、発達心理学、人類学などと領域が異なると、「見えるもの」も、「見え方」も異なってくる。フィールドワーク終了後、各自が撮影したビデオや写真を共有するのだが、撮影場面がそれぞれ異なり大変興味深かった。
比較的早くから移民の問題を抱えていたアメリカ、オーストラリア、ドイツなどでは、心理学、教育学、人類学、言語学を駆使した外国人幼児の保育のためのガイドラインが作成されているが、その評価をめぐっては、まだ議論の余地が多く残されている。また、西欧以外の諸国における外国人幼児の保育の調査・研究もみられるようになり、西欧の理論的枠組を再検討しようとする動きが活発化しつつある。本書では欧米の諸理論やアジアの現状とも比較し、乳幼児期からの日本の異文化間教育の可能性について探る。また、高向山先生、翁麗芳先生、崔順子先生による、中国、台湾、韓国の研究動向の整理により、他の筆者たちが短い期間のフィールドワークでは掘り起こせなかった状況を提示してもらえた。
本書は、序章で「乳幼児をとりまく多文化的状況」を概観し、「フィールドワークからみえてきたもの」「アジアにおける異文化間教育研究」「乳幼児期からの異文化間教育への理論的視座」の3部構成となっている。具体的には、中国人5歳児の仲間関係への適応過程、環境に埋め込まれた保育観と乳幼児の発達、乳幼児期における多様性尊重の教育、アジアにおける研究動向の整理、乳幼児期からの異文化間教育とは、異文化接触の文化化構造、子どもの実践知など、各自がもっとも関心をもつ事項を取り上げ、乳幼児期からの異文化間教育の理論構築に向けてアプローチした。さらに巻末資料として、「日本、中国、台湾、韓国の保育・幼児教育制度」を掲載したので、比較教育学、異文化間移動する子どもの発達の連続性に関心をもつ方々にご利用いただきたい。
本書は、ひとつひとつの事象を丁寧に分析しながら、「異文化間教育」と「発達」をクロスしようと試みた書である。研究者の方々だけでなく、幼稚園教諭、保育士など幼児教育や保育を担う方々、保育者をめざす学生の方々、子育て中の保護者の方々をはじめとする多くの方々にとって、多文化のなかで生きる子どもたちの連続した発達をどう支援すればよいのか考える契機となれば幸いである。とくに、保育者養成系の教育機関で学ぶ学生の方々には、ぜひ本書を読んでから保育現場に出ていただきたいと切望してやまない。
2006年6月
編著者 山田千明
目次
乳幼児をとりまく多文化的状況(国境を越えた移動・居住の活性化;多文化化が進む保育機関)
第1部 フィールドワークからみえてきたもの(中国人5歳児の仲間関係への適応過程―関係発達論の視点から;環境に埋め込まれた保育観と乳幼児の発達;乳幼児期における多様性尊重の教育―アンチバイアス教育を手がかりとして)
第2部 アジアにおける異文化間教育研究(中国における異文化間教育研究;台湾における幼児教育研究―台湾の外国人花嫁の子どもの教育問題;韓国における異文化間教育研究;日本における異文化間教育研究)
第3部 乳幼児期からの異文化間教育への理論的視座(乳幼児期からの異文化間教育とは;異文化間接触の文化化構造;子どもの実践知)
著者等紹介
山田千明[ヤマダチアキ]
共栄学園短期大学社会福祉学科助教授。福井県出身。AFS交換留学生として米国ミネソタ州キャンビーハイスクールに留学。筑波大学第二学群比較文化学類卒、同大学院修士課程教育研究科修了、同大学院博士課程教育学研究科単位取得退学。茶道総合資料館(裏千家今日庵)職員、高校教諭、筑波大学教育学系助手を経て現職。宇都宮大学教育学部非常勤講師。専門は、比較・国際教育学と多文化保育学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tokotoko
かっぺ(こと悩める母山羊)
Wulan
-

- 電子書籍
- 大台ケ原の自然誌 森の中のシカをめぐる…
-
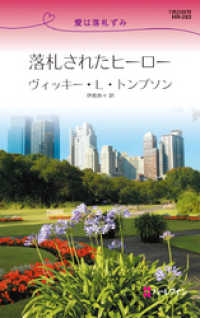
- 電子書籍
- 落札されたヒーロー ハーレクイン







