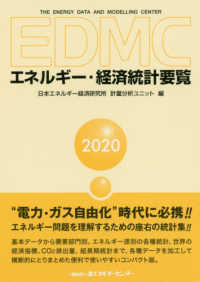出版社内容情報
神奈川県で早くからDVと闘ってきた民間シェルター記録。自立を目指すDV被害者とそれを支援する活動は、被害者を取りまく現実の理不尽さを訴えてやまない。ボランティアの体験談や専門家との対談などを収めるほか、DV関連年表および関係資料を付す。
はじめに
DV関連用語解説
第1章 DV被害者と向き合って
みずらシェルターとは *金田麗子(みずら理事)
逃れるということ、振り切るということ *S・O(三六歳、みずらボランティア歴五年)
シェルター利用者に助けられたこと *R・I(四九歳、みずらボランティア歴九年)
忘れられない経験 *M・T(三九歳、みずらボランティア歴九年)
食卓を囲む被害者たち *K・Y(五七歳、みずらボランティア歴一五年)
私がシェルターで出会った人たち *K・H(五四歳、みずらボランティア歴七年)
日々試されている *K・O(五三歳、みずらボランティア歴一六年)
子どもたちにできること *Y・N(六二歳、みずらボランティア歴九年)
現代版 女三界に家なし *T・I(六一歳、みずらボランティア歴一一年)
第2章 対談 DV最前線
シェルターでいま、何が起きているか
対談者*狩野敦子(社会福祉法人礼拝会ミカエラ寮施設長)
司法の場におけるDVへのまなざし
対談者*川島志保(弁護士・横浜弁護士会)
DV被害と児童虐待――子どもをいかに守るのか
対談者*佐藤隆司(神奈川県相模原児童相談所指導課長補佐)
DV被害者の抱える精神的困難
対談者*阿瀬川孝治(精神科医)
神奈川県のDV被害者救済システムと取り組み――「神奈川県の方式」とは?
対談者*栗原ちゆき(元神奈川県立女性相談所指導課長)
外国籍女性のDV被害
対談者*三木恵美子(弁護士・横浜弁護士会)
*武藤かおり(特定非営利活動法人女性の家サーラー理事)
第3章 座談会 地域で「女性への暴力」と闘い続けて
――相談者から学び、現実的な解決を目指す「みずら相談活動」の一七年
資料編
みずら年表 みずらvsDV(1988~2005)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画・かながわDV被害者支援プラン(抜粋)
おわりに
はじめに
DV、あるいはドメスティック・バイオレンスという耳慣れない外来語は、一九九〇年代半ばに忽然と私たちの前に現れた。この言葉はそれまで誰も語ることのなかった、けれど決して稀ではない夫婦の現実をあらわにして社会的関心を集める推進役となった。私たちは「ドメスティック・バイオレンス」という言葉を得てはじめて、夫が妻を殴ることの重大な意味を悟ったのである。
夫と妻が互いに思いやり、慈しみ合うはずの家庭で繰り返される激しい暴力は、到底「夫婦喧嘩」などという言葉で表されるようなものではないこと。妻は暴力によって支配されて家庭から逃げ出せずにいること。多くの場合、子どももまた暴力の被害にさらされ、心も体も傷つけられていること。ときには、妻や子の死という最悪の結末さえもたらすこと。何より、暴力に満ちた家庭で育った子どもは生涯にわたって消えることのない、深い深い傷痕を胸に抱いて生きていかねばならないこと……。
こうした、あまりにも重大な事実に私たちはようやく気づいたのである。
DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉が喚起した社会的関心の高まりによって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が制定され、各地に「シェルター」と呼ばれる緊急一時避難所が生まれ、自治体は被害者の自立に向けた援助に取り組み始めた。対策は徐々に進んできたかに見える。けれど、民間シェルターのスタッフの一人として、被害女性と子どもたちが受けた被害の重さと、今後も続くに違いない過酷な現実の一端を垣間見る時、「自立支援」という言葉で表される現状はあまりにも不備が多い。
一九九〇年、「女性のための何でも相談」として産声を上げたみずらは、女たちの相談に耳を傾けるうち、家庭の中で理不尽な暴力にさらされている女性たちがいることを知った。その現実に背中を押されてDVという言葉も知らないまま、女たちに隠れ家を提供することになった。だが、夫の元からようやくの思いで逃げ出した後に出会う現実はあまりにも過酷で生きづらく、夫が変わってくれることに一縷の望みを託して、子どもの手を引いて家庭に戻っていった女性たちもいた。
DV防止法が成立し、改正法が施行されてなお、夫やパートナーの暴力によって家を失った女性と子どもが、経済的にも精神的にも安心して安定した生活を送れる環境はいまだ整っていない。直面する現実の厳しさにも大きな変化はない。
今回、本書の出版を思い立った背景には、こうした現実への苛立ちと焦燥がある。
第1章では、シェルターでの生活をサポートするケアスタッフが、被害女性と子どもたちの日常生活を書いた。「わが家」から着の身着のまま逃げ出さざるを得なかった女性と子どもが、シェルターという緊急一時保護施設でどんな暮らしを送っているのか、その現実の一端を知っていただければとの思いからである。
第2章では、DV被害者の保護と自立支援に取り組む、さまざまな立場の専門家を招いて「DV最前線」について語り合った。被害女性が女一人で、あるいは子どもを抱えて自立しようとして出会う困難と課題をさまざまな立場で語ってもらうことで、「自立支援」という言葉を耕していきたいとの願いからである。
第3章では、みずらという私たちの団体が女性への暴力といかにして出会い、どのように闘ってきたのか、その歩みをメンバーの座談会を通して振り返った。自分たちの来し方を振り返って検証し、今後の活動に役立てたいとの思いからである。
巻末の資料編では、みずらの歩んできた一七年の歳月を「女性への暴力との闘い」という視点で整理し、年表とした。さらに、わが国で最もDV対策の進んだ自治体と自負する神奈川県の自立支援プラン『かながわDV被害者支援プラン』の骨子を乗せ、併せて昨年四月に神奈川県女性相談所が行った「DV被害者の同伴児調査の結果の概要」を参考資料として付した。これらの資料を通してDVという犯罪への認識を新たにし、さらには、これまで「見えない被害者」として見過ごされてきた子どもたちの被害の一端を知っていただければとの願いからである。
何より、この本を編む過程そのものによって、被害女性と子どもたちの自立に寄り添う団体として成長していきたいとの強い思いがあった。
私たちの思いを読み取っていただき、ドメスティック・バイオレンスへの理解を深める一助としていただければ幸いである。
二〇〇六年四月
編者を代表して 安宅左知子
目次
第1章 DV被害者と向き合って(みずらシェルターとは;逃れるということ、振り切るということ;シェルター利用者に助けられたこと;忘れられない経験;食卓を囲む被害者たち ほか)
第2章 対談 DV最前線(シェルターでいま、何が起きているか(狩野敦子(社会福祉法人礼拝会ミカエラ寮施設長))
司法の場におけるDVへのまなざし(川島志保(弁護士・横浜弁護士会))
DV被害と児童虐待―子どもをいかに守るのか(佐藤隆司(神奈川県相模原児童相談所指導課長補佐))
DV被害者の抱える精神的困難(阿瀬川孝治(精神科医))
神奈川県のDV被害者救済システムと取り組み―「神奈川県の方式」とは?(栗原ちゆき(元神奈川県立女性相談所指導課長)) ほか)
第3章 座談会 地域で「女性への暴力」と闘い続けて―相談者から学び、現実的な解決を目指す「みずら相談活動」の一七年
資料編
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
akubineko
-
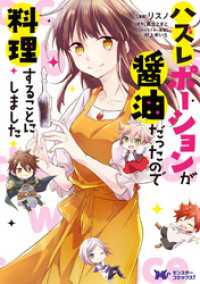
- 電子書籍
- ハズレポーションが醤油だったので料理す…
-
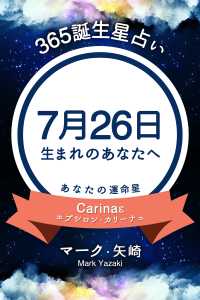
- 電子書籍
- 365誕生日占い~7月26日生まれのあ…