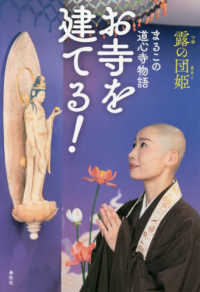出版社内容情報
日本文化は単線的に発展したものではなくその底流には多くの基層文化を抱えている。アイヌ、朝鮮半島、南方文化…日本文化の基層に流れるさまざまな潮流を探り、その影響を考える。同時に現代日本社会・文化の変革の可能性を基層文化との関係から構想する。
特集のことば
特集【日本文化――その成り立ち】
巻頭対談
日本文化の多様な構造(赤坂憲雄/東北芸術工科大学教授×沖浦和光/桃山学院大学名誉教授)
日本人の起源論をめぐって(尾本惠市/総合研究大学院大学・葉山高等研究センター・上級研究員)
何が列島の文化の豊かさを奪ったのか(千本秀樹/筑波大学教授)
「東アジア共同体」と歴史認識の問題(沖浦和光)
日本文化史における秦氏(川上隆志/専修大学助教授)
南蛮文化の文化史的影響(笠井惠二/京都産業大学教授)
仏教のなかの女性差別(源 淳子/女性学研究者)
輝ける闇の国家・熊野(和賀正樹/ジャーナリスト)
文化の十字路・佐渡(浜野 浩/佐渡鉱山町文化史研究会)
火の神をたずねて(中山銀士/グラフィック・デザイナー)
琉球文化圏の風土性(真久田 正/『うるまネシア』編集委員)
鉢叩きの残像(平松真一/郷土史家)
中上健次「闇の国家」論(川野真衣)
[現代と思想家]
ナショナリズムと柳田民俗学(橘川俊忠/神奈川大学教授)
[発信]
性別秩序(ジェンダー)をめぐる攻防(池田祥子/本誌編集委員)
[文化時評]
二〇一〇年から振り返る四年前のワールドカップ(陣野俊史/批評家)
[メディア時評]
日本は民主主義の国か(喜多村俊樹/ジャーナリスト)
[想うがままに]
熊沢誠さんの退職を労う(小寺山康雄/本誌編集委員)
[この一冊]
『傍観者の時代』ドラッカー著(宮崎 徹/本誌編集委員)
『前川國男 賊軍の将』宮内嘉久著(南雲明男/本誌編集委員)
[医療と現代]
再生医療の現在(富澤瑞穂/医療問題研究者)
米中による世界共同管理論の台頭(叶 芳和/拓殖大学教授)
最近の改憲動向と立憲主義の危機(山内敏弘/龍谷大学教授)
狭山事件 最高裁特別抗告棄却の論理(鎌田 慧/ルポライター)
「日本司法支援センター」の意味するもの(石田省三郎/弁護士)
◎本誌前号住沢博紀論文
「憲法改正と東アジア共同体への選択」をめぐって(進藤榮一/江戸川大学教授、唐 亮/横浜市立大学教授、小林正弥/千葉大学教授、蜂谷 隆/阿部知子衆議院議員政策秘書、小林良暢/グローバル総研所長、山田 勝/本誌編集委員)
06夏号(VOL.8)予告
編集後記
特集のことば
歴史認識
環境・エネルギー・食糧・人口・人権、そして安全保障――アジアの諸国はそういった地球規模の危機に大なり小なり直面しているが、いずれも一国だけでは乗り越えられぬ難問である。
政治レベルでは、現在の六者協議が、東アジアの集団安保体制の足固めになるかどうか。経済レベルでは、自由貿易地域と共通通貨の実現を遠望する「東アジア共同体」論が活発になりつつある。靖国問題で首脳間の対話もできない現状では、そういう構想は空中楼閣のように見える。しかし、靖国問題の根源にあるものを解きほぐしていかなければ、腹を割った対話はできない。国家の壁を越えた〈人的交流〉と〈文化理解〉を実現するためには、どうしても「歴史認識」の問題を解決せねばならない。
その意味では中国と韓国が日本の現政府に見切りをつけたこと自体が、新しいアジア状勢を創出する重要なきっかけになる。そのことを察知した小泉首相は、急速に精気がなくなった。「まず天皇に靖国に参拝してもらえ」と見当違いの暴言を吐く外相が補佐役なのだ。小泉の後継と目されているのも、同じ穴の狢(むじな)のようで、まことに頼りない。日本の対米貿易比重は二〇%を割り、対アジアは五〇%を超えた。イラクで大失態をやらかしたブッシュ一辺倒の外交政策のドン詰まり――こういった基礎教養と歴史的センスに欠ける連中に舵取りは任せておけないと、心底一番危惧しているのは経済界だろう。
小泉政権後、外交では新しい次元での東アジア共同体論、国内では改憲と安保体制論が当面の争点になってくるだろうが、いずれにしても靖国に端を発した「歴史認識」が先決問題となる。その検討されるべき「歴史」は、明治維新まで遡ればよいというものではない。それぞれの国家の民族構成と文化の源流を踏まえて、有史以前まで視圏に入れて論じなければならない。それはまた、東アジアの諸国家の成り立ちと歴史的変遷、それに基いたナショナル・アイデンティティの根本にまで及ばねばならない。
迂遠な回路のように見えるが、「歴史認識」の問題を解決する糸口になるのは、東アジア全体の歴史や文化の基層まで掘り下げた論議である。日本民族の起源論と大和王朝の成り立ちを論点に含めた本特集は、そのための第一歩である。