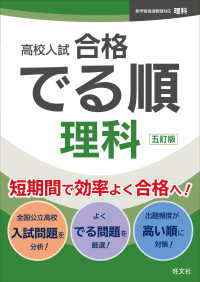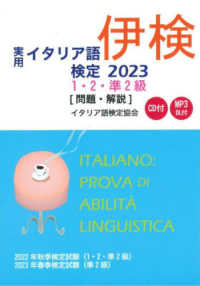出版社内容情報
1994年の「サラマンカ宣言」以降、世界各国でインクルーシブ教育の実践はどのように行われているのか。 そこにはどんなジレンマと緊張があり、可能性があるのか。国際的な比較によって、共通の問題に対する解決策を見いだし、新しい洞察を提供する。
謝 辞
ペーパーバック版へのシリーズ編者序文
ペーパーバック版への編者序文――新しい千年への挑戦
序 章
第1部 民主制における特殊教育の明確化
第1章 インクルーシブ教育――民主制社会における要件
第2章 教育に対する個人の権利と障害のある子ども――アメリカの政策からの教訓
第3章 インクルージョンとインクルージョンズ――インクルーシブ教育の理論と言説
第4章 市場のイデオロギー、教育、そしてインクルージョンに対する挑戦
第2部 インクルーシブ教育のジレンマ
●変革期にある制度
第5章 イングランドとウェールズ――「競争と管理」か「関係当事者による参加とインクルージョン」か
第6章 アメリカ合衆国における「欠陥」イデオロギーと教育改革
第7章 オランダ――キャッシュフローの方向性変更による統合への支援
第8章 転換期にある北欧型福祉国家における「統合」
第9章 カナダにおけるインクルージョン運動――哲学、展望そして実践
第10章 スペイン――自治地域のインクルージョンに対する反応
●変化しつつある制度
第11章 癒しの社会に向かって――日本の特殊教育からの見地
第12章 チェコ共和国におけるインクルーシブ教育の課題――変わりゆくシステム
第13章 ブルガリア――ジプシーの子どもと特殊教育に関する社会的概念の変化
●開発期の制度
第14章 チリにおけるインクルーシブ教育の開発――私的制度対公的制度
第15章 南アフリカにおけるインクルーシブ教育――公正と多数派の権利の達成
第16章 南ブラジルにおける教授法に関する言説と学業不振
第3部 インクルーシブ教育に関する対話
第17章 福祉国家と個人の自由
第18章 政策と実践? インクルーシブ教育と学校教育への影響
第19章 南アジア系青年と 人種差別、エスニック・アイデンティティ、教育
第20章 グローバリゼーションと文化伝達――展開しつつあるインクルージョンの実践における国際機関の役割
第21章 排除――中産階級と共通善
第22章 権利擁護、自己権利擁護とインクルーシブな活動――まとめ
訳者あとがき
索 引
訳者あとがき
本書は、Harry Daniels and Philip Garner (Eds.) Inclusive Education, World Yearbook of Education 1999. 2000 paperback edition. London, Kogan Pageの全訳である。第一版は一九九九年に刊行されたが、翌二〇〇〇年にペーパーバック版として、新たにシリーズ編者の序文および本書編者のH・ダニエルズとP・ガーナーによる長文の序文が付されて刊行された。これが本書である。
本書は、国際教育年鑑(World Yearbook of Education)の一九九九年版として刊行されたが、教育年鑑の第一巻は一九三三年に刊行された古い歴史をもつ。また、教育年鑑の刊行には、ロンドン大学教育研究所の関係者が深く関与してきたことにより、イギリスの教育学ならびに関連分野の考え方が色濃く反映されていることも、本書の特徴であろう。
教育年鑑の一巻として刊行されたことに示されているように、インクルーシブ教育は、立場を超えて現代の国際的教育運動の共通の目標となっている。それゆえインクルーシブ教育は、イギリス、アメリカ合衆国、スウェーデンなどの先進国のみならず、開発途上国においても、さらには、ユネスコなどの国連関係機関や世界銀行、OECD等の主要な政策課題になっている。しかし立場を超えて共通の目標を共有しているということは、それぞれの国の背景、資源、文脈等は同じではないから、同一の用語や表現を用いていても、各国は、統一された概念や理念を必ずしも共有していないことを示唆する。たとえば、理念や目的のレベルにおいてすら、指向性が異なるように、インクルーシブ教育理論は複雑な様相を内包している。
日本におけるインクルーシブ教育への関心は、このような国際的動向から見るとかなり偏っている。インクルーシブ教育の本質からして、インクルーシブ教育は通常教育の問題で(も)ある。しかし日本では、第一に、文教政策では特殊教育の特別支援教育への転換、すなわち障害児教育の改革という傾向が強く、インクルーシブ教育に対して初等中等教育としてどのように取り組むのか否かという政策の明確さに欠けている。第二に、通常教育の現場でのインクルーシブ教育に対する理解も関心も希薄であるばかりか、学界においても、教育学研究者のインクルーシブ教育への反応は、文部科学省の受け止め方と大差なく、障害児教育の問題としているかのようである。第三に、障害児教育関係者もまた、類似のインクルーシブ教育理解、すなわち、インクルーシブ教育論のラディカルさに対する認識不足と、障害児教育の改革に限定した部分的な理解に陥っている傾向が強い。
このような日本の現状からみて、本書はきわめて適切な内容となっている。本書は、この重大な課題解決のために教育学の再生を期待している点、そして、間接的にではあるが、日本の教育の根本的改革の必要性への示唆という点で、時宜にかなっている内容となっている。また、インクルーシブ教育が成り立っている背景と原理の提示だけではなく、ローカルな条件のもとでのインクルーシブ教育の成立可能性にも言及している(日本については第一一章で日本の長短と可能性を見事に記述している)。さらに、インクルーシブ教育が成立・展開を可能にするうえでのさまざまな背景についてのとりわけ英米等の執筆者による論文は豊かな学識の裏づけがあり、この点でも私たちが学ぶべき点は多くある。
第一部では、イギリスとアメリカの代表的なインクルージョン論者により、インクルーシブ教育と民主制社会との密接な関連が述べられている。第二部では本書で最も頁数が割かれており、インクルーシブ教育のジレンマが、制度の再編、変化、発展という観点から、インクルーシブ教育が展開しているヨーロッパの先進国、特殊教育制度が確立していてインクルーシブ教育への転換を模索している日本を含む国々、今後、インクルーシブ教育を展開しようとしている開発途上国について、それぞれ述べられている。第三部では、第一部と第二部をうけて、インクルーシブ教育が実現する過程において、理論的・実践的諸問題についての寄稿者による見解が提示されている。
本書の翻訳は、訳者たちが参加していた日本学術振興会科学研究費補助金による研究プロジェクトの一環として行われた。翻訳にあたっては、難解な箇所も多々あった。最善を尽くしたつもりであるが、思わぬ誤りがあるかもしれない。ご教示いただければ幸いである。
二〇〇六年三月
訳者を代表して 中村満紀男
目次
第1部 民主制における特殊教育の明確化(インクルーシブ教育―民主制社会における要件;教育に対する個人の権利と障害のある子ども―アメリカの政策からの教訓;インクルージョンとインクルージョンズ―インクルーシブ教育の理論と言説 ほか)
第2部 インクルーシブ教育のジレンマ(変革期にある制度;変化しつつある制度;開発期の制度)
第3部 インクルーシブ教育に関する対話(福祉国家と個人の自由;政策と実践?インクルーシブ教育と学校教育への影響;南アジア系青年と人種差別、エスニック・アイデンティティ、教育 ほか)
著者等紹介
ダニエルズ,ハリー[ダニエルズ,ハリー][Daniels,Harry]
バーミンガム大学教授(特殊教育・教育心理学)、Ph.D.
ガーナー,フィリップ[ガーナー,フィリップ][Garner,Philip]
ノッチンガム・トレント大学教授(特別な教育的ニーズ)
中村満紀男[ナカムラマキオ]
筑波大学大学院人間総合科学研究科教授。教育学博士
窪田眞二[クボタシンジ]
筑波大学大学院人間総合科学研究科教授。教育学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
kyon
-

- 和書
- 統合保育の方法論