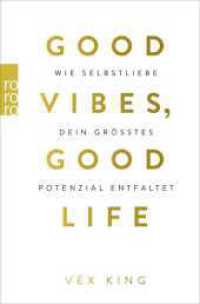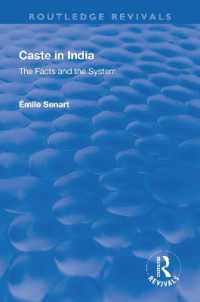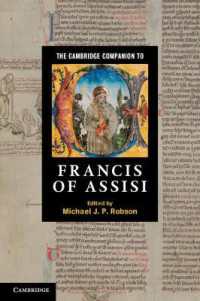出版社内容情報
ホワイトバンド効果で、世間の募金に対する関心は高まっている一方、使途や過程・しくみの透明性など、募金とNPOの関係については課題も多い。NPOにとって、「募金」は成熟した市民社会を形成し、課題解決に挑むための有効な手段となるのか?
[特集]寄附・募金を考える―日本に寄附文化を根づかせるために
●問題提起
●座談会 注目の運動の担い手が寄附・募金を語る
●論点
ホワイトバンドが提起したこと(国際問題研究家/北沢洋子)
市民力としての寄附拡大に向けて(パブリックリソースセンター事務局長/岸本幸子)
募金、ファンドレイジングの仕組み―アメリカの事例(インディアナ大学研究員/大西たまき)
●インタビュー NGOのキャンペーン(サステナ代表/マエキタミヤコ)
●コラム 韓国社会の寄附文化(宋 悟)
●寄稿
寄附文化醸成のためには、税制と制度整備が必要(国立民族学博物館教授/出口正之)
寄附市場の創出―「寄附市場創造協会」の挑戦(慶應義塾大学教授/跡田直澄)
●コラム ピーター・ドラッカーさんを偲んで(慶應義塾大学教授/金子郁容)
●オピニオン 商社の国際貢献について(伊藤忠商事(株)社長/小林栄三)
●リポート
アジア「津波」国際NGO会議(日本国際ボランティアセンター代表/熊岡路矢)
第3回国際交流・協力実践者会議を見聞して(日本経済新聞社論説委員/松本克夫)
DVへのホリスティックな取り組み
編集後記
◇本号を編集中に二人の方の訃報が届いた。お一人は、冒頭に追悼文を掲載させていただいた経営学者、ピーター・ドラッカー氏である。氏が、21世紀の社会の重要な構成要素として民間非営利組織の新たなる機能と役割を強調され、提示されていることは、NPOセクターに関わるものにとって、随分と勇気づけられ、示唆に富んだ著述は道標となった。
◇もうお一人は、本協議会の会員でもある(財)PHD協会の創設者、岩村昇氏である。1962年から18年間、ネパールの辺境の村で医療活動を行った後、アジアの地域指導者の養成に尽力された。岩村さんは「生きることは分かち合うこと、貧しきものと」「日本人は心持ちにならなければ」を説かれた。今でこそ、多文化共生が時代のキーワードとして用いられるが、岩村さんから「共に生きる」という言葉を聞いたのは20年以上前で、ずしりと心に響いた。「自分のためだけに使っていた時間、財、技能の10%を困っている人に」という呼びかけは、今回の特集の「寄附・募金を考える」に通じる理念である。お二人の訃報に接し、平和で豊かな未来をつくるために、私たちが今、為さなければならないことは何かをあらためて考えさせられた。