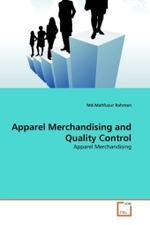出版社内容情報
英語嫌いの生徒が大半を占めるクラスで、授業の中で彼らのつまずきをどう回復させるか。本書は学力差が大きいといわれる高校の英語学習に、独自の視点から果敢に取り組んでいる3つの実践例をもとに2つのコラムも交えてわかりやすく解説する。
[巻頭言]教えと学びの交響する教室へ(竹内 常一)
はじめに(小島 昌世)
短期間で自信を持たせる読みの指導(田中 容子)
【コラム】 歌を授業に(米蒸 健一)
英語嫌いの生徒と向き合って(室井 明)
【コラム】 人と人をつなぐ──私の授業開き(室井 美稚子)
あの手この手で言語学習に挑む定時制(絹村 俊明)
[解説]実践に見る外国語教育の困難を超えるてだて(小島 昌世)
あとがき(小島 昌世)
はじめに(小島 昌世)
生徒たちは、高校入学時にはすでに英語という教科について、たくさんの教科観、イメージ、思い込みをもっています。これらのいくつかは、高校の英語授業成立の壁になります。この壁をとりはらい、新しい教科観をつくりだすことができるかどうかが、高校英語授業成立の鍵となります。
英語授業を成り立ちにくくしている、生徒たちの思い込みについて考えてみましょう。
「自分は英語はだめ」という思い込み
新しい言語を身につけるということは大変なことです。言語はさまざまな側面をもっていますが、最も重要なのは「意思伝達の道具」という側面です。道具であれば、使いこなす技能がなくてはなりません。したがって、英語という教科は、各教科の中でもとりわけ技能の修得を必要とする教科なのです。英語の習得には、繰り返しによる練習と記憶の維持が欠かせません。中学での、週あたり3時間程度の学習では無理というべきかもしれません。何らかの方法で授業以外の学習時間を確保できなかった生徒たちが、「英語はわからない」「中学で落ちこぼれた」「わたしには英語はむり」と思いこむことで、学習からひいてしまうのも無理からぬことです。高校の授ん。「聞き取るちから」「話すちから」の獲得は特別の訓練を必要としますから、意識的な指導をしなければなりません。けれども、高校生という年齢にいたった者にとっては、文字による理解や確認は、おおいに学習の助けとなります。4領域をバランスよく指導するというスタンスにたつことの方が現実的だといえます。英文の資料を読む、調べたことを英語で発表する、考えを英文のリポートにする、その間にQ and A がおこなわれるなど、ひとつの話題の学習を4領域にわたっておこなう工夫が考えられます。同じ題材を4領域にわたって学習することは、言語というものの全体像をつかむことにもなります。
実践的な英語力ということで場面シラバスにしたがった指導も導入されています。しかし、場面ごとの会話は、さしせまった必要があるときにこそ良く定着します。自分が、英語でなければ伝え合えないという場面に直面することを想定できない場合には空疎なものと感じられるでしょう。外国人を教室に招くなど、必要をつくりだす工夫もあります。また、学校がある地域の状況を考えて、可能性のある場面を、生徒と想定しあうこともあってもいいでしょう。地域の状況によっては、英語でなくスペイン語や韓国の、自分の現実の生活とかけはなれたものと感じています。英語を学習することの意味がわからなくなっています。英語だけでなく、学習することそのものの意味がつかめなくなっているのです。
原因のひとつは、かれらが受けてきた英語授業が、英語という言語で伝えられている内容を自分とかさねて考える機会になっていなかったということにあります。およそ、伝える内容をふくみもたない言語というものはありません。“Oh!”という一語にしても、それを発するある情感を伝えています。けれども、授業で、ある文法項目を教えるときにとりあげる英文の内容に、どれほどの注意がはらわれているでしょうか。プリントの練習問題には、脈絡のない英文がならんではいないでしょうか。脈絡のない英文の羅列を繰り返し提示された生徒たちは、英文は内容にこだわらなくてもいいものだと感じてしまいます。英語という言語が技能の修得の道具にすぎなくなり、「伝える道具」という本質をつかむことができず、英語で伝えようという意欲からとうざかっていきます。
世界で起こっている現代社会の問題を学習することは、英語という教科に期待される課題のひとつです。教科書にもそういうレッスンが増えていまのの技能の獲得をからませてゆくのが英語教師のしごとです。
英語Iの教科書から小説教材が減っています。そこにはある必然性がありますが、思春期の生徒のもつ感情をことばにして提示してみせるという点で、文学作品は重要な意味をもっています。自己と世界との把握をうながす授業を成立させる可能性をもった教材はどのようなものかを探り、さまざまな教材を開発することが、授業拒否をのりこえるひとつのてがかりとなります。
「生徒と先生は対立するもの」という思い込み
授業拒否と教師不信は一体のものです。生徒は漠然と、英語はたいせつだと思っています。たいせつだと思えばこそ、その力がないと評価する者を、自分に敵対する者と感じるのです。英語の学習をすることが、自分のおかれている状況を把握し、状況を変えていくちからをつけることになると実感できるような授業をすること。学習することで、自分の値打ちを発見させること。そして、教師は、生徒の側にたって共に人の値打ちを探っている者だと、行動と姿勢で示すことが、この壁をのりこえることを可能にします。生徒にとって教師は、非常に身近に存在する他者です。両者のあいだに「共にたつ者」という関係をうちた
目次
短期間で自信を持たせる読みの指導
英語嫌いの生徒と向き合って
あの手この手で言語学習に挑む定時制
解説 実践に見る外国語教育の困難を超えるてだて
著者等紹介
小島昌世[コジママサヨ]
津田塾大学学芸学部英文学科卒業。1940年生まれ。國學院大学文学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。