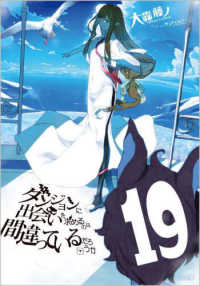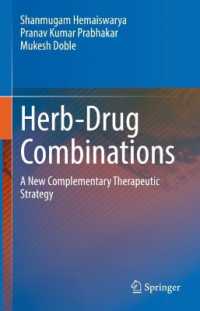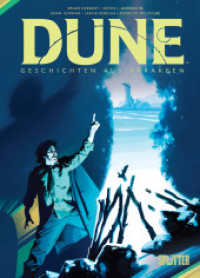出版社内容情報
靖国参拝、新しい歴史教科書問題、ナショナリズム、反日デモ…緊張する現在の日中関係はどのようにつくられたのか。そしてメディアはそれをどのように報じたのか。アジアの2つの大国のよりよい関係を目指す、相互理解のためのメディア分析。
序に代えて 本書の構成とJCCの活動について(高井潔司)
第1部 胡錦濤外交の基本路線
第1章 新時期に中国外交が直面する主な挑戦(王逸舟)
1 新時期とはなにか
2 発展への挑戦
3 主権への挑戦
4 責任への挑戦
5 日中関係
6 私の家族4世代
7 質疑回答
第2章 王逸舟教授の中国新外交論を読む(矢吹晋)
1 王逸舟教授招請の経緯
2 王論文の全体構想
3 発展への挑戦
4 主権への挑戦
5 責任への挑戦
6 日中関係について
第2部 中国のナショナリズム
第3章 民族主義と国民感情──日中比較(王 屏)
1 中国の民族主義に対する中華伝統文化の影響
2 中国民族主義の特徴とその指向性
3 日中の民族主義の現状とアジアの未来
第4章 伝統文化と民族主義(清水美和)
1 王屏論文へのコメント
2 中国「反日」の源泉
3 高級モールと物乞い
4 「民意」の噴出口
第5章 反日デモは民族主義か──いくつかの論点整理(田畑光永)
1 2005年反日デモの特徴
>第4部 未来志向の日中関係
第9章 歴史から未来へ(馮昭奎)
1 「一強一弱型」関係から「強強型」関係へ
2 「農・工型」関係から「工・工型」関係へ
3 「友好の高潮期」から「感情摩擦期」にはいる
4 「政府主導」から「民間主体」に向かう広範な交流の時代
5 日中政治関係の3つの可能性
6 日本はなぜ強硬路線に傾くのか?
7 日中関係は強強対決に進むのか?
第10章 日本外交の至上課題(村田忠禧)
1 はじめに
2 反日デモの意味するもの
3 八方塞がりの小泉外交
4 アジアの一員としての日本と中国の発展
付 録
序に代えて 本書の構成とJCCの活動について
日中コミュニケーション研究会(JCC)理事長 高井 潔司(北海道大学大学院国際広報メディア研究科教授)
中国各地で2005年春発生した「反日」デモは、投石などを受けた北京大使館や上海総領事館、日本レストランの被害の映像が、日本のテレビニュースやワイドショーで繰り返し流され、日本社会をパニックに陥れた。パニックを生じたのは、損害の大きさゆえというより、日本の社会にとって予期しないデモだったからといえよう。その結果、一部のマスコミはデモの原因を、中国側の反日教育のせいと決め付けた。この日本側の論調は、逆に中国側の反日感情を一層高め、相互不信は最高レベルに達している。それほどに日中間では近年、認識のギャップが目立っている。
他方、東アジアにおいては、グローバル時代に対応し、経済面で相互補完、相互依存が深まり、日中両国を中心にした、「東アジア共同体」の形成さえ取り沙汰されている。だが高まる相互不信は、今後の東アジアにおける日本外交の幅を狭めかねない、憂慮すべき事態ともいえよう。
筆者が理事長を務める日中コミュニケーション研究会(JCC)は、1999年の発足以来、日中逸舟氏と王屏氏)を採録し、さらにあらたに2本の論文の執筆を依頼し、計4本の論文を柱に、日本側の研究者がコメントを加えるというスタイルを取った。つまり、胡錦濤外交の基本軸を論じた王逸舟論文、中国のナショナリズムの歴史的な展開を明らかにした王屏論文、中国メディアの日本報道を分析した劉志明(りゅうしめい)論文、日中関係の現状分析から今後のあり方を説いた馮昭奎論文である。一見するとバラバラの論文のように見える。しかし、対日新思考論議まで呼び起こし、国際協調を基調とする胡錦濤政権の対日外交(王逸舟論文)が、中国の大衆の間で高まるナショナリズムの波によって揺さぶられ(王屏論文、清水コメント)、さらに昨今の大衆メディア、インターネットの報道を通して、さらに過激な対日世論へと変容していく過程(劉志明論文)を読み取ることもできる。第4部の2つの論文は、こうした中国側の動きに対応する日本外交のあり方を提言している。馮昭奎論文はそうした風潮のなかで、日中関係の重要性を説き、未来志向の日中関係を提唱している。馮氏は2000年余の日中交流を振り返りながら、現在、アジアに2つの強国が並び立つ史上初の「強強時代」を迎え、日中関係が「友好の)小平理論同様、愛国主義教育が強調されたからといって即大衆に受容されるとはいえないだろう。もちろん「反日」デモと愛国主義教育は無縁ではないだろうが、「愛国主義教育実施綱要」や「反日教育」の存在を指摘しただけでは、何の証明にもならない。またそれだけで「反日」デモが起きたなどとはいえまい。受容の構造、プロセスを明らかにする必要がある。例えば、小泉首相の靖国参拝や歴史教科書の改訂問題、一部政治家の戦争責任否定論など日本側の動きも、愛国主義教育によって教えられる日本軍国主義復活、日本の右傾化に対する中国大衆のマイナスイメージを強化させ、「反日」へと向かわせる作用を疑いなく果たしている。残念ながら、日本では、愛国主義教育=反日という単純な分析によって、「反中」「嫌中」を煽る言説が広く流布している。そうした言説がいかにも日本の「国益」を代表したかのように装っているが、実はそうした単純な言説の結果、問題への対処を誤り、日本のアジアにおける外交カードを著しく低下させ、日本外交の手足を縛る結果を招いている。
第10章の村田論文は当初、掲載を予定していなかった。しかし、「反日」の動きが決して中国側だけの原因で生まれていないこ満、不信感が「反日」を通してぶちまけられたという側面も、あのデモにはあった。4月中旬以降、中国当局が押さえ込みに乗り出したにもかかわらず、愛国団体が再三デモの継続を呼びかけ、最終的には当局の強い統制によってデモが封じ込められたことも、あのデモが「反日」に止まらない性格を持っていたことの傍証である。
もちろん一方では、中国の大衆の間に日本側の歴史認識に対する強い不満があるのは事実であるが、他方、市場経済の進展に伴い、社会の多元化、大衆化、情報化が進行し、大衆の側には、日本だけでなく中国当局に対する不満も蓄積している。しかし、政治面では、共産党の一元支配が現政権の至上課題となっており、その不満の表現は厳しく抑えられている。そのインバランスが「反日」という形で「はけ口」を見出す現象を生み出す要因となっている。第8章の拙稿は、こうした構造を解き明かそうと試みたものであるが、清水コメント、渡辺論文などと読み重ねていただくと、そうした意味合いが一層明らかになるだろう。
2005年8月10日
内容説明
靖国参拝、『新しい歴史教科書』問題、ナショナリズム、反日デモ…。緊張する現在の日中関係はどのようにつくられたのか。そしてメディアはそれをどのように報じたのか。アジアの2つの大国のよりよい関係を目指す、相互理解のためのメディア分析。
目次
第1部 胡錦涛外交の基本路線(新時期に中国外交が直面する主な挑戦;王逸舟教授の中国新外交論を読む)
第2部 中国のナショナリズム(民族主義と国民感情―日中比較;伝統文化と民族主義 ほか)
第3部 日中摩擦とメディア(日中コミュニケーションギャップと情報発信;メディアと世論、そして日中関係 ほか)
第4部 未来志向の日中関係(歴史から未来へ;日本外交の至上課題)
著者等紹介
高井潔司[タカイキヨシ]
1972年東京外国語大学中国語科卒業。同年読売新聞社入社。テヘラン特派員、上海特派員、北京支局長、論説委員を歴任。1999年4月北海道大学教授。2000年4月から現職の北海道大学大学院国際広報メディア研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。