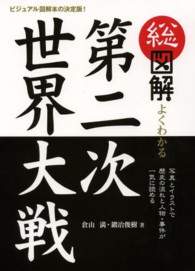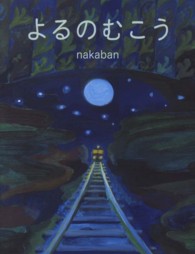出版社内容情報
今、学校現場には学力向上の特効薬かのように、少人数制とセットで習熟度別授業が強引に導入されている。子どもや親の願いに応え学力を育てるのか――実践・研究の両面から学力格差を拡大させている実態をも明らかにし教育における多様性と平等を問い直す書。
はじめに●小寺隆幸
第1章 今、教室で何が起こっているか
高まる学力と深まる学力 ――6年生算数じっくりコース 異質な学力の子どもたちのなかで学力は育つ●橋本友子
あいまいな不安・不満・幻想――親の立場から ――学校内にもち込まれる経済格差●阿部綾子
学力は向上したのか ――学力向上フロンティアスクールでの教師の実践と苦悩●中山優希
クラス解体でコミュニケーションは実現するか ――中学校英語授業実践と集団活動の再評価●柏村みね子
第2章 習熟と習熟度別授業を考える
子どもたちの学び合いを断ち切り学力格差を拡大する危険性 ――習熟度別授業の実態をふまえ、未来を見すえた議論を●小寺隆幸
習熟とは何か ――熟達化研究の視点から●松下佳代
「過重負担と能力別への移行」からの解放を ――「学力向上策」ではなく学力保障の一方法として●梅原利夫
あとがき●梅原利夫
はじめに
「先日小学校の息子の公開授業を見ました。こだまクラス30人、かがやきクラス30人、がんばりクラス10人と習熟度別でした。こだまクラスは明るい。子どもたちは楽しそうに問題づくりをしていました。かがやきクラスは割合の応用問題をやっていました。子どもたちは、ちらちらと他のクラスを見ていて親も複雑でした。がんばりクラスは親が2人参観していました。ここだけ電気の数が少ないのかなと感じるほど暗い雰囲気でした。このような子どもの暗さを生む授業はやってはいけないと思いました」
ある父親のこのつぶやきを聞いて、胸が締めつけられる思いだった。これは、例外的な事例だろうか。それとも、全国各地の学校にこのような暗さが忍び込んできているのだろうか。
日本の学校は今、急ピッチで変わりつつある。いったい、どこに向かって――。現場の教師も先が見えないまま、上からの指示・命令で動かざるを得ない状況が学校を覆っている。さまざまな改革のなかでも習熟度別授業の実施は、一歩誤れば子どもの心に傷を残し将来にまで影響する。それでも反対の声は小さい。確かに現在の学校や授業にもさまざまな問題がある。できない子が放置される授業、学力差が広家庭教師を全ての子どもにつけるのが一番良いというイメージだが、日本では一斉授業が発達しており、少人数教育に焦点を置くと逆に悪くなる」
(土居健郎、キャサリン・ルイス他『甘えと教育と日本文化』、PHP研究所、2005年)
確かに日本の教師たちは子どものさまざまな考えを引き出し、子どもたちの学び合いをとおして考える力を育ててきた。そういう学びの基本をだいじにしようという本質的な議論が欠如したまま、習熟度別授業が強制されている。この現状に一石を投じ、子どもたちにどのような学びが必要なのかを考えるきっかけにしたい、という願いで私たちはこの本を編んだ。
本書の第1章は、学校現場の実践を具体的に紹介し、問題点を明らかにするように努めた。習熟度別授業の典型的な教科である算数・数学・英語について三人の実践者に報告をしていただくとともに、親の立場からの率直な疑問を書いていただいた。
第2章では問題点の掘り下げと今後の課題について二人の編者がそれぞれの視点で考察した。併せて習熟の概念を熟達化研究の新たな知見をもとに問い直し、学校教育での水平的熟達化の意義を論じた松下佳代の論考をとおして、学力のあり方や学校教育の意味
内容説明
学力についての議論が、どんな子どもにとっても、未来の社会への希望と個人のしあわせや豊かな生き方をつなぎ、また、人と人とのつながりをつむぐものとなることを願って、このシリーズを贈ります。
目次
第1章 今、教室で何が起こっているか(高まる学力と深まる学力―6年生算数じっくりコース―異質な学力の子どもたちのなかで学力は育つ;あいまいな不安・不満・幻想―親の立場から―学校内にもち込まれる経済格差;学力は向上したのか―学力向上フロンティアスクールでの教師の実践と苦悩;クラス解体でコミュニケーションは実現するか―中学校英語授業実践と集団活動の再評価)
第2章 習熟と習熟度別授業を考える(子どもたちの学び合いを断ち切り学力格差を拡大する危険性―習熟度別授業の実態をふまえ、未来を見すえた議論を;習熟とは何か―熟達化研究の視点から;「過重負担と能力別への移行」からの解放を―「学力向上策」ではなく学力保障の一方法として)
著者等紹介
梅原利夫[ウメハラトシオ]
1947年、教育基本法施行と憲法施行のあいだに東京・新宿で生まれる。和光大学人間関係学部教授。カリキュラム論、いじめ・不登校の教育学などを担当
小寺隆幸[コデラタカユキ]
1951年生まれ。東京都多摩市立和田中学校数学科教師。数学教育協議会会員。現在のテーマは現実の問題に結びつけた数学教育の創造。チェルノブイリ子ども基金や原爆の図丸木美術館の理事として反核・平和の活動もライフワーク
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。