出版社内容情報
全身の筋肉が萎えて行き寝返りさえ打てぬ難病筋ジスに兄弟3人ともが冒された著者。兄や仲間の死を乗り越え、同じ障害をもつ人びとのために自立ホーム・難病ホスピスを作り運営してきた懸命な生の軌跡を、死が日常に隣り合う生活の中で自ら綴る感動の記録。
はじめに(澤地久枝)
第一章 聖霊の時――初めての死
第1節 聖霊との出会い
第2節 初めての死
第3節 親友との別れ
第二章 苦悩の時――筋ジス患者の悲しみ
第1節 筋ジス病棟
第2節 西病棟の運命
第三章 悲哀の時――生への挑戦
第1節 自立ホームの限界
第2節 難病ホスピスの宿命
第四章 彷徨の時――兄弟の別れ
第1節 生死をさまよう
第2節 長兄、寛之との別れ
第3節 次兄、秀人との別れ
第4節 追憶から聖霊へ
最終章 支えられて
あとがき
はじめに(澤地久枝)
筋ジストロフィー患者の山田三兄弟とはじめて会った夏の日から、三〇年近い年月がすぎた。
長男の寛之さん、次男の秀人さんはすでに彼岸の人となった。末っ子の富也さん一人が、奇跡のような五〇代を生きている。
つぎつぎに事業の計画をたて、そこへ引きこまれるたび、わたしは、富也さんは「事業魔」みたいと思っていた。「事業もいいけれど、あなたには本を書く義務がある」、としつこく言ってから、ずいぶん時間が過ぎた。寛之さんや秀人さんが語りつくせぬままに終わった筋ジス患者としての青春。富也さん自身の、闘病と一人の男性としての人生を書くべきであるとわたしは考えたのだ。
ひとつには、書くことで、行動派の彼に安静の時間を確保したいという思惑もあった。
だが、一度ならず死線を越え、その間に幾度も催促されながら、一向に原稿は書かれなかった。それでも、五年前の奇跡的「生還」が、彼の気持を少し変えたかも知れない。
いつものことながら、ある日突然、ドサっと原稿が送られてきた。富也さんの頼みごとは、いつも有無を言わせぬ形でやってくる。
わたしはしっかりと送られてきた彼の第一稿を読んだ。そして、「これる。それで「なにか書いてほしい」。一〇日間くらいのうちにと言う。
宅配便で再校ゲラが届く。徹夜して読む。苦心の結晶であると納得した。文章を書くには、才能というより体力と集中力が不可欠なのだ。富也さんはいのちのギリギリの力をふりしぼって、これをまとめた。いまでは電話にも出られない体力で、やっとここへたどりついたのだ。
筋ジスによって奪われた多くの人生についての証言。自分のためではなく、兄たちや病友たちの無念の死を書きのこす使命感に支えられて、彼は精一杯の文章を書いたのだ。
彼自身のことは、あまり具体的に書いてはいない。わたしが注文したテーマの半分がこの本にまとまり、あと半分は富也さんのこれからの仕事としてのこっている。彼がより長く生きるべく、課題がのこったことをわたしは喜びたい。
一人でも多くの読者の手にわたることを祈る。希望のない「生きるたたかい」を放棄しなかった心やさしい筋ジス患者たちを忘れてしまわないために――。
二〇〇五年七月二日
目次
第1章 聖霊の時―初めての死(聖霊との出会い;初めての死;親友との別れ)
第2章 苦悩の時―筋ジス患者の悲しみ(筋ジス病棟;西病棟の運命)
第3章 悲哀の時―生への挑戦(自立ホームの限界;難病ホスピスの宿命)
第4章 彷徨の時―兄弟の別れ(生死をさまよう;長兄、寛之との別れ;追憶から聖霊へ)
最終章 支えられて
著者等紹介
山田富也[ヤマダトミヤ]
1952年4月4日福岡県大牟田市生まれ。1968年4月宮城県にある当時の国立療養所西多賀病院に入院。1974年に退院し、ありのまま舎を創設。難病・重度障害者問題について出版・映画・講演を通して啓蒙運動を展開する。1986年、ありのまま舎は社会福祉法人として、自立ホーム、難病ホスピスを相次いで建設。啓蒙運動だけではなく難病・重度障害の人びとの自立支援を実行。仙台市より「賛辞の楯」、朝日新聞社より「朝日社会福祉賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おたきたお





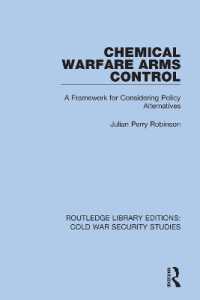
![けだまのゴンじろー 〈1〉 - まんが家ボタンつき!! [特装版コミック] コロコロコミックス (初回限定版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40994/4099430448.jpg)


