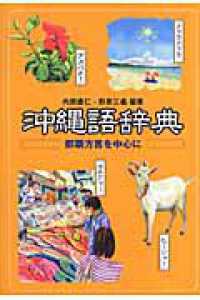出版社内容情報
認知症高齢者のキャンプ活動に取り組んできた桃山学院大学の石田易司教授と日本キャンプ協会による実践マニュアル。認知症があっても自然のなかでキャンプを楽しむための技術と知恵が満載。認知症の方々にかかわりをもつ人たちにぜひ読んでいただきたい一冊。
はじめに
1.認知症高齢者のキャンプ
認知症高齢者キャンプの参加者
1.認知症の主な原因
2.認知症の主な症状
3.基本的な接し方
4.キャンプの参加者像
キャンプというもの
1.自然の中の簡便な暮らしということ
2.プログラムがあること
3.社会的なシステムの中で
認知症高齢者キャンプの目的
1.暮らしをいきいきと
2.お年寄りの尊厳や人権を守る
3.若者を育てる
4.その他
認知症高齢者キャンプの実際
1.運営主体
2.キャンプ場
3.態勢
4.経費
5.プログラム
6.介護
7.このキャンプの特徴
2.キャンプの運営
キャンプの運営
1.マンツーマンと小グループ
2.参加者と参加費
3.アセスメント
4.事前のスタッフ研修
5.ボランティアのシステム
6.運営主体
7.役割分担
8.ミーティング・レコードと評価
3.キャンプの生活
キャンプ場決定の条件
1.目的と参加者
2.移動時間
3.ハード
4.経費
5.プログラム
2.作る楽しさを共有する
3.簡便さを尊重
4.参加する喜び
4.キャンプのプログラム
さまざまなプログラム活動
1.プログラムの基本的な考え方
2.プログラムの組み方の基本
3.プログラム決定の条件
4.具体的なプログラム活動
5.これからの認知症高齢者キャンプ
これからのキャンプの課題
1.まちづくり
2.認知症の理解と啓発
3.効果測定と治療
4.若者の育成
5.キャンプ場づくり
6.ユニバーサルキャンプ
おわりに
はじめに
私たちが認知症の高齢者のキャンプを1993年に世界で初めて実施してから10数年がたった。1997年、ロシアのサンクトペテルブルグで開催された第3回世界キャンプ会議で、大阪体育大学永吉宏英教授がこの事例を発表した時に、世界のキャンプ指導者が一様に驚きの声を上げた。世界の国々によってキャンプに対する取り組み方の違いはある。世界の趨勢はキャンプの対象は青少年中心だし、高齢化率の急上昇、認知症高齢者の増加、一方で介護のための社会資源の未整備という状況を抱えているのは日本だけということもある。また、大人に対して集団での活動ということに抵抗をもつ国もある。そういった日本の特殊事情はあるにしろ、世界で最初ということは、もし私たちが不勉強でなければ、間違いのないことだろう。そして、今後他の国で広がっていくかどうかもわからない。
しかし、日本の現状では、この活動は今後もとても大切なものであり、ますます広がっていかなければならない活動だろう。認知症などの病気や障害をもった高齢者の暮らしがもっと豊かにならなければならないし、福祉施設での暮らしがもっと個人を尊重した自由なものにならなければならないと思うからだ。高齢になるとい術をもっている。そのことを活用して、人生を豊かに暮らしたいと願っている。だから、「認知症高齢者のキャンプ」なのだ。
新しい社会福祉法の下で、各地でつくられている福祉の条例や実践のための計画の中で「福祉文化」という言葉がよく使われている。最低限度の生活を保障するという福祉の暗いイメージから脱却して、明るい豊かな福祉文化を形成するために、高齢者が自然の中でいきいき活動している姿は悪くない。そのためにこの本がたくさんの人に読まれることを願っている。
日本キャンプ協会専務理事
石田易司(桃山学院大学)
目次
1 認知症高齢者のキャンプ(認知症高齢者キャンプの参加者;キャンプというもの;認知症高齢者キャンプの目的;認知症高齢者キャンプの実際)
2 キャンプの運営(マンツーマンと小グループ;参加者と参加費 ほか)
3 キャンプの生活(キャンプ場決定の条件;キャンプ場ガイド;コミュニケーション(かかわり方の基本)
安全
食事とレシピ)
4 キャンプのプログラム(さまざまなプログラム活動)
5 これからの認知症高齢者キャンプ(これからのキャンプの課題)
著者等紹介
石田易司[イシダヤスノリ]
1948年、京都府生まれ。京都府立大学文家政学部文学科卒業。京都府立木津高校教諭、朝日新聞社を経て、桃山学院大学社会学部社会福祉学科教授(グループワーク、レクリエーション)。日本キャンプ協会専務理事、NPO法人キャンピズ代表、大阪市立いきいきエイジングセンター館長など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
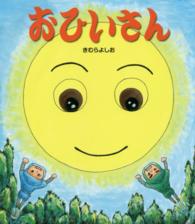
- 和書
- おひいさん