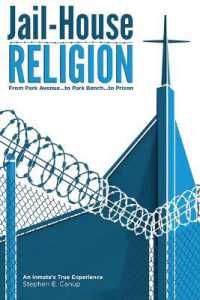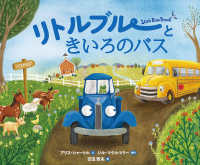出版社内容情報
社会福祉士受験資格を得るために必要な実習について平易に解説。実習先の選び方、実習記録のポイント、利用者との接し方などをQ&A方式で答える第1部と、児童、高齢者など領域ごとの機関についての概要と実習プログラムを紹介する第2部で構成されている。
第1部 実習入門Q&A編――基本をおさえる
第1章 実習の仕組みと具体的な準備
1 実習と福祉職
2 実習の目的・枠組み・位置づけ
3 実習のかたち
4 実習の流れ
5 実習計画と事前学習
6 実習前の不安とその対処
7 実習と健康
8 実習前に少し気になっていること
第2章 実習から何を学ぶのか
1 実習中の心構えと姿勢
2 利用者からの学び
3 実習記録とスーパービジョン
4 事例検討からの学び
5 福祉従事者としての適性
第3章 実習後に重要なこと
1 振り返りの位置づけ
2 実習報告書と実習報告会
3 評価
4 実習の終わりに
第2部 実習実践編――実習先への理解を深め、実習の全体像を把握する
福祉事務所の概要
社会福祉協議会の概要
児童相談所の概要
児童福祉施設の概要
身体障害者福祉施設の概要
知的障害者福祉施設の概要
老人福祉施設の概要
はじめに
淑徳大学として、本格的に社会福祉実習教育に着手したのは、1997年(平成9年)からである。そして1998年(平成10年)には、淑徳大学独自の体制として「淑徳大学社会福祉実習指導センター」を立ち上げ、実習指導センターを中心として、社会福祉現場実習指導体制の整備・充実をはかってきた。
あれから7年余、実習指導センターも2度の引越しを経て、いまだに機能も統合と分化の道を歩んでいる。
この長い月日のなかで、積み上げてきたことも少なくない。実習指導センターや実習に携わる教員のなかで、『淑徳大学版・実習教育テキスト』を出版したいという思いが強くなってきた。
その主要な理由は、淑徳大学としての実習教育のスタイルが確立されてきたことである。現在、「社会福祉援助技術現場実習」が「社会福祉援助技術現場実習指導」と「社会福祉援助技術現場実習」とに分かれ、なおかつ「社会福祉援助技術演習」の科目も現場実習と関連させながら行うことが必要とされている。淑徳大学の場合、2年次生から「社会福祉士コース」として、300名前後の学生が社会福祉士資格を取得するべく、学習を始めるが、それらの科目を有機的に結びつけ、なおかつ、していただいた。実習生が、実習に出るにあたって、「不安に感じていること」「具体的な準備」には、大いに参考となるはずである。今回、掲載した実習先の種別は20種類であるが、今後、実習先の種別が増えれば、それらを継ぎ足していかなければならない。できるだけ数多くの種別から実習先を選択できるというのは、学生の立場からすれば、必然的に求められているところであると考えている。(後略)
目次
第1部 実習入門Q&A編―基本をおさえる(実習の仕組みと具体的な準備;実習から何を学ぶのか;実習後に重要なこと)
第2部 実習実践編―実習先への理解を深め、実習の全体像を把握する(福祉事務所の概要;社会福祉協議会の概要;児童相談所の概要;児童福祉施設の概要;身体障害者福祉施設の概要 ほか)
著者等紹介
小木曽宏[オギソヒロシ]
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科助教授
柏木美和子[カシワギミワコ]
淑徳大学社会福祉実習指導センター講師
宮本秀樹[ミヤモトヒデキ]
淑徳大学社会福祉実習指導センター講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
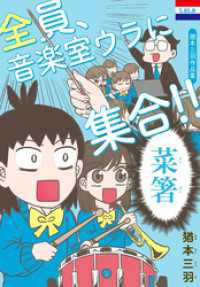
- 電子書籍
- 猶本三羽作品集「全員、音楽室ウラに集合…
-
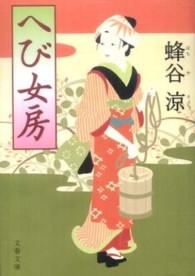
- 和書
- へび女房 文春文庫