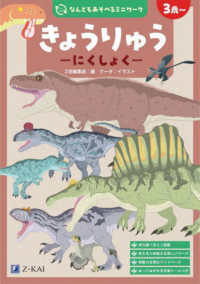出版社内容情報
コソボ、ルワンダ、東ティモール…紛争の絶えない現代に私たちは平和のために何ができるのか。選挙監視、除隊兵士支援などの活動に携わる執筆者陣が「平和構築」の概念・理論を実証的な事例を用いて紹介。紛争予防から復興支援までを見据えた入門書。
まえがき
第1部
第1章 平和構築(Peace Building)とは何か───政府、市民社会組織の役割そしてインターバンドの活動(首藤信彦)
1 冷戦後世界に蔓延する地域紛争と国家観の変容
2 予防概念の登場
3 人間の安全保障概念の登場
4 PCPB(紛争後の平和構築)から民主化支援へ
5 市民社会に突きつけられる9.11テロ後の現実と新しい課題
第2章 紛争分析・解決手法と市民参加型の平和構築の展望───開発とガバナンスの構築(山田 満)
はじめに
1 紛争を理解するための分析枠組みと解決手法
2 平和構築における「開発」の位置づけ
3 多層的アイデンティティ下の市民が参加する平和構築のあり方
おわりに
第3章 平和構築と制度構築───主に法制度構築の観点から(小川秀樹)
はじめに
1 人間の安全保障論の登場
2 コソボ紛争の事例研究
3 紛争と制度構築
4 法制度構築の今
5 日本が法制度構築に貢献できる理由
おわりに
第4章 平和維持と平和構築の接点───平和維持の多様な形態と平和構築への貢献(上杉勇司)
はじめに
1 国連PKO
2 人道的介入
3 DDRと選挙
4 カンボジアにおけるDDR
5 NGOによる除隊兵士支援
おわりに 除隊兵士支援における留意点
コラム カンボジアDDRプロジェクト事始め───風と光の原野で元兵士を支援(渡辺和雄)
第8章 東ティモールの教育開発と公用語問題───平和構築の視点から(田平由希子)
はじめに
1 公用語と公教育の関係
2 東ティモールの教育の歴史
3 国連統治下の教育の再建
4 公用語と現実の言語使用の乖離
5 公用語政策への国際支援の影響
おわりに
コラム 子どもの笑顔で知る平和───初めての選挙監視活動体験から得た平和構築の視点(玉木智宏)
第9章 平和構築と国民和解───虐殺後のルワンダの事例から(小峯茂嗣)
はじめに 冷戦の終結とアフリカの地域紛争
1 ルワンダの虐殺
2 虐殺後の国民和解政策
3 ガチャチャ
4 地域での共存に向けて
おわりに 9.11後の世界とアフリカの平和構築
コラム 国連PKO活動と国連ボランティア───シエラレオーネ選挙支援国連ボランティア(安藤秀行)
あとがき
索引
まえがき
最近「平和構築」という言葉が頻繁にメディアに登場するようになった。しかし他方で、「平和構築」の中身は論者によってかなり幅があるのも事実だ。国連が実施する一連の平和活動(予防外交、平和創設、平和維持)の一環として捉える考えもあるが、最近では貧困の除去など紛争(再発)の芽を摘みとる予防までがその範囲に含まれるようになった。
本著は目次をみてもらえば一目瞭然であるが、「平和構築」を広義に捉えた構成内容になっている。第1部では、第1章で平和構築の包括的な視点を、第2章で開発とガバナンスの構築を、第3章で法整備制度の構築を、第4章で平和維持との関係を、第5章で小型武器の問題をそれぞれ扱い、平和構築の全体像を理解してもらう構成になっている。
また、第2部では平和構築の各論、あるいは実証的側面からなる内容構成になっている。第6章ではメコン地域開発を通じた地域の信頼醸成の視角から、第7章は紛争後平和構築の重要な課題になっているDDR問題、第8章は平和構築の途上にある東ティモールの言語・教育政策の問題、第9章には未曾有の民族浄化を経験したルワンダの国民和解の問題をそれぞれ扱っている。さらに、本著では平和構築
目次
第1章 平和構築(Peace Building)とは何か―政府、市民社会組織の役割そしてインターバンドの活動
第2章 紛争分析・解決手法と市民参加型の平和構築の展望―開発とガバナンスの構築
第3章 平和構築と制度構築―主に法制度構築の観点から
第4章 平和維持と平和構築の接点―平和維持の多様な形態と平和構築への貢献
第5章 小型武器と平和構築―武力紛争・市民社会・多国間主義
第6章 平和構築と地域協力―カンボジア和平後のメコン地域開発の経験
第7章 平和構築とDDR―市民による除隊兵士支援のあり方について
第8章 東ティモールの教育開発と公用語問題―平和構築の視点から
第9章 平和構築と国民和解―虐殺後のルワンダの事例から
著者等紹介
山田満[ヤマダミツル]
1955年北海道生まれ。大学卒業後2年間就職し、アメリカのオハイオ大学大学院東南アジア研究科に留学(M.A.取得)。帰国後、神奈川県立高校教員を10年間務める。その間、第3世界ショップのボランティアスタッフなどの市民運動に従事する。80年代に高校教員として開発教育を実践し、定時制高校への転勤を契機に東京都立大学大学院博士課程に入り、政治学を研究する。95年から大学教員へ。九州国際大学、和歌山大学、東ティモール国立大学客員研究員を経て2003年から埼玉大学教養学部教授。政治学博士(神戸大学)。03年12月よりインターバンド代表に就く。専攻は、国際関係論、国際協力論、東南アジア政治社会論
小川秀樹[オガワヒデキ]
1956年岡山県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ベルギー政府給費生としてルーヴァン大学国際法研究所に留学、横浜国立大学大学院博士後期課程修了。国際経済法学博士。国連ESCAP(在タイ、外務省ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー〔JPO〕)、イスラエル大使館専門調査員、JICA企画調査員・準客員研究員、外務省NGO専門調査員(インターバンド所属)などを経て山口県立大学助教授。専攻は国際関係論、開発協力論、国際経済法
野本啓介[ノモトケイスケ]
1965年東京都生まれ。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。(株)日本興業銀行に5年間勤務ののち、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。在ホーチミン日本国総領事館専門調査員、国際協力銀行(JBIC)開発金融研究所専門調査員を経て、2002年より北星学園大学経済学部専任講師。専攻は、政治学、国際政治、日本外交、国際協力・開発援助政策。インターバンド理事・運営委員、国連大学グローバルセミナー北海道セッションプログラム委員、JICA北海道国際センター講師(日本の政治・行政)なども務める。カンボジアおよびインドネシアで国際選挙監視活動に参加
上杉勇司[ウエスギユウジ]
1970年静岡県生まれ。国際基督教大学で学士号、アメリカのジョージメイソン大学紛争分析解決研究所で修士号、イギリスのケント大学で国際紛争分析学Ph.D.を取得。専攻は紛争解決学、安全保障論。財団法人平和・安全保障研究所、財団法人南西地域産業活性化センターを経て、特定非営利活動法人沖縄平和協力センター事務局長兼主任研究員。琉球大学で非常勤講師も務める。この間、カンボジア、東ティモール、インドネシアで国際選挙監視要員として勤務した経験も持つ。著書の『変わりゆく国連PKOと紛争解決―平和創造と平和構築をつなぐ』(明石書店、2004年)は平成16年度国際安全保障学会最優秀出版奨励賞(加藤賞)を受賞。秋野豊ユーラシア基金の第2回ユーラシア紛争調査研究プロジェクト(秋野豊賞)を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。