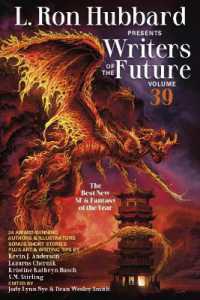出版社内容情報
IBA(国際法曹協会)調査団の調査によって、日本の刑事訴訟手続きにおける取調べの異常さが明らかにされた。裁判員制度の導入に向けて、録画・録音による取調べの記録(=可視化)の必要性を訴え、公正で透明な司法のあり方を提言する。
はじめに
第1章 なぜ取調べの可視化が必要なのか
日本における取調べの可視化に関する概観
日本における取調べの実態
取調べ受忍義務
なぜ日本の弁護士は、現時点で立会いに先行して録画・録音を求めているのか?
取調べ録画・録音反対論とその批判について
取調べの可視化に関する政府の見解
最高検察庁の見解
内閣司法制度改革推進本部の見解
警察庁の見解
法務省の見解
取調べ録音・録画の導入に関する質問主意書と小泉総理大臣の答弁書
司法制度改革審議会の見解
日本弁護士連合会の見解
被疑者取調べ全過程の録画・録音による取調べ可視化を求める決議
「取調べの可視化」についての意見書
取調べ過程の透明化を(談話)
第2章 IBA調査団による調査と報告
IBA調査と日本国内の反響
事前準備
調査団との打ち合わせ
事件関係者との面談調査
刑事法学者との懇談
関係機関からの聴取
記者会見
現地調査
IBA調査報告書の意義
裁判員制度の実施と取調べの可視化の必要性
IBA報告書「日本事件
事例8 リクルート事件
事例9 パキスタン人放火事件
事例10 草加事件
諸外国における取調べ可視化の実情
報告1 イギリス
報告2 オーストラリア
報告3 ドイツ
報告4 韓国
報告5 台湾
はじめに
二〇〇四年五月の通常国会で、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立したことは、わが国の刑事裁判の歴史において、まことに画期的な出来事でした。
刑事訴訟手続きを法曹三者の専門家だけに委ねるのではなく、国民が刑事裁判の審理と評決に参加する制度が実現することによって、これまでの刑事訴訟手続きは根本的に改められることとなります。
その中でも最も重要なことのひとつは、捜査過程を裁判手続きの中で検証することができる制度作りが求められていることです。
これまで、いくつかの死刑確定事件について再審が開始されて無罪となるなど、さまざまな誤判事例がありましたが、その中の多くは、被疑者・被告人が、捜査官の強要や誘導によって虚偽の自白をしたものであったとされています。
捜査段階の取調べにおいて作成された供述調書が任意に作成されたものであるかどうか、その内容が供述した通りの事実を記載したものであるか否かが争点となり、取調べ状況がいかなるものであったかをめぐって、多くの証人尋問をなさざるをえないことが、刑事裁判の審理の長期化をもたらす一因となっています。にもかかわらず、結局密室での取調べの実情につい言しました。
本書は、IBAの調査内容と提言を整理して、さらにいくつかの参考となる資料や報告書をまとめたものであり、本書の刊行は、裁判員制度の実施を前にして、まことに意義深いものがあると確信しております。
二〇〇四年九月
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
内容説明
IBA(国際法曹協会)は、二〇〇三年にわが国の取調べ状況を調査し、その結果を二〇〇四年一月に報告書としてまとめ、取調べの録画・録音が必要であると日本政府に提言しました。本書は、IBAの調査内容と提言を整理して、さらにいくつかの参考となる資料や報告書をまとめたものである。
目次
第1章 なぜ取調べの可視化が必要なのか(日本における取調べの可視化に関する概観;取調べの可視化に関する政府の見解 ほか)
第2章 IBA調査団による調査と報告(IBA調査と日本国内の反響;IBA報告書「日本における被疑者の取調べ―電磁的記録の導入」)
第3章 取調べの可視化に関する専門者会議(ファリー・ナリマン氏による基調講演;ニコラス・カウデリー氏のコメント ほか)
第4章 資料編(事例研究;諸外国における取調べ可視化の実情)
-

- 和書
- どうぶつえんのクリスマス