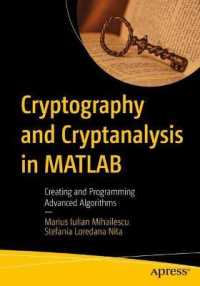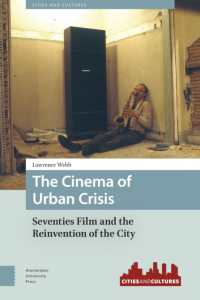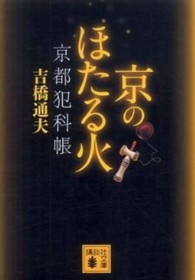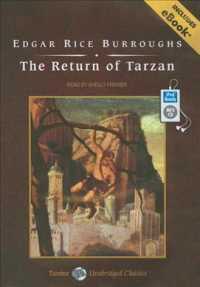出版社内容情報
なぜ、アメリカのマイノリティの学生たちは学校の教師になりたがらないのか? 代表的なマイノリティ集団(アフリカ系、ラテン系、アジア系、先住民族系)の教育関係者116人へのインタビューを通し、教師不足を引き起こす原因を様々な角度から分析する。
まえがき(ジョン・U・オグブ)
第1章 問題と研究
第2章 アフリカ系アメリカ人の教師
第3章 ラティーノの教師
第4章 ネイティブ・アメリカンの教師
第5章 アジア系アメリカ人の教師
第6章 人種対応教育について
第7章 教師教育の改革
第8章 マイノリティ学生を教職に就かせるための提案
第9章 解釈
訳者あとがき
参考文献
本書は、なぜマイノリティの学生は教師にならないのかというテーマを掲げ、その背後にある要因の解明を目的とし、その解明に基づきアメリカの教師教育の改革についての提言を行ったものである。本書は、マイノリティの学生が教師にならない「社会的・構造的障害」的説明を超え、「社会文化的要因」である「地域の力」や「教職へのイメージ」に焦点をあてるというユニークな議論を展開している。一般的に言われている「社会的・構造的障害」的説明では、アフリカ系アメリカ人、ネイティブ・アメリカン、ラティーノについての教師不足の説明としては有効であるようだが、アジア系アメリカ人についての説明としてはまったく当てはまらない。その「社会的・構造的障害」的説明ではない説明を追求するために、それぞれのマイノリティ・グループの歴史・社会・文化的背景の理解を前提として、教育に従事するマイノリティの人たちの考え方を聞き取る方法によって、それぞれのマイノリティが個別に持つ要因とすべてのマイノリティに共通する要因について、当事者の「生の声」に言及しながら、彼らの説明を分析する「社会文化的要因」の重要性を指摘している。読者は、それぞれマイノリティの教師の一人一人のる専門職主義の概念を発展させることができる」と提言し、アメリカ的な専門職主義を変革すべきであると主張している。そして、最後に、アメリカ社会の価値観としてある、教師に対する評価の低さを批判し、アメリカ社会における教師の復権、役割の重要さを訴えて、本書の結論としている。読者は、その結論にいたるまでの様々な議論の中に、ゴードン博士のマイノリティに対する共感と教師に対する期待の大きさを読み取るであろう。
日本の読者にとっての本書の別の意義は、公民権運動以降のアメリカの学校で何が起こっているかという点を指摘したところにもある。日本のアメリカ研究者が人種民族問題を取り扱うとき、人種差別撤廃の契機になった公民権運動の歴史的意味などを中心に議論することが多いが、公民権運動がもたらした学校における人種統合の結果として、マイノリティ教師の離職が増えたり、就職が困難になったという点などの功罪については、あまり取り扱ってこなかった。本書は、公民権運動の否定的側面にも言及している。(「訳者あとがき」より抜粋)
内容説明
本書は、教職へのマイノリティの参加を増加させるという重要な問題を取り扱っている。著者は、マイノリティが教師になる決断をすることに潜在的に影響を与える地域の力についての比較研究を通して、この問題を考察している。地域の力とはマイノリティの地域、集団の成員が持っている教師や教職についての考えやイメージのことである。
目次
第1章 問題と研究
第2章 アフリカ系アメリカ人の教師
第3章 ラティーノの教師
第4章 ネイティブ・アメリカンの教師
第5章 アジア系アメリカ人の教師
第6章 人種対応教育について
第7章 教師教育の改革
第8章 マイノリティ学生を教職に就かせるための提案
第9章 解釈
著者等紹介
ゴードン,ジューン・A.[ゴードン,ジューンA.][Gordon,June A.]
英国出身。アメリカ・ワシントン大学で博士号(Ph.D.教育に関するリーダーシップと政策研究)取得。現在、カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校教育学部準教授
塚田守[ツカダマモル]
三重県出身。広島大学大学院地域研究科(アメリカ研究専攻)で修士号(国際学修士)取得後、ハワイ大学大学院社会学研究科で博士号(Ph.D.社会学)取得。現在、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 徐福伝説の謎