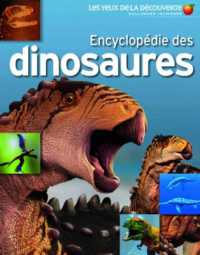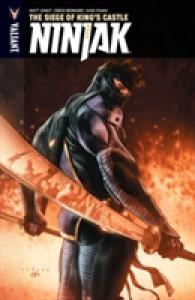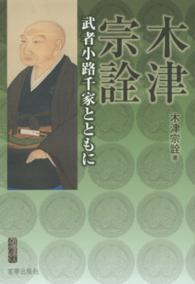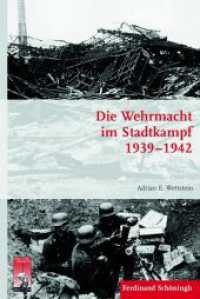出版社内容情報
人間中心の過去の歴史学をはなれ、人も生体の一部としてとらえ直す環境史の試み。歴史学と生態学とを結びつけ、新しい視点を探求する。
謝 辞
第1章 イントロダクション――歴史と生態学
環境史
生命共同体
共同体の生態学と歴史
エコロジカル・プロセス
第2章 原始の調和
セレンゲティ――人間と他の生物との関係
オーストラリア・カカドュ――原始の伝統
アリゾナ州のホピ族――土地の魂のなかにある農業
結論
第3章 文化と自然の大いなる離婚
ウルクの城壁――ギルガメシュと都市の起源
ナイル川渓谷――古代エジプトと持続可能性
ティカル――古代マヤ文化の崩壊
結論
第4章 思想と想像力
アテネ――思想と実践
西安――中国の環境問題と解決策
ローマ――環境からみた衰亡の理由
結論
第5章 中 世
フィレンツェとヨーロッパの情景――成長を阻止したもの
タヒチ、ハワイ、ニュージーランド――島の生態系に及ぼしたポリネシア人の影響力
クスコ――インカ帝国における環境保護
結論
第6章 バイオスフィアの変容
テノチティトラン――ヨーロッパの生物による侵略
ロンドン――工業化時代の都市、国、帝国
ガラパゴス諸島――ダーウィンの進化論
訳者あとがき
本書はAn Environmental History of the World: Humankind's Changing Role in the Community of Lifeの全訳である。著者のドナルド・ヒューズはUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で生物学の学士号、ボストン大学で神学の学士号、そして同じくボストン大学で歴史学の博士号を取得した学際的な研究者で、現在はデンヴァー大学(コロラド州)の歴史学教授である。専門領域は古代ギリシア、ローマ、エジプトの歴史であるが、地中海や太平洋諸島に、そして「聖なる森」にも関心を持っており、ドイツ語、ギリシア語、スペイン語、フランス語、ロシア語など多くの言語にも堪能だという。環境史を書くにはまさに適任者と言えよう。
本書の意図については著者が「イントロダクション」で詳しく説明しているが、環境史というのは歴史学の新しいテーマの一つとされている。それは環境の変化を単に歴史的に跡づけるのではなく、歴史学と生態学を結びつけることによって新しい視点を発見するインターディシプリナリーな学問である。著者はさまざまな地域、さまざまな文化をケーススタディとして提示しながら(実際に著者はイラクを除いてすべての地域を自分の足で歩き、眼で見また、ヨーロッパ人によるアメリカ大陸の征服も生物相による侵略が武器による侵略以上に破壊的な結果をもたらしたことを明らかにしている。このように生態学の視点を入れることで、わたしたちの歴史に対する見方はより多角的になり、豊かなものとなる。
環境破壊や生態系の危機については今では多くの人が知っているし、環境という言葉はありふれた用語になった。しかし、ここに来るまでには長い年月と自然環境の異変に気づき警鐘を鳴らすパイオニアが必要であった。たとえばレイチェル・カーソンは四〇年以上も前に農薬による環境汚染を憂慮して『沈黙の春』を書いていたし、日本でも石牟礼道子が水銀に汚染された水俣の海のことを『苦海浄土』に書いたのは六〇年代の終わりであった。しかしわたしたちはそれらの警告を深刻に受けとめなかった。著者が指摘するように、わたしたちは生態系を歴史を動かす重要な要素とは見ず、「背景」としてしか捉えてこなかった。
環境破壊や生態系の危機が広く知られるようになった今日でも、わたしたちの関心は環境保護よりも経済発展に向かいやすい。ましてや、地球全体の生態系の状態に想像力を働かせることは難しい。
生態系を守るためには地球全できる国にしようとする動きが出始めている。いずれの場合も、生態系への配慮はほとんど見られない。
そうやって手を拱いている間にも環境破壊は確実に進行している。つい最近の新聞にもマングローブの森がこの一〇〇年間にその面積を半減しているという記事が載った。インドやフィリピンでは約八〇パーセントも減少しているという。森を喪失させた原因の一つは枯葉剤の使用であるが、より大きな原因はエビの養殖場を作るために、あるいはエネルギー資源や製紙の原料として使うために森の木が大量に伐採されたことにある。わたしたちが日常的に使っている紙や備長炭もこれらの森の産物である。つまり、わたしたちの生活を快適にするために森が失われているということだ。森の喪失は生態系の破壊でもある。マングローブの森とともに数え切れないほどの動植物の種が絶滅してしまった。しかも、マングローブの森は一例に過ぎない。本書で詳しく述べられているように、オゾン層の破壊、土壌の浸食、湖沼の汚染、放射性物質の拡散などの事態もまた同時に進んでいる。わたしたちは快適な生活を手に入れる営みを文明と称して、自然環境を破壊してきたのだ。
希望はないのだろうか。そんなことはない
目次
第1章 イントロダクション―歴史と生態学
第2章 原始の調和
第3章 文化と自然の大いなる離婚
第4章 思想と想像力
第5章 中世
第6章 バイオスフィアの変容
第7章 開発と保護
第8章 現代の環境問題
第9章 現在そして未来
第10章の全体の結論
著者等紹介
奥田暁子[オクダアキコ]
大妻女子大学、恵泉女学園大学講師
あべのぞみ[アベノゾミ]
明治大学農学部卒、北海道大学大学院公法研究科修了
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。