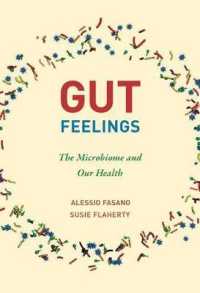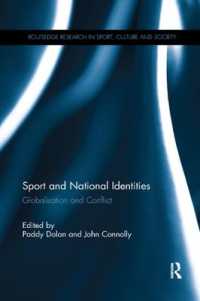出版社内容情報
ベトナム戦争終結から30年を迎え、その戦後から現在に至る変化は著しいベトナム。歴史と風土を踏まえて、各分野の専門家40人がその変化を政治、経済、社会、文化について、グローバル化と民族文化、法治国家化と民主化などの視点を交え多面的に描きだす。
1 「ベトナム」の成り立ち
第1章 「ベトナム」という名称――国号の変遷と「ベトナム(越南)」
第2章 ベトナム人の由来――建国神話と銅鼓、そしてベトナム考古学
第3章 北属南進の歴史――圧倒的な存在としての中国・フロンティアとしての中・南部
第4章 フランスによる植民地支配――その遺産と負債
第5章 ベトナム民族運動――勤王運動から独立まで
第6章 ベトナム戦争――二つのベトナム
第7章 ベトナムと周辺諸国との国境問題――中国、ラオス、カンボジアとの歴史的つながり
第8章 多民族国家――54の民族
第9章 越僑――在外ベトナム人との関係
第10章 ベトナム語と「クオックグー」――公用語としてのベトナム語
2 大地と水、ムラとマチ
第11章 山と平野、水と土――二大デルタの自然と農業
第12章 北部平野集落の成り立ち――過密な人口を支える輪中地帯の形成
第13章 「ムラとムラ人」――はたして「農民」なのか「商売人」なのか?
第14章 メコンデルタ開拓村――フロンティアの終焉
第15章 盆地の生活――ターイ族の暮らし、民族雑居
第16章 ベトナム人と海――海が苦手な北部の人、得意な中部の人
第17章章 教育――教育の「ドイモイ」は始まったか
第31章 社会悪――売買春・エイズ・麻薬
4 グローバル化する文化と「民族文化」
第32章 マスコミと情報化――情報量の増大と情報の規制
第33章 「宗教」と「信仰」――公認されている宗教と非公認の宗教
第34章 ベトナムの民間宗教――聖母道
第35章 冠婚葬祭――復活する人々の行事
第36章 音楽・演劇――伝統芸能からVーPOPまで
第37章 文化遺産と美術品――遺産の保持と新たな創造
第38章 現代文学――戦争文学からポスト戦争文学へ
第39章 映像――プロパガンダから娯楽へ
第40章 ベトナム料理――北・中・南部の豊かな味
5 ドイモイ下における政治の諸相
第41章 戦時体制からドイモイへ――ポスト冷戦期の社会主義志向路線
第42章 ベトナム共産党――その支配の「正統性」
第43章 国家機関――ベトナム的社会主義的法治国家
第44章 ホーチミン思想――イデオロギーかシンボルか
第45章 軍隊と公安――その変容と本来の姿
第46章 大衆団体――現在の祖国戦線とその姿
第47章 国民統合と開発――中部高原の少数民族運動
第48章 中央と地方――地方の「自治」と
はじめに
「エリア・スタディーズ」のベトナム版の企画が動き出してまもなくの二〇〇三年三月二〇日、アメリカはイラク戦争に踏み切った。それから一年余り経った現在、泥沼化するアメリカのイラク占領統治に対し、世界はベトナム戦争の再来だと指摘し、ベトナム戦争の教訓を思い起こし始めた。力による制圧は決して地域の人々を幸せにはしないことが改めて噛みしめられるようになっている。近年「普通の国」化しつつあったベトナムは、思わぬところからまた特別な存在「記憶の国」として脚光をあびようとしているかのようである。ただ、「記憶の国」の栄光は、戦争体験の悲惨さと背中合わせであるが。
ひるがえって今から二九年前の一九七五年、ベトナムはアメリカとの戦争に勝利し、民族解放闘争の「英雄」として世界史上に躍り出た。貧しい小国ベトナムが大国アメリカを打ち破ったことは驚きをもって受け止められ、それによってベトナム近現代史の歩みを反植民地主義的ナショナリズムや「革命のポリティックス」のプリズムを通して見る傾向が強められた。そこで捉えられたベトナム人像は、あまりに政治的・軍事的な人間像に偏っており、ベトナム人を「英雄」的に祭り上げた見方であった。じみの「近代化、工業化」が前面に押し出されるようになった。その意味でベトナムはあたりまえの途上国となり、「普通の国」になった。ベトナム戦争期のベトナムが外国人ジャーナリストにとっての「花形の地」であったとすれば、九〇年代から二一世紀初頭のベトナムは先進国の開発援助専門家にとっての「花形の地」となったのである。
本書では、「普通の国」であるベトナムを多面的に捉え、「等身大のベトナム」の人々を描くことに腐心した。ドイモイは、ベトナム人だけでなく、外国人の研究者やジャーナリストにとっても、大きな変化をもたらした。それまで主に共産党機関誌や政策をまとめた研究書などによってしか情報を得られず、フィールドワークもままならない、いわば情報飢餓的状態におかれていたが、一九九〇年代に入るとベトナムに長期滞在して現地調査することが容易になり、今までとは比較にならないくらい素顔のベトナム人に触れることが可能となった。本書の特色は、このような留学やプロジェクト実施などで現地での生活や実務を豊富に経験してきた研究者・ジャーナリスト・政府系職員・NGO関係者などによって多彩な執筆陣を構成していることである。本書を通して、一枚岩ではな流・経済関係など日本との関係はますます緊密になってきている。それだけに「等身大のベトナム」や「普通の国」ベトナムを捉える、腰のすわった深みのあるベトナム像が求められるようになってきているといえる。
本書は六部構成になっている。1はベトナムという国の枠組みが歴史的・空間的・人間集団的・文化的にどのように形成されてきているのかを検討している。2では現代ベトナム人が暮らす地理的・生態的環境について述べられ、3ではドイモイによって生じた社会・生活の変容について扱われている。4では戦時期の文化のありようから脱してグローバル化と「社会化(民営化)」が進む文化の状況とそれに対抗・補完するかたちで「民族文化」が提唱され重要視されるようになっている文化状況が描かれている。5では「法治国家化」や「民主化」など、ドイモイ下における社会主義体制の政治的変化を追っており、6では国際統合圧力がかかる状況下の「社会主義市場経済」の現状とその課題について説明されている。(後略)
内容説明
本書では、「普通の国」であるベトナムを多面的に捉え、「等身大のベトナム」の人々を描く。現地での生活や実務を豊富に経験してきた研究者・ジャーナリスト・政府系職員・NGO関係者などによって多彩な執筆陣を構成。一枚岩ではない多様なベトナムの人々の価値観や生活を汲み取ってもらいたい。
目次
1 「ベトナム」の成り立ち
2 大地と水、ムラとマチ
3 「公平・民主・文明的な社会」を目指して
4 グローバル化する文化と「民族文化」
5 ドイモイ下における政治の諸相
6 「工業化・現代化」への道
著者等紹介
今井昭夫[イマイアキオ]
東京外国語大学外国語学部助教授。ベトナム地域研究専攻
岩井美佐紀[イワイミサキ]
神田外語大学外国語学部国際言語文化学科助教授。社会学博士。ベトナム農村研究専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゅう
Sobbit
kamome46
Great Eagle
Ryotaro Sato
-

- 和書
- ベーシック国際関係論