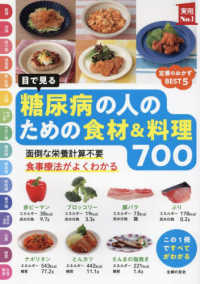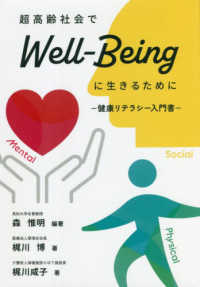出版社内容情報
チベット仏教を軸にチベット人の思想,文化,歴史,生活様式を初心者にもわかりやすく伝える格好の入門書。本書をひもとくことで,過去から現在,そして未来へとつながるチベット人の精神性の一端をかいまみることができよう。
はじめに
1 聖者たちのチベット
第1章 観音菩薩に祝福された民――開国伝説
第2章 “世界の屋根”チベット高原――チベットの地理
第3章 聖王たちの古代王朝――古代チベット王国と仏教
第4章 チベット最古の宗派――ニンマ派
第5章 チベットの“心臓”――聖都ラサ
第6章 世界宗教への道――後伝仏教総論
第7章 モンゴル帝国を擒にしたチベット仏教――サキャ派
第8章 密教行者のコミュニティ――カギュ派
第9章 整然とした僧団秩序――ゲルク派
第10章 東洋の法王庁・垂直のヴェルサイユ――ダライラマ五世とポタラ宮
第11章 “中国”はチベット仏教圏の不可分の一部である――中国とチベット八〇〇年史
2 雪の国の仏教
第12章 チベットからみたインド仏教――インド仏教略史
第13章 無尽蔵の智慧の宝庫――チベット仏教の聖典
第14章 時を超えたタントラ行者――パドマサンバヴァ
第15章 吟遊するヨーガ行者――ミラレパ
第16章 文殊菩薩の啓示を受けた大学僧――ツォンカパ
第17章 覚りへの道のガイドブック――ラムリム
第18章 ディベートの楽しみ――論理学
第19第33章 薬師仏の浄土――チベット医学入門
第34章 世界を読み解く手がかり――チベットの占い
第35章 タントラに基づく暦――チベットの暦
第36章 諸天がはたらきかける未来――護法尊
第37章 仏教国で生き続けたマージナルな宗教――ボン教
4 チベット・オリエンタリズム
第38章 名探偵ホームズの秘密――チベットをめざした探検家たち
第39章 シャングリラの原像――隠された聖地の伝説
第40章 臨死体験の手引き――チベット死者の書
第41章 ティンセルタウンのチベット・フリークたち――ハリウッドとチベット仏教
第42章 ロックでチベット支援――世界で盛り上がるチベット文化支援
第43章 “秘境”はそれほど遠くない――チベットを旅する人のために
5 チベットのいま
第44章 チベット高原サンクチュアリ化計画――弾圧と環境破壊
第45章 自由と真実を求めて――チベット人たちのいま
第46章 リトル・ラサ――ダラムサラとチベット亡命政府
第47章 ダライラマの悲しき陰画――パンチェンラマ
第48章 ミレニアムの亡命劇――二人のカルマパ
第49章 草原の民のアイデンティティー探し
はじめに
チベットという“国”がこの世から姿を消しておよそ半世紀の時がすぎた。しかし、今なおチベットは人びとの口の端にのぼり、その文化は人びとを魅了し続けている。チベット文化の存続を願う人びとは年を追うごとに増え、チベット文化に対する認知度はかつてないほど広く、深いものとなっている。
国を失っても、そのアイデンティティが崩壊するどころかよりいっそう鮮明となり、さらに外国人までまきこんでひろがってきたその理由は何であろうか。言わずと知れたことだが、チベット文化、とりわけ仏教文化には国境や民族を超えて通用する普遍的な性格があるからである。
本書はこのように世界中で評価を受けているチベット文化の様々な側面を、過去から現代に至るまで、また、内と外の視点から総合的に紹介することを目的としている。これまでのチベット入門書に比べれば、章立てや内容が網羅的かつ専門的になるよう心がけたつもりである。
第1部の「聖者たちのチベット」では、開国に始まり中国の侵入によって終わる伝統的なチベット世界の歴史を、チベット人の信じるがままに紹介した。なぜ、史実を客観的に述べるのではなく、チベット人の思考をなぞるのかといえば、見たチベット・イメージ」が第3部のテーマである。
そして、最後の第5部「チベットのいま」は、ダライラマ、カルマパ、パンチェンラマなどの現代を生きる高僧達に焦点をあててチベット人が今現在直面している問題をあぶりだした。
第5部の最終章であると同時に、本書全体の最終章でもある第五十章に据えられているのが、ダライラマ十四世の人と思想である。ダライラマは太古にチベットを祝福した観音菩薩の化身であり、開国の王ソンツェンガムポの転生であるという意味では、第1部で扱った神話の体現者である。そして、彼が仏教哲学の大家であるという点では第2部で扱ったチベット仏教の体現者といえ、伝統的な僧院社会に生きる現代チベット人としては、第3部で扱ったチベットの日常文化の体現者といえる。また、彼の聖者としての生き方が西洋人の持つチベット・イメージを裏切ってこなかったことから、第4部で説かれたチベット・オリエンタリズムの体現者として位置づけられる。つまり、ダライラマこそがまさに、神話と現実の接点にあって、チベット文化のあらゆる側面を奇跡のように体現する人物なのである。このような意味でダライラマ十四世は本書を総括する第五十章に据えられた
内容説明
本書は世界中で評価を受けているチベット文化の様々な側面を、過去から現代に至るまで、また、内と外の視点から総合的に紹介することを目的としている。1では、開国に始まり中国の侵入によって終わる伝統的なチベット世界の歴史を、チベット人の信じるがままに紹介した。2では、チベット仏教をテーマとし、3では、仏教以外の生活文化、ボン教、医学、音楽、占星術などについて扱った。4では、「外部から見たチベット」像を扱った。5は、ダライラマ、カルマパ、パンチェンラマなどの現代を生きる高僧達に焦点をあててチベット人が今現在直面している問題をあぶりだした。
目次
1 聖者たちのチベット(観音菩薩に祝福された民―開国伝説;“世界の屋根”チベット高原―チベットの地理 ほか)
2 雪の国の仏教(チベットからみたインド仏教―インド仏教略史;無尽蔵の智慧の宝庫―チベット仏教の聖典 ほか)
3 暮らしの文化(ラサ近郊のある農家の暮らしから―チベットの衣食住;解脱へと近づくために―チベット仏教の僧院生活 ほか)
4 チベット・オリエンタリズム(名探偵ホームズの秘密―チベットをめざした探検家たち;シャングリラの原像―隠された聖地の伝説 ほか)
5 チベットのいま(チベット高原サンクチュアリ化計画―弾圧と環境破壊;自由と真実を求めて―チベット人たちのいま ほか)
著者等紹介
石浜裕美子[イシハマユミコ]
早稲田大学大学院文学研究科史学科(東洋史学専攻)後期課程単位取得退学。文学博士。日本学術振興会特別研究員を経て、現在、早稲田大学教育学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
土偶
Yoshiki Ehara
akko
アルパカさん
-

- 電子書籍
- アルタスの東風【タテヨミ】第95話 恋…
-
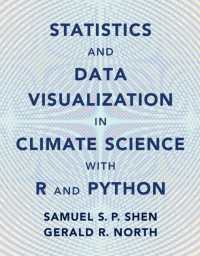
- 洋書電子書籍
- RとPythonを用いた気候科学におけ…