出版社内容情報
アジア16の国・地域の新聞・マスコミは、イラク戦争や米国の中東政策、各国の国連外交をどう評価していたか。各国・地域の政権、国民の対応と新聞論調の動向をアジア各国の地域研究者がレポートする。
序●メディアにみる各国・地域の考え方の相違[松井和久・中川雅彦]
総論●アジアにおける反米輿論[松井和久・中川雅彦]
インドネシア1●宗教対立を否定、経済への影響を懸念[松井和久]
インドネシア2●地方都市ジョグジャカルタにおける反応[川村晃一]
マレーシア●戦争反対で政府・野党・市民が一致[中村正志]
パキスタン●国連安保理での「踏絵」を免れた政府[牧野百恵]
バングラデシュ●米国関与の長期化が「ジレンマ」を軽減[村山真弓]
インド●冷静かつ実際的な対応[近藤則夫]
中国●米国への非難に終始[佐々木智弘]
朝鮮民主主義人民共和国●次の標的になることを強く警戒[中川雅彦]
ベトナム●ベトナム戦争経験者としての反戦の主張[坂田正三]
ラオス●歴史的経験にみる反戦とアメリカの脅威[山田紀彦]
台湾●遠くの戦争より隣の肺炎[佐藤幸人]
スリランカ●自国の和平プロセスに対する影響を懸念[荒井悦代]
タイ●小国の曖昧なる中立宣言[重冨真一]
シンガポール●イラク攻撃を支持するも、アメリカの一極支配には疑念[加藤学]
フィリピン●アメリカ支持の政府、アメリカ批判のメディア、家族を案ずる国民
本書は、二〇〇二年一月に刊行された『アジアは同時テロ・戦争をどう見たか』(重冨真一・中川雅彦・松井和久編、明石書店)の続編として、主に各国の現地語新聞等の社説、論評、報道等を材料に、二〇〇三年三月二〇日に始まった米英軍を主力として豪州軍が加わった連合軍のイラク攻撃に対して、アジア諸国がどのような反応を見せたかについてまとめたものである。
二〇〇一年九月一一日に起こった同時多発テロについては、アジア諸国をはじめ世界の多くの国々は「テロリズムに反対する」ということで基本的に一致していた。米軍がアフガニスタンのターリバーン政権を武力で攻撃した際にも、輿論ではアメリカの軍事行動に対する批判があったにしろ、政府による公式のアメリカ非難はほとんど見られなかった。政権担当者としては、アメリカの行動に不満があったにせよ、自国でのテロは望ましいことではなく、また、アメリカを敵に回すのを避ける必要があったのであろう。
ターリバーン政権に対する攻撃の場合と違って、今回のイラク攻撃についてアジア諸国では政府レベルではっきりと反対を表明している国々が目立つ。政府がアメリカの行動を支持した国々でも、国内の輿論は必ずしもそれと同問題にされているのであろうか。さらに、アメリカはイラクとテロリズムとの関係を指摘しているが、アジア諸国は今回のイラク攻撃を「テロとの戦い」と認識しているのだろうか。これらの問いへの解答は、本書の各論を読んで判断していただきたい。
序 編者
内容説明
本書は、二〇〇二年一月に刊行された続編として、主に各国の現地語新聞等の社説、論評、報道等を材料に、二〇〇三年三月二〇日に始まった米英軍を主力として豪州軍が加わった連合軍のイラク攻撃に対して、アジア諸国がどのような反応を見せたかについてまとめたものである。
目次
総論 アジアにおける反米輿論
インドネシア(宗教対立を否定、経済への影響を懸念;地方都市ジョグジャカルタにおける反応)
マレーシア―戦争反対で政府・野党・市民が一致
パキスタン―国連安保理での「踏絵」を免れた政府
バングラデシュ―米国関与の長期化が「ジレンマ」を軽減
インド―冷静かつ実際的な対応
中国―米国への非難に終始
朝鮮民主主義人民共和国―次の標的になることを強く警戒
ベトナム―ベトナム戦争経験者としての反戦の主張
ラオス―歴史的経験にみる反戦とアメリカの脅威〔ほか〕
著者等紹介
松井和久[マツイカズヒサ]
アジア経済研究所地域研究第1部主任研究員
中川雅彦[ナカガワマサヒコ]
アジア経済研究所地域研究第1部研究員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 【デジタル限定】丸山りさ写真集「ひたむ…


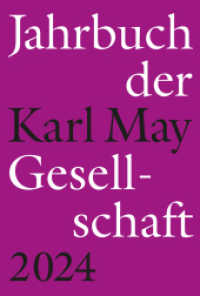

![小学館おふろポスター 名探偵コナンの日本地図 - 47都道府県 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40994/409942510X.jpg)


