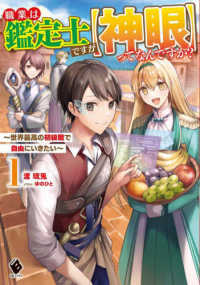出版社内容情報
教育学者フレイレの生涯や,留学生の作文などを紹介しながら,異文化をどう捉え,それを自分の中にどう取り込んでいくか,多文化とどう対話していくかという筋道を,心理学的なプロセスを辿って考察。「多文化社会にいかにして適応していくか」という現代的課題に迫る。
第1章 かかわりあいとしての文化
はじめに/「文化」をみる視点/こころのプログラムとしての文化/文化とは何か/文化どうしの接触とこころの反応
第2章 多文化にひらく
はじめに/外発的にひらくことの問題点/内発的にひらくということ/内発的にひらくための鍵概念「創造性」
第3章 多文化との対話への心理学的メカニズム
はじめに/ブラジルの教育者パウロ・フレイレをとおして考える対話力/対話理論/ことばによる対話力発達の心理学的メカニズム
第4章 多文化との対話を生きた人たち
はじめに/福澤諭吉:福澤諭吉をとおして考える内発的発展/新渡戸稲造:明治が生んだ対話的能動性
第5章 多文化との対話の七つの物語
はじめに/共生の思想をもつ/こころの触れあいを感じる/こころをつなぐ“ことば”を身に付ける/自然への関心を共有する/本当のやさしさをもつ/相手文化への興味を適切な方法で表現する/身体と精神で相手の話を聴く姿勢をもつ
目次
第1章 かかわりあいとしての文化
第2章 多文化にひらく
第3章 多文化との対話への心理学的メカニズム
第4章 多文化との対話を生きた人たち
第5章 多文化との対話の七つの物語
著者等紹介
倉八順子[クラハチジュンコ]
多文化対話教育研究者、教育学博士。1955年生まれ。慶応義塾大学卒業、銀行勤務、海外日本人学校英語教諭、慶応義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻博士課程修了、明治大学専任講師、助教授を経て多文化対話教育研究所を設立。現在、チャータースクール東京賢治の学校にて対話教育の実践活動にあたる。専門はコミュニケーション心理学。フレネ教育研究会会員。異文化間教育学会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 燃える果樹園 文春文庫