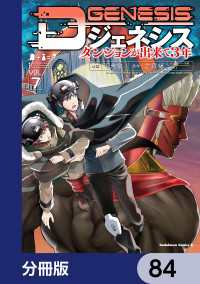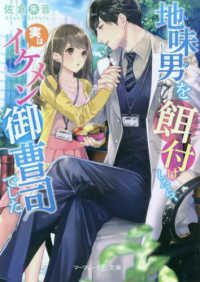出版社内容情報
多動な(ADHD:注意欠陥多動性障害をもつ)子どもたちにどのように向き合ったらよいのか? 子どもたちをより深く的確に知るためには? 教育現場で求められる実践は? 教師に,保護者にむけて経験豊かな執筆陣がネットワークのなかでの育みを提唱する。
第1章 多動な子どもの医学・医療
ADHDの概念および診断基準/ADHDとその他の発達障害/ADHDの原因仮説とその医療/ADHDの心理・認知面の特徴/心理・認知を踏まえた環境設定とは
第2章 多動な子どもの教育
多動な子どもの教育システム/多動な子どもの指導/多動な子どもと通級による指導
第3章 多動な子どもとコミュニケーション
言語・認知の特徴/パニック状態への対処/多動な子どもへの運動指導
第4章 多動な子どもたちと社会性の発達
社会性とその発達段階/自分との「対話」が育てる社会性
第5章 多動な子どもたちをネットワークで育む
目次
第1章 多動な子どもの医学・医療(ADHDの概念および診断基準;ADHDとその他の発達障害 ほか)
第2章 多動な子どもの教育(多動な子どもの教育システム;多動な子どもの指導 ほか)
第3章 多動な子どもとコミュニケーション(言語・認知の特徴;パニック状態への対処 ほか)
第4章 多動な子どもたちと社会性の発達(社会性とその発達段階;自分との「対話」が育てる社会性)
第5章 多動な子どもたちをネットワークで育む(共通の約束やルールの中で育てる;連携をスムーズにする要因、阻む要因 ほか)
著者等紹介
石崎朝世[イシザキアサヨ]
東京医科歯科大学医学部卒。東京女子医科大学小児科、都立府中療育センターを経て、現在(社)発達協会王子クリニック院長。医学博士・小児科医
湯汲英史[ユクミエイシ]
早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、(社)発達協会王子クリニック心理・言語指導室担当、同協会事務局長。言語聴覚士・社会福祉士・精神保健福祉士
一松麻実子[ヒトツマツマミコ]
上智大学文学部社会福祉学科卒、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院聴能言語専門職員養成課程卒、白百合女子大学大学院文学研究科発達心理学専攻修士課程修了。現在、上智大学文学部社会福祉学科「障害児心理学」担当、(社)発達協会開発科科長。言語聴覚士・社会福祉士・精神保健福祉士
水野薫[ミズノカオル]
千葉大学教育学部養護学校教員養成課程卒、東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了、東京都公立学校教員、東京都教育委員会指導主事を経て、現在、よこはま発達クリニックセラピスト、IEPのびのび教室指導員、ながやまメンタルクリニック臨床心理担当。学校心理士
黒川君江[クロカワキミエ]
千葉大学教育学部卒。東京都公立小学校教員(情緒障害通級指導学級担任)を経て、現在、文京区立駒本小学校コミュニケーションの教室主任、全国情緒障害教育研究会常任理事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。