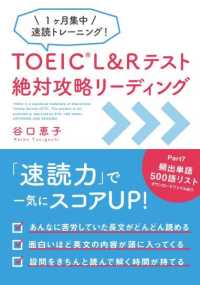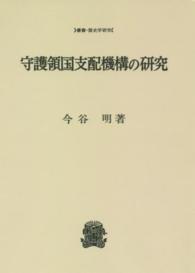出版社内容情報
国際社会秩序の維持,国際貢献のために求められる安全保障のあり方とは何か。21世紀の新たな日米関係,東アジア域内の安定化のための方向付けなど,現実的かつ画期的な安全保障論を提示する。
序 章 日米安保条約「再定義」と周辺事態法――その法と政治
第一章 日米安保「再定義」による日米同盟の意義――批判とその問題点の検討
1 市場経済システムのグローバル化と日米同盟
2 国連(安保理)決議なしの米国(および同盟国)の武力行使
3 「周辺事態法」の国際法的評価
4 在アジア米軍は「抑止力」ではなく「地域安定力」へ
第二章 南北人権観の系譜
1 グローバリゼーションと人権
2 人権観念の南北間対立
3 民族(人民)自決権の展開と変容
第三章 文明と文化そしてアジア
1 アジアの経済危機と機能的統合
2 文明と文化そしてアジア
第四章 二十一世紀における日本の安全保障
1 日米安保条約の「再定義」
2 「日本周辺」有事と日米安保体制――有事利用(駐留)のすすめ
3 日本の安全保障の環境特性
内容説明
二十世紀末の1999年、小渕政権は多くの法律を一挙に成立させた。成立した法律とは、周辺事態法等のガイドライン関連法、通信傍受法、改正住民基本台帳法、国旗・国歌法等、多くの行政立法である。総じて言えば、一般市民の生活に関する国家統制的性格の強い法律ばかりである。「公共の福祉」がそうした立法を正当化する根拠とされているようである。こうして戦後の日本国民の精神生活の基盤として定着した「人権観念」は、西欧的天賦人権観から公共の福祉を広く解した「法律の留保」を認める人権観へ(人権の内在的制約論から国策的制限論へ)と急速に転換しつつあるように思われる。日本国民の人権観の時代的転機を示すものかもしれない。省庁の改編縮小は精神機能的には「小さな政府」を必ずしも意味しない実証例となるかもしれない。
目次
序章 日米安保条約「再定義」と周辺事態法―その法と政治
第1章 日米安保「再定義」による日米同盟の意義―批判とその問題点の検討
第2章 南北人権観の系譜
第3章 文明と文化そしてアジア
第4章 二十一世紀における日本の安全保障