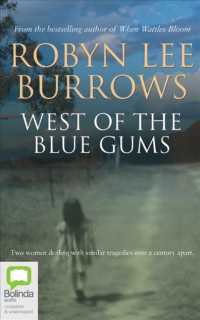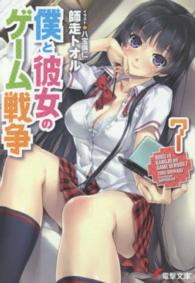出版社内容情報
明治以降の近代化政策によって新たに生み出された貧困と差別,その集中的表現形態としての都市下層社会。戦前期東京市を対象に,施設,施策の展開,社会調査の実態等を分析,その歴史的意義に迫る。
1 戦前東京の下層社会と社会事業
第1章 日清戦争後の都市下層社会における慈善事業―東京市四谷鮫河橋の二葉幼稚園を具体例として
第2章 産業革命期の都市下層社会における貧困児童教育―東京市特殊尋常小学校の展開を具体例に
第3章 昭和戦前期のスラム・クリアランス―不良住宅地区改良法の制定をめぐって
第4章 戦時局下の貧困児童への保護施策―児童虐待防止法の制定をめぐって
第5章 現場の実践者財部叶の社会事業観―石井十次に関連して
2 草間八十雄の生涯・都市下層社会調査
第6章 生涯と思想
第7章 帝国公道会での活動
第8章 都市下層民衆の生活実態調査―「細民調査」から「被虐待児童調査」まで
第9章 文明協会での活動
第10章 『女給と売笑婦』の趣旨と内容構成
第11章 東京市厚生局での活動
内容説明
競争を原理とする近代社会において、不断に生み出される社会的弱者をどのように受け容れるかという問題が、日本の近代化が開始されて以来いまだに解決されぬまま今日にいたっている。著者はここに日本の福祉問題の原点の一つがあると思っている。今日、市場原理が福祉問題の解決に導入されようとする状況にあればこそ、その問題がどのように取扱われてきたかを史的に研究することは等閑視されてよいものでない。むしろ、今日的意義はより大きいと思われる。本書では、これまでの調査研究をひとまずまとめることで、ささやかな提起を試みている。
目次
1 戦前東京の下層社会と社会事業(日清戦争後の都市下層社会における慈善事業―東京市四谷鮫河橋の二葉幼稚園を具体例に;産業革命期の都市下層社会における貧困児童教育―東京市特殊尋常小学校の展開を具体例に;昭和戦前期のスラム・クリアランス―不良住宅地区改良法の制定をめぐって;戦時局下の貧困児童への保護施策―保童虐待防止法の制定をめぐって ほか)
2 草間八十雄の生涯・都市下層社会調査(生涯と思想;帝国公道会での活動;都市下層民衆の生活実態調査―「細民調査」から「被虐待児童調査」まで;文明協会での活動 ほか)
-
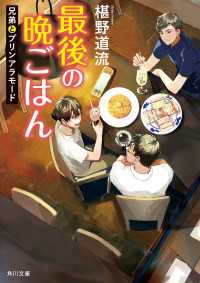
- 電子書籍
- 最後の晩ごはん 兄弟とプリンアラモード…