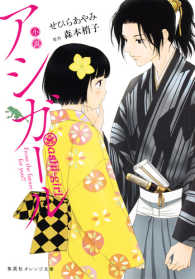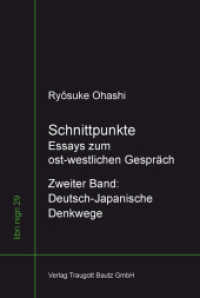出版社内容情報
「笑い」とは、批判・共感・排除・活力・包容と様々な機能をもつ、奥深いもの。人間を描く文学の「笑い」を読み解くと、その時代の価値や社会が見えてくる。本書では、和文体が形成し始める平安前期の『土佐日記』を、「笑い」という新たな観点で見つめ、『竹取物語』からは「笑い」を通して、「集団主義」と「恥」の現象について考察する。そして、『源氏物語』を、作品そのものとしての「笑い」をテーマにして論じ、これまで充分に論じられてこなかった側面に光をあてる。古典文学や和語を起点に、当時の日本文化と、現代に通じる人々の意識を抽出する異色の文学論。
目次
第1篇 平安前期の和文における笑いの諸相(「笑い」論の展開と文学における笑いの領域―特に平安前期の和文に照らして;『土佐日記』の方法としての笑い―非日常空間における仮名日記の試み)
第2篇 平安中期までの「人笑へ」言説(日本文化論との接点から見る古典における「恥」の言説―『竹取物語』とその前後;中流階級の女性における「人笑へ」、そして恋―平安貴族に仕えた女房格の作者を中心に;平安貴族の道徳感情、「人笑へ」言説―平安中期までの系譜学的考察)
第3篇 『源氏物語』の諧謔性と笑い(頭中将と光源氏―「雨夜の品定め」の寓意性;『源氏物語』における「女」と「仏」―若紫巻における喩としての「仏」を中心に;玉鬘十帖の笑い―端役から主要人物への拡がり;男女関係に用いられる「たはぶれ」の一考察―平安前期の作品における解釈の問題をめぐって;『源氏物語』時代の「たはぶれ(る)」攷―物語における色恋の生成)
著者等紹介
金小英[キムソヨン]
韓国釜山大学校日語日文学科卒業。2013年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。2012年、同博士後期課程に在学中、アメリカのコロンビア大学と早稲田大学とのDDP(Double Degree Program)により修士学位を取得。以後、釜山大学校日本研究所専任研究員、全南大学校人文大学学術研究教授を経て、現在、釜山大学校非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。